 |
| 漫画版の「竜馬がゆく」は面白いですよ |
司馬遼太郎さんが描いた坂本龍馬の魅力と世界観をさらに楽しめる
幕末の動乱期が舞台で明治維新の志士が主人公の漫画は、昔も今も大人気です。
そんな幕末ジャンルで多くの作品に主役として登場しているのが坂本龍馬。志士たちの中でも人気のある偉人。だから、
「坂本龍馬が主人公で、彼の波乱の生涯を描いた面白い漫画ってありますか?」
そんな声がたくさんあります。
ここ最近で連載されている漫画作品では「週刊文春」で掲載中の「竜馬がゆく」。
国民的な歴史作家・司馬遼太郎さんの代表作でもある同名小説を、漫画家・鈴ノ木ユウさんがコミカライズした作品です。
ただ司馬さんの作品は「英雄・龍馬」像を作ったといわれるほど。龍馬ファンにとって、まさにバイブル。それだけに、
「漫画版って、司馬さんの原作と比べて面白いですか?」
「漫画版は原作の龍馬のイメージや世界観を壊さずにストーリーを描けているのかな?」
「竜馬がゆく」のファンからは、そんな声がたくさん上がっているんです。
そんな心配はご無用! 漫画版は司馬さんの原作と同じくらいドキドキワクワクさせてくれて面白いんです。
この記事では、原作の人気要素をバッチリ押さえた漫画版がストーリー上で展開している魅力的なポイントをピックアップ。
- 龍馬の人間形成に影響を与えた姉・乙女との絡みが濃厚でジ〜ンとくる
- 序盤から龍馬の「名言」が紹介されストーリーの伏線になっている
- 剣に生きる志士たちの剣闘シーンが迫力満点に描かれている
上記の3つの魅力について紹介&解説します。
この記事を読めばナットク&マンゾク。龍馬の波乱に満ちた生涯が分かります。
司馬さんの原作の人気要素を漫画版がバッチリ押さえているので、原作のイメージや世界観の魅力をより高めていて面白いことが分かります。
さらに漫画版のページを開いてストーリーを楽しみたくなりますよ。
※この記事では作品中の表記としての「竜馬」と、歴史資料などで記されている「龍馬」を使い分けています。
「竜馬がゆく」ってどんな作品なの?
★鈴ノ木さんの描く龍馬がカッコいい
漫画版の「竜馬がゆく」は、「週刊文春」2022年5月5・12日合併号から連載がスタート。
単行本は計10巻(2025年1月1日時点)が発売中です。
前述した通り、原作は国民的作家・司馬さんの筆による同名小説。作画は漫画家・鈴ノ木ユウさんが担当しています。
ストーリーは原作をほぼ踏襲。土佐(高知)の郷士・坂本家で生まれた龍馬が、風雲急を告げる幕末の日本で活躍。
日本初の商社&海軍を創設し薩長連合や大政奉還など明治維新に貢献した、劇的な生涯が描かれています。
作画を担当する鈴ノ木さんの代表作といえば、「モーニング」で連載していた「コウノドリ」。
主人公の男性産科医がトラブルを抱える患者たちに寄り添い、悩みを解決していく人間ドラマが秀逸な作品。
詳細な描き込みで登場人物の心理描写が絶妙な鈴ノ木さんの絵のタッチは、司馬さんが描いた「竜馬」の姿とマッチしています。
★司馬さんの原作の魅力をさらに倍増
司馬さんが描いた「竜馬がゆく」は、1963年から1966年まで「産経新聞」夕刊で連載。
現在は文藝春秋から単行本(全5巻)と文庫版(全8巻)が発売中です。
司馬さんの作風は、主人公の史実や歴史的な事実&背景を土台にしてフィクションをたくみに交えるスタイル。
「竜馬がゆく」を読んだファンは「龍馬の真の姿を描いている」とハマってしまう魅力に満ちています。
今では龍馬研究が進み、龍馬のさまざまな側面や新事実が発表されています。
それでも龍馬の物語といえば「竜馬がゆく」があげられるなど、今も人気が続いています。
令和の時代でも読み継がれる理由は前述した、
- 龍馬の人間形成に影響を与えた姉・乙女との絡みが濃厚でジ〜ンとくる
- 序盤から龍馬の「名言」が紹介されストーリーの伏線になっている
- 剣に生きる志士たちの剣闘シーンが迫力満点に描かれている
上記の3つの魅力といえます。漫画版でもこの3点がバッチリと描き込まれていて、原作の魅力を倍増している感じ。
ここからは3つの魅力について、1つずつ紹介&解説していきます。
1.龍馬の人間形成に影響を与えた姉・乙女の絡みが濃厚でジ〜ンとくる
★土佐のお仁王さま
龍馬の姉で男まさり、弟から「乙女大姉」と愛された坂本乙女(おとめ)。
司馬さんの原作と同様、漫画版でも龍馬に関わる重要人物としてストーリーに登場しています。
龍馬にとって、乙女は「育ての母」。それも弟にスパルタ教育を施した豪快でチャーミングな女性として描かれています。
乙女は父・坂本八平(直足)と母・幸の三女として土佐で誕生。龍馬は3歳下の弟になります。
身長は175センチ(5尺8寸)、体重は112キロ(30貫、おそらく中〜晩年)。
龍馬もストーリー上で身長5尺8寸(高知県立坂本龍馬記念館によると、173〜179センチ)とされ、乙女とほぼ同じ。
娘さんのころから体格がよかった上に、薙刀・剣術・馬術・水泳など武芸が達者。
さらに琴や三味線・舞踊・謡曲などや、和歌や経書(儒教の経典)などの文芸もマスター。まさに文武両道の女傑。
高知城下では「土佐のお仁王さま」と呼ばれていました。
★龍馬の育ての母
乙女と龍馬の母・幸は体が弱く、龍馬を身ごもった時は40歳を越えていたそうです。
だから年の離れた龍馬をメチャかわいがった。でも龍馬が10歳のころ、他界しました。
優しかったお母さんを亡くして、龍馬はメソメソ。おねしょも治らなくて「よばあ(寝小便)たれ」とバカにされていました。
しかも勉強もできなくて、通っていた学塾(寺子屋)を追い出されたんです。
そんな龍馬を母に代わって育て、鍛えたのが乙女。弟をコテンパンにして、父や兄・権平が止めるまでやめなかった。
漫画版のストーリーでも、そのスパルタぶりが描かれています。
池から上がろうとする竜馬の顔を足でけって、再び池にたたき込む。「いいかげんにせんか」とたしなめる父・八平に、乙女は毅然として反論。「竜は雨や雲を得て天高く昇るといいますから、水につけて本当の竜になるかどうかを試しているんです」
「おまんだけと思うなよ。父上も兄上も姉さんらも、母上が亡くなったことを必死に堪えて乗り越えようとしとるがじゃ」「いつかあの世で母上と会った時、おまんは何を母上に伝える?」「私はえへんと胸を張って、竜馬を立派に育てたじゃろと自慢したい! おまんは違うがか ⁉︎」竜馬は「わしがたくましい男になったら、母上はほめてくれるかのう…」。
幼いころは気弱で寝小便たれだった龍馬にとって、乙女は唯一の応援団長でした。
「昔から他の子と比べると、目の光が違っていた」「龍馬は絶対に大物になる」と信じ、弟を鍛え続けました。
読み書きなど必要な学問も姉に鍛えられ、できるようになる。経書や漢籍も姉に教えられ独創的な解釈で学者を驚かせたほど。
坂本家の本家は「才谷屋」という屋号で質屋などを営む豪商でした。郷士という「士分」を買って本家から独立したんです。
2人は坂本家に漂う商人の空気の中で育ちました。龍馬が他の志士とは違う商人的な思考と活動で一目置かれた理由とされています。
さらに同じ空気の中で育った乙女のスパルタもあって、〝異彩の志士・龍馬〟が生まれたんだと思います。
長じて志士となった竜馬は、日本中を駆けめぐって活動しました。そんな忙しい日々でも欠かさず送っていたのが乙女への手紙。
自分の近況や政局と自分の考え、遭遇した事件などを事細かく分かりやすい文体(口語体)で姉に伝えていました。
また、聞きつけた姉の悩みごとに対するアドバイスまで送っていました。
乙女への手紙は16通が現存していて、おかげで龍馬の人柄や思想が分かる。幕末の政局も分かる第一級の資料です。
龍馬という風雲児を育て、しかも歴史的な資料を後世に残す。乙女はまさに女傑。
そんな乙女の姿を漫画版では生き生きと描いている。乙女と龍馬の絡みはストーリーの読みどころでもあるんです。
2.序盤から龍馬の「名言」が紹介されストーリーの伏線になっている
★読めば勇気100倍になる
幕末の志士の中でも、龍馬はさまざまな名言を残したことで有名です。
勉強や進学・進路など、悩み多き若者が読めば勇気100倍になるような、しびれるようなセリフが龍馬の人気の秘密でもあります。
最も有名なモノでは、龍馬が乙女にあてた手紙の中で記された「日本を今一度せんたくいたし申候」でしょう。
旧態依然として、欧米列強が迫る世界情勢に対応できない日本の改革を誓った言葉です。
龍馬の名言も彼の考え方や人間性が分かる貴重な資料といえます。
司馬さんの原作ではストーリーの進行とともに紹介されていきますが、漫画版では序盤からふんだんに登場しています。
★座禅するより歩けばいいじゃないか
第3話では「座るより歩けばいいじゃないか」。この名言と逸話がカッコいい!
当時の武士の間では、たしなみとして座禅が推奨されていました。いざ戦場に向かう際の精神力を養うためでした。
武市は「座禅は己と向き合い、死を恐れぬ精神を身につけられる」。これに竜馬は「そんなもんは座るより歩けばいいじゃないか」。
土佐の風習である「女正月(城下の女性が武家商家を問わず自由に行動できる日)」に、竜馬は町娘のハツと知り合う。ハツに「おかしな歩き方」と笑われ、竜馬は「座禅をしとる」と答える。「15歳ん時から、いつ頭上から岩石が降ってきても平然と死ねる工夫をしながらひたすら歩いちょる」。「じゃが、襲いかかる岩石を空想すると無性に怖い」。
稽古後に家路につく竜馬の後ろ姿を見て、師範代の土居揚五郎がつぶやく。「たしかに大きい。うしろが斬れぬわい」
龍馬の名言でもう一つ有名なモノとして「世の人は我を何とも言わば言え。我がなす事は我のみぞ知る」があります。
司馬さんの原作では、薩摩・長州・土佐などの尊攘派が京で活動していた一方で、龍馬が幕臣の勝海舟の弟子となったころ。
勝から黒船の操船を学んでいる龍馬へ、仲間の志士たちが「こんな大変なときにアイツは何をしてるんだ」と陰口をたたいていた。
その際に龍馬が「世の人は我を何とも言わば言えー」と語った。司馬さんはそう記しています。
日根野道場から小栗流目録を与えられた竜馬に対し、坂本家ではさらに大流派を修行させるため江戸に留学させる。江戸への旅立ちの際、竜馬は見送りにきた土居師範代にこぼす。「寝小便たれだったわしが江戸で通用するんじゃろうか」。土居は「強い弱いなど、他人が勝手に噂するもんじゃ。ただ自分を信じてぶつかってくればそれでいい」。竜馬は「世の人は何とも言わば言え。我がなす事は我のみぞ知る、そういうことじゃな」。
ストーリー序盤で、若いころから龍馬は他人に馬鹿にされても我が道をいく強いハートの持ち主であると強調している。
そして天下の浪人になって京・大坂(今の大阪)で飛躍を目指す時期に、強いハートで目標に向かって突き進む。
そんな伏線になっていると考察します。
★皆が仲良う遊べるようにしたい
実際に龍馬が残した名言ではないけど、龍馬の人間性と政治哲学が表れている漫画版オリジナルの名言も紹介します。
母・幸は桜の苗木に手を合わせて「竜馬がたくましく育ちますように」と祈っていた。竜馬は「それは無理じゃ。わしはケンカも弱いき、いつも皆に泣かされる」。幸は「たくましいとはケンカや剣術が強いことではないがよ」「いたわりのある者のことじゃ」。「お友達がいじめられていて」「今は助けてあげることが出来なくていい」。「いつか本当に友達を助けてあげられる自分を作り上げればいいがよ」。
「わしは、いじめた者もいじめられた者も、皆が仲良う遊べるようにしたい」
そして、ストーリー上では龍馬が混乱を極めた幕末の政局でどう動いたのか。これを示唆する「名言」なんです。
1866(慶応2)年にボッ発した第2次長州征伐で勝利した薩長は、徳川幕府の武力討伐へ舵を切ります。
このままでは内乱となり欧米列強の侵攻を許すと危惧した龍馬は、同胞が血を流すことなく事態を収拾しようと奔走します。
それが、幕府が政権を返上して日本中が一丸となり新政権を作る大政奉還案の推進でした。
前述した「皆が仲良う遊べるようにしたい」という「名言」は、龍馬が推し進めた大政奉還案につながる伏線だと思います。
3.剣に生きる志士たちの剣闘シーンが迫力満点に描かれている
★龍馬の剣技をリアルに再現
龍馬といえば、日本初の商社であり海軍でもある「亀山社中」「海援隊」を創設。
犬猿の仲だった薩摩と長州の間をとりもち「薩長連合」を斡旋。土佐藩などによる大政奉還の建白をアシストし幕府にピリオドを打たせた。
そんな活動や事績が有名です。それ以上に龍馬ファンを魅了しているのが、剣の腕前。
司馬さんの原作では、少年時代や江戸留学時の剣術修行や御前試合での剣豪ぶりの描写が素晴らしくてメチャ興奮します。
司馬さんの描写は龍馬が相手と対峙し、剣(竹刀)を激しく交わす姿が頭の中で浮かび上がるほど。
漫画版での剣闘シーンは、原作の描写をリアルに再現。迫力と緊迫感が満ち満ちていて最高!
鈴ノ木さんのペンのタッチによって龍馬の剣のスピード感と破壊力が強調されて、めっちゃ迫力があるんです。
★闘いの息づかいが伝わってくる
鈴ノ木さんは、龍馬の剣技を素晴らしいペンのタッチで迫力満点に再現しています。
門人や関係者が見つめる中、竜馬は切紙(初級の免許所持者)や古参株の目録者(中級免許所持者)を初太刀で退けた。道場中に「強い…」というつぶやきとため息が流れた。
第5話では、混乱の京で「人斬り」の異名を誇った岡田以蔵の剣闘シーンが圧巻。
足軽の身分ゆえに道場に通うことがゆるされない以蔵は、樫の木を削った重い木刀で来る日も来る日も素振りを繰り返した。素振りは実戦的な練習法とされ「素振り3年で初伝の腕」。以蔵の打ち込みのスピードは竜馬をも驚かせた。
武市に道場生との立ち会いを許された以蔵は、野生的な跳躍力と打ち込みで道場生や師範代までも圧倒。以蔵は「勝てる。勝てるぞ。道場には上士も郷士も足軽もない」。武市には豪快な突きで吹き飛ばされるが、入門を許される。
歴史資料や伝承によると、龍馬は高知城下の小栗流で中伝目録(修行の半ばで授けられる免許)を得て日根野道場の師範代に就任。
留学した江戸では千葉周作が興した北辰一刀流に入門。龍馬は周作の弟・千葉定吉の道場で塾頭を務め「免許皆伝」までいったとされています。
幕末の江戸では「北辰一刀流」「神道無念流」「鏡心明智流」の三大流派が隆盛。
多くの志士たちが門をたたき、その1つの流派で龍馬は名を上げたわけです。
一方で龍馬は「実際の剣術は弱かったのでは?」という説もあります。
北辰一刀流の免許は「初伝」「中伝」「奥伝」の3つ。「免許皆伝」は「奥伝」にあたり「大目録」が授けられます。
龍馬の場合、もらった剣の皆伝書が存在せず、現存するのは長刀(薙刀)の皆伝書のみ。
一方で2015年に「北辰一刀流兵法皆伝」=大目録を示す資料が見つかり「ホントに龍馬は強かったのでは?」と論争になっています。
龍馬が千葉道場で修行したのはわずか3年。「大目録」に至るまでは長い時間が必要とされています。
それでも千葉道場の塾頭の実力は「中目録」クラスといわれています。
わずか3年で塾頭にまで至ったことを考えると、龍馬の剣はやはり強かったんだと思います。
そんな龍馬が経験する剣客たちとの闘いを、漫画版は迫力満点に描いています。
江戸で入門した千葉定吉の長男で剣客・重太郎の華麗な太刀さばき。重太郎は父・定吉に代わり、龍馬に剣技を指南した人物。
2人の激烈な稽古での立ち会いシーンは緊迫感が漂っています。
さらに土佐藩主催の御前試合では、長州藩士で後の指導者・桂小五郎と激突。
桂は神道無念流の達人で「バッタのようにせわしない」スピードの剣を駆使。
土佐藩の代表として鏡心明智流の達人・武市が対戦する予定でしたが、武市は桂を嫌い龍馬に立ち会いを頼むんです。
桂のスピードに合わせたら負ける。そう考えた龍馬の作戦が…、豪快でカッコよすぎるんです。
この続きはぜひ作品でお読みください。
まとめ・原作の龍馬のイメージを漫画版がさらに高めている
 |
| 龍馬は魅力的な人物です |
ここまで漫画版「竜馬がゆく」の魅力について紹介してきました。
そして司馬さんの原作の人気要素をバッチリ押さえ、ストーリー上で展開している魅力的なポイントをピックアップ。
- 龍馬の人間形成に影響を与えた姉・乙女の絡みが濃厚でジ〜ンとくる
- 序盤から龍馬の「名言」が紹介されストーリーの伏線になっている
- 剣に生きる志士たちの剣闘シーンが迫力満点に描かれている
上記の3つの魅力について紹介&解説しました。
漫画版ではもちろん、龍馬の波乱に満ちた生涯が描かれています。
そして司馬さんの原作と同じくらいドキドキワクワクさせてくれて面白い!
原作の人気要素を漫画版がバッチリ押さえて、原作のイメージや世界観の魅力をさらに高めています。だから、
「坂本龍馬が主人公で、彼の波乱の生涯を描いた面白い漫画ってありますか?」
「漫画版って、司馬さんの原作と比べて面白いですか?」
「漫画版は原作の龍馬のイメージや世界観を壊さずにストーリーを描けているのかな?」
なんて方にはピッタリの作品です。この記事を踏まえて作品を読めばナットク&マンゾク。
「竜馬がゆく」の世界観にハマり、龍馬ファンになること間違いなしです。
当ブログでは、ほかにも坂本龍馬のことを紹介している記事を公開しています。
司馬さんの原作や、龍馬に関する最新の研究成果や考察について紹介中。ぜひお読みください。
坂本龍馬は薩摩藩士?フリーメーソン?暗殺の黒幕は?幕末の英雄の新事実が面白い「龍馬本」3作品
中高生におススメ!苦手な日本史が好きになる歴史小説4選と活用法
この記事で紹介した作品を「すぐ読みたい」という方は、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。
「BOOK☆WALKER」などのマンガストアなら無料で試し読みができますよ。
読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」
月額840円でマンガ単行本が20000冊以上読み放題「BOOK☆WALKER」
※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して本や商品を紹介しています。
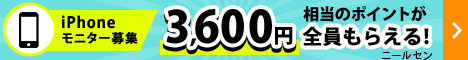

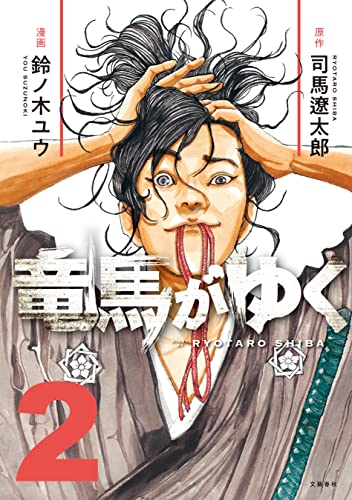

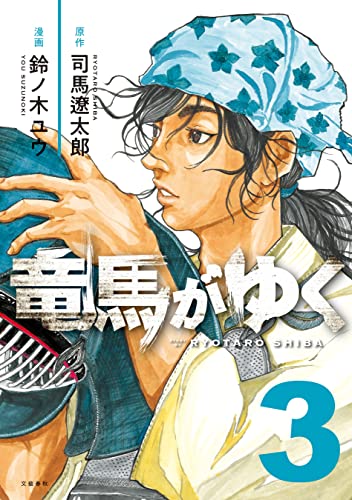

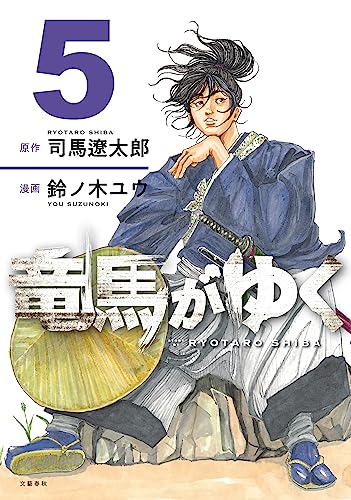






0 件のコメント:
コメントを投稿