 |
| 伝説の伝奇作家は「クトゥルフ神話」に影響を受けた |
諸星ワールドの中でも異色のブラックユーモアが楽しめる
20世紀の米国人作家、ラヴクラフトによる数々のホラー作品によって生み出された「クトゥルフ神話」。
「太古から地球に存在する異形のモノ」たちがテーマの怪奇作品は、世界中の作家や漫画家たちに今も影響を与えています。
当然ながら日本のクリエーターたちも影響を受けています。
伝奇漫画の第一人者である漫画家・諸星大二郎さんもその1人。
昭和から令和まで独特で奇怪な世界観が大人気なレジェンド作家です、それだけに、
「諸星さんもクトゥルフ神話に影響を受けていると聞いたけど、それが分かる作品を教えて!」
「クトゥルフ神話と同じくらい奇怪な諸星さんのオススメ作品を読んでみたい!」
なんて声がたくさんあるんです。
そんな方に、当ブログがオススメするのが「栞と紙魚子」。
「クトゥルフ神話」の香りが漂い、同じくらい不気味。さらに諸星さんの奇怪な世界観にシュールさとブラックユーモアが加わった名作。
まがまがしさが漂う「諸星ワールド」の中でも、異色な作品なんです。
この記事では作品の中でも「クトゥルフ神話」と同じように奇怪で、「諸星ワールド」の中でもシュールなオススメのエピソード、
- クトルーちゃん(1996年発表)
- おじいちゃんと遊ぼう(1997年発表)
- 生首事件(1995年発表)
上記の3エピソードを紹介&解説します。
この記事を読めば、諸星さんが受けた「クトゥルフ神話」の影響がよく分かる。
そして「栞と紙魚子」が持つ「クトゥルフ神話」以上に奇怪でシュールで不条理で、ブラックユーモアに満ちた世界観が分かります。
さらには実際に作品を手にしてページを開きたくなりますよ!
「クトゥルフ神話」と「栞と紙魚子」について
★太古の地球の支配者たちを描いたラヴクラフト
「クトゥルフ神話」の創始者は、米国人作家のハワード・フィリップス・ラヴクラフト。
執筆した主なジャンルはホラー。でも対象は幽霊や吸血鬼などの人間起源のアヤカシではなく、太古の地球を支配した異形のモノたち。邪神。
宇宙から飛来し過去の時代から影をひそめてきた支配者=邪神が、現代によみがえり人間社会に恐怖をもたらすーこれがテーマです。
ラヴクラフトは多くの異形のモノたちを生み出しましたが、有名なのがタコやイカの軟体動物が巨大化したような「クトゥルフ」。
ラヴクラフトの死後も後輩作家たちが彼の世界観を踏襲した物語を発表。その作品群を体系化したのが「クトゥルフ神話」です。
ラヴクラフトの代表作は、前述した、太平洋に眠るクトゥルフがテーマの「クトゥルフの呼び声」。
陰気な港町を不気味な異形のモノたちがさまよう「インスマウスの影」など。
「クトゥルフ神話」の世界観や設定は世界中のクリエーターに影響を与え、小説や映画、漫画、アニメ、ゲームに反映されました。
★諸星ワールドでも異色な「栞と紙魚子」
「クトゥルフ神話」に影響を受けた日本の漫画家はたくさんいます。
その中でも独自の世界観を構築し、伝奇ジャンルを作り上げた1人が諸星大二郎さんです。
代表作「妖怪ハンター」では、古代から存在する日本の邪神や悪鬼、妖怪たちを考古学者・稗田礼二郎が暴き出すストーリー。
小文献や遺跡などに残された、太古の地上の支配者たちの存在を明らかにするのがテーマでした。
一方で「栞と紙魚子」は、2人の女子高生が異形のモノに遭遇しトラブルに巻き込まれる物語。
主人公は2人。ロングヘアの美少女・栞(しおり)。ちょっと天然ボケでトラブルに巻き込まれちゃう。
その栞をアシストするのがメガネで三つ編みの美少女・紙魚子(しみこ)。古本店の娘で奇書好き。
遭遇する異形のモノの正体は明かされず、異形のまま。登場キャラは、そんな「非日常」的な現象を「日常」として受け入れちゃう。
その受け入れ方がとぼけた感じで、シュールで不条理でブラックユーモアにあふれた世界観が楽しめる作品です。
少女向けホラー雑誌「ネムキ」で1995年から2008年まで不定期で連載。単行本は計6巻(朝日ソノラマ版)が刊行。
2008年の第12回文化庁メディア芸術祭でマンガ部門優秀賞を受賞。
2008年には日本テレビ系で「栞と紙魚子の怪奇事件簿」のタイトルで実写ドラマ化されています。
次項からは「クトゥルウ神話」の香りが濃厚に漂い、シュールでブラックユーモアに満ちたオススメのエピソードを紹介していきます。
1.クトルーちゃん
★得体の知れない怖さが最高
1996年発表のエピソード。「栞と紙魚子」のエピソードの中で、最も「クトゥルフ神話」の香りが漂う作品。
ある日、栞は友人のピンチヒッターでベビーシッターのバイトに出かけた。栞が訪ねた家は、ずっと空き家のままの〝お化け屋敷〟といわれている一軒家。玄関に段ボールが置かれていて、中から突然女の子が飛び出してきて、「お姉ちゃん遊ぼう!」。「エイリアンごっこ。これからお姉ちゃんの顔にくっついて手を口に突っこむの」
クトルーは、飛んでいる虫を首を伸ばして食べたり、首を180度回して「テケリ・リ」と叫んではしゃぎまわる。父はホラー作家・段一知(だん・いっち)。お母さんは外国人で巨大な顔。クトルーが悪ふざけすると手を伸ばしてはたく。
クトルーに「本を読んで」と頼まれ、ページを開いたら不気味な生物が飛び出す〝立体絵本〟。あるページを開いたら、クトルーのペット「ヨグ」が飛び出してきて、手に持った包丁で栞に襲いかかってきた…。
★「クトゥルフ神話」のキャラが由来
栞がクトルーちゃんの家で遭遇するキャラたちは、いずれも不気味すぎ。
そしてキャラたちの名前やしぐさは「クトゥルフ神話」に由来しているんです。
クトルーちゃんの名前は、前述した邪神たちのボスキャラの1人「クトゥルフ」。
彼女が叫ぶ「テケリ・リ」はラヴクラフトの「狂気の山脈にて」に登場する、太古に地球へ飛来した巨大生物ショゴスの鳴き声。
お父さん「段一知」は、「ダンウィッチの怪」に登場する架空の村の名前。彼の容貌のモデルは、まさにラヴクラフト。
そして「お母さん」。巨大な顔とトンデモなく長い手。グニャグニャした軟体動物や節足動物のような足を何本も持っている。
栞と紙魚子が暮らしている「胃の頭町」に存在するアヤカシたちから尊敬を集めている。まさに巨大で異様な邪神のよう。
太古の邪神が遠縁で、邪悪な魔導士によって地球に召喚された際に段氏と知り合ったのがなれそめだそうです。
栞と紙魚子が暮らしている「胃の頭町」では、クトルーちゃんのペット「ヨグ」をはじめ不気味な生物がたくさんいます。
街中でチョロチョロしているのが、「お母さん」の故郷(くに)の生物「ムルムル」。
猫ぐらいのサイズで背中に羽がある生き物。お母さんが捕まえてはおやつとしてパクリ。「ヨグ」が呪文で呼び出しているんです。
その「ヨグ」は、ラヴクラフトの各作品に登場する邪神「ヨグ=ソトース」の名前が由来とのこと。
このヨグが不気味。凶悪な人間のような顔に、体と手足にぐるぐる渦巻きマークが無数。包丁を手にして襲ってくる…。
「クトルーちゃん」というエピソードでは、「クトゥルフ神話」のキャラたちが暴れまくっているワケです。
★「クトゥルフ神話」を昇華
紙魚子は家の手伝いで、蔵書を買い取るために段一知の家を訪問。積まれていた飛び出す絵本を開いた。ページには栞が段家を訪問してからの出来事が描かれている。最後には栞がヨグと飛び出してきて、紙魚子と逃げ出す…。
時空を超越する不可思議な諸星ワールド。「クトゥルフ神話」もそのベースになっています。
第1巻の巻末(朝日ソノラマ版)にある「あとがき」では、諸星さんが「クトゥルフ神話」との〝なれそめ〟を明かしています。
ラヴクラフトを読んでいたのも随分昔なので(なんと20年前くらい前?)、まあパロディというほどのものでもないと思って下さい。
諸星さんは「クトゥルフ神話」の「太古から地球に存在する異形のモノ」というテーマに影響を受けつつ、自身の世界観を展開した伝奇作品を創作。
さらにブラックユーモアとシュールさを加えることで「クトゥルフ神話」を昇華。
そして、自身の作品群の中でも〝異色さ〟が際立っているのが「栞と紙魚子」なんです。
2.おじいちゃんと遊ぼう
★クトルーちゃん一家の秘密を最初に披露
1997年発表のエピソード。「栞と紙魚子」の中で、クトルーちゃん一家は準レギュラー的なキャラ。
ある日の道端で栞は段一知とバッタリ。段は「大きな塀のようなものを探してる」「小説のヒントにしたい」と明かす。栞は近所にある大きな塀を紹介する。一方で紙魚子から、段と会った日の夜の事件を教えられる。夜道で巨大な顔の女性にあいさつされた。大きな壁が夜道を歩いていた。隣町の工場のガスタンクを転がす女性を目撃した。「もしかしてクトルーちゃんのお母さんじゃない?」。2人が段家に行くと、庭に大きな壁やガスタンクがあった…。
「夜中に地震があって段家に雷が落ちた」「その後、屋根の上に真っ黒い影が2つ現れ、大声で笑った」段家の庭では、ペットのヨグが頭を抱えて震えている。さらに玄関からお邪魔すると異空間に落ちてしまう。段がいる部屋は異様な雰囲気で地下鉄が走り抜けたり。段は「大柄なお客さんがきていて、よその空間を借りてきた」。クトルーによると「(ママの)おじいちゃんとおばあちゃんがきてるんだよ」。
クトルーちゃんはパパの仕事の邪魔にならないように、隣の部屋でおじいちゃんとおばあちゃんに遊んでもらっていました。
栞と紙魚子が「ちょっとだけ」と隣室をのぞくと、2つの巨大な顔で埋まった異様な空間でクトルーちゃんが遊んでいるんです。
★おじいちゃんとおばあちゃんは高位の邪神⁉︎
前述した通り、クトルーちゃんのお母さんは巨大な顔に長〜い手と節足動物のような無数の足の持ち主。
そんなお母さんの両親は、彼女以上に巨大で異様。そしてこの2人はどこから来たのか?
段氏はご近所の人たちに「妻は外国人」と説明。でも「外国人」というより「エイリアン」ですよね。
段夫妻は両親がどこからきたのかは明かしていませんが、間違いなく異次元、異世界、もしくは宇宙。
「ほかに方法がないし、交通費もかからないから」
何しろお母さんが祭壇で呼び出したときには雷が落ち、地震が起きた(近所の主婦談)ほどですから。
だから孫のクトルーちゃんと遊ぶのも、地球規模の大変動が起きちゃう。
おじいちゃんとおばあちゃんがクトルーちゃんと遊んでいたとき、おじいちゃんが無茶しすぎてクトルーちゃんをバラバラにしたり。
外に散歩に行くときは、家の天井を吹き飛ばしてクトルーちゃんと空に舞い上がったり。
空を移動する際は、台風クラスの暴風を巻き起こしたり。その所業はまさに「邪神」そのものですね(笑)。
 |
| おじいちゃんとおばあちゃんは超巨大 |
★まがまがしさと不条理さが生み出すブラックユーモア
おじいちゃんとおばあちゃんが巻き起こした暴風は、胃の頭町周辺に多大な被害を残しました。
全半壊した家屋36軒。吹き飛ばされた自動車17台。倒された木が数十本。けが人50人以上。
クトルーちゃんは「キャハハ」と大笑いして散歩を満喫してたけど、被害は甚大。この不条理さがいいオチになっていて笑っちゃう。
おじいちゃんとおばあちゃんにくっついてきた「ムルムル」を、お母さんが集めてつくだ煮にして栞にお土産で持たせたり。
ストーリーはブラックユーモアに満ちています。
諸星さんの作品は、「妖怪ハンター」をはじめ「まがまがしさ」が充満しています。
そして奇怪な現象やその原因=邪神の正体を、主人公の稗田礼二郎が暴いていくというスリリングさが特徴です。
一方で「栞と紙魚子」は「クトゥルフ神話」をベースとした、正体不明の異形のモノが跋扈(ばっこ)している。
古本店の娘である紙魚子が、店にある奇書をめくって異形のモノや異常な現象を確かめるんだけど、正体がちゃんとは分からない。
胃の頭町の異常な状況も変わらない。ストーリーを楽しんでいる読者にとっては「非日常」です。
でも、栞と紙魚子をはじめ登場キャラは「非日常」を「日常」に感じている。
ワケの分からないムルムルが街中をチョロチョロしてたり、ヨグが包丁を持って襲ってきたり。
それなのに「んっ? それって、いつものことじゃん」って感じ。
不条理を「日常」として受け入れているキャラたちの姿が、何ともブラックでユーモラスな世界観を創ってるんです。
この世界観こそ「栞と紙魚子」が諸星作品の中でも異色な輝きを放っている特徴であり、面白さの秘密なんです。
3.生首事件
★異色作のファーストエピソード
1995年発表のエピソード。「栞と紙魚子」シリーズの第1話です。
諸星さんの特徴である「まがまがしさ」に、シュールさとブラックユーモアがあふれかえっています。
諸星さんの自選短編集「汝、神になれ鬼になれ」にも収録されているほど。
胃の頭町内でバラバラ死体が発見された。栞と紙魚子が通う高校でも騒ぎになったが、なぜか栞だけが浮かない顔。栞は紙魚子に「相談したいことがあるの」と自宅に招く。押し入れからクーラーボックスを取り出しフタを開けると、首。実は栞がバラバラ死体の第一発見者で、「すごいもの見つけちゃった」と興奮して持ち帰ってしまったという。「これをどうしたいの?」という紙魚子に、栞は「それを相談したいの」「元のところにおいといた方がいいかしら」。紙魚子は「こういう事の本がうちにあった気がするな。帰って調べてみるわ」。
本によると「水槽に水道水をはり生首を入れる。最初は乾燥餌から、慣れてきたらイトミミズなどを与えるとよいでしょう」。
★不条理な世界観が面白すぎる
最初は「生首を飼うなんてバカバカしい」と思っていた栞ですが、情が湧いてきたのか⁉︎
「飽きたら捨ててしまえばいいんだわ」と世話を始めると、水中に入れた乾燥餌はいつの間にかなくなっている。生首は腐る様子はなく、水の中でゆらゆら揺れているのをみると、生きているような気がしてくる。紙魚子が持ってきたイトミミズを入れると、生首は目玉を動かしながら食べている。生首は水槽の中を泳ぎ、栞はだんだん魚みたいな気がしていく。
諸星さんが描く生首は目玉がぎょろっとして不気味だけど、イトミミズを食べる姿がユーモラス。
栞はこれからどうすればいいか迷って、再び「生首の正しい飼い方」を開いたら「海や川に返してあげましょう」。紙魚子は「まあ、海は全ての生命の故郷だって言うじゃないの」。2人は「竜之介」を川に流すと、生首は2人に別れを告げるように振り返り流れていった。
結局は生首がなぜ魚のように振る舞うのか分からない。でも、何とも不可思議でシュールなラストがたまらないんです。
★栞と紙魚子のとぼけた会話が隠し味に
まがまがしい絵柄とシュールで不条理なストーリーの「栞と紙魚子」に、さらにひと味加えているのが2人の会話。
「非日常」を「日常」として受け入れている2人だけに、交わす言葉がメチャとぼけた感じでイイんですよ。
紙魚子「なによ、これ⁉︎」栞「頭よ、バラバラ事件の…今、警察が探してる…」栞「もう少し驚いたら?」紙魚子「あんたが驚くなって言ったんじゃないの」栞「こんなことめったにないし…紙魚子にも見せたかったし…」紙魚子「ありがと」
栞「二度と戻って来ないでね!」紙魚子「あっ、鯉につつかれてる」紙魚子「おっ、鯉にかみついた…ようし!達者で暮らせよ!!」栞「紙魚子、帰るわよ」
そして、最後に。この記事のテーマは「クトゥルフ神話の香りが漂う」エピソードを紹介することでした。
前述した通り、作品には「クトゥルフ神話」にまつわるエピソードがたくさん出てきます。
でも「クトゥルフ神話」がモデルのキャラが出てこないエピソードも、そのテーマは「得体が知れないモノは存在する」。
これは「太古から存在する地上の支配者」=「異形のモノ」という「クトゥルフ神話」のテーマと同じなんです。
作品には「生首事件」と同じくらいインパクトがあってシュールなエピソードがたくさんあるので、ぜひお楽しみください。
まとめ・「クトゥルフ神話」の香りにブラックユーモアが加わった名作
 |
| 「クトゥルフ神話」にブラックユーモアが加わった名作 |
ここまで「クトゥルフ神話」の影響を受けた名作である「栞と紙魚子」を紹介してきました。
そして「栞と紙魚子」で「クトゥルフ神話」の香りが漂い、諸星さんの奇怪な世界観にブラックユーモアが加わったオススメの、
- クトルーちゃん(1996年発表)
- おじいちゃんと遊ぼう(1997年発表)
- 生首事件(1995年発表)
上記の3つのエピソードを紹介&解説しました。
諸星さんは若いころ「クトゥルフ神話」を読み、影響を受けた1人。そして生み出された作品の1つが「栞と紙魚子」です。
紹介したエピソードは「クトゥルフ神話」と同じくらい奇怪で、「諸星ワールド」では異色な不条理さとブラックユーモアが最高です。
この記事を読んだことで、「栞と紙魚子」の世界観の特徴と魅力がよく分かったと思います。だから、
「諸星さんもクトゥルフ神話に影響を受けていると聞いたけど、それが分かる作品を教えて!」
「クトゥルフ神話と同じくらい奇怪な諸星さんのオススメ作品を読んでみたい!」
という方にはピッタリなエピソードなんです。ぜひ、作品のページを開いてみてください。
「クトゥルフ神話」と同じくらい奇怪で、ブラックユーモアに満ちた「諸星ワールド」をオナカいっぱい楽しむことができますよ!
当ブログでは、ほかにも諸星大二郎さんの名作&傑作を紹介しています。ぜひご覧ください。
エヴァ、トランスヒューマニズム…伝奇マンガの名作「生物都市」が秘める3つの先駆性
「いつもと違う」シュールで独創的な世界観を楽しみたい人にお勧め「幻想的な漫画」3選
この記事で紹介した作品を「すぐ読みたい」という方は、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。
「ebookjapan」「コミックシーモア」などのマンガストアなら無料で試し読みもできますよ。
※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して本や商品を紹介しています。
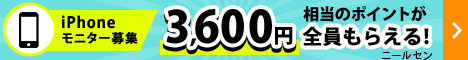











0 件のコメント:
コメントを投稿