 |
| オリオン座近くに存在する馬頭星雲の正体は⁉︎ |
古代史のミステリーがたっぷり詰まった諸星大二郎の傑作
オカルトやSF漫画ファンに「伝奇漫画の傑作を教えて!」と聞けば、必ず名前が上がるのが、「暗黒神話」。
伝奇漫画のレジェンドで第一人者、諸星大二郎さんの作品です。
諸星さんの代表作「妖怪ハンター」「マッドメン」などに並ぶ傑作。作品が発表された昭和の伝奇ファンに衝撃を与えました。
令和の今でも「名作」として高く評価されていますが、ただ発表から50年近くたっているだけに、
「すごく評判がいいけど、どんな内容なの?」なんて声がたくさん。
そして、作品を読んだことがある人からは、
「読んでみたけど内容が難しすぎる。誰か解説してほしい…」
そんな声も数多く上がっているんです。
実は「暗黒神話」は古代の神話・歴史のミステリー要素が詰まっているのが特徴。
だから、古代神話や歴史的な知識があるとメチャ楽しめるんです。
この記事では「暗黒神話」の詳細や壮大なストーリーをより楽しむために必要な知識として、
- 古代の日本・中国・インドの神話&歴史が交錯するストーリー
- 「暗黒神話」を楽しむために知っておきたい歴史・神話的な知識
- 続編の「孔子暗黒伝」で「暗黒神話」ワールドがさらに広がる
上記の3つの基礎知識を紹介&解説します。
この記事を読めば「暗黒神話」の詳細についてよく分かり、難しい内容も面白く理解できます。
さらに作品のページを開きたくなり、壮大なストーリーにハマりたくなりますよ。
「暗黒神話」ってどんな作品なの?
★古代史と神話が交錯する壮大なストーリー
「暗黒神話」は「週刊少年ジャンプ」1976年20号〜25号で連載。
諸星さんにとっては、1974年から週刊少年ジャンプで掲載した「妖怪ハンター」に次ぐ連載作品になります。
そして「畜生の章」「阿修羅の章」「餓鬼の章」「地獄の章」「人間の章」「天の章」の全6話で構成されています。
コミックスは全1巻。単行本をはじめ、豪華愛蔵版、文庫版と幅広く刊行されています。
ストーリーは日本の古代史や数々の神話、さらには仏教、古代インド哲学とヒンズー教やSF要素も盛り込まれ、壮大のひと言に尽きます。
1988年には「暗黒神話 ヤマトタケル伝説」のタイトルでゲーム化。
1990年にはアニメ(OVA)化もされて、大人気を博しています。
★主な登場人物とあらすじ
主人公は、山門武(やまと・たけし)。13歳の中学生で古代日本の豪族の血を引き、右肩にヘビのようなあざがある。
そして菊池一彦(きくち・かずひこ)。古代の九州南部にいたクマソの末えいで豪族・菊池一族の宗主。別名・菊池彦。
さらに謎の老人・竹内。白いあごひげの老人で、武が行く先々に出現。歴史学者と名乗る。
武は子供のころから縄文土器にひかれ、時おり足を運ぶ長野・諏訪の博物館で謎の老人・竹内と知り合う。ある日、亡父の知り合いという小泉に声をかけられ、父親は殺されたと告げられる。冬休みのある日、武は小泉とともに諏訪を訪問。亡父が研究していたという甲賀三郎伝説にまつわる洞窟の前で竹内と再開。3人が洞窟に入るとクサリにつながれた怪物がいた。
この不可思議な怪物との遭遇を皮切りに、武は日本各地の神話にかかわる遺跡を巡り、自分の正体に気づいていくんです。
1.古代の日本・中国・インドの神話&歴史が交錯するストーリー
 |
| 縄文土器はプリミティブさが魅力 |
★「畜生の章」
「暗黒神話」は古代の歴史&神話などの要素がたっぷり詰まっています。それだけに、ストーリーは入りくんでちょっと複雑。
この項では、ストーリーを分かりやすくするため「6つの章」それぞれのあらすじ=ポイントを説明していきます。
甲賀三郎伝説の洞穴から、武と小泉、竹内は脱出。その際、体中に8匹のヘビがからみつく不思議な土偶を持ち出す。土偶には古代絵文字(神代文字)があり「わが母の国 根の堅州国(かたすくに)へいけ」と記されている。3人は車で西へ。目的地である根の堅州国は島根・出雲だった。
古事記などで描かれている「国譲り神話」。天孫族が出雲の大国主(オオナムチ)に「出雲を譲れ」と迫る物語。
大国主の息子・建御名方(タケミナカタ)は抵抗したけど、腕をもぎ取られるなど敗走。諏訪まで逃げてきたそうです。
出雲へ向かう車中で竹内は、古代では神はありがたいものではなく、たたりや破壊・死をもたらすものと説明。神や怪物の正体は分からず、だから古代人は「神」とうやまい「魔」とおそれ「暗黒神の使い」と読んだ。車は制御がきかなくなり暗黒の空間を爆走。行手には洞穴にあった土偶のような姿をした怪物がいて「おまえを待っていた」。
★「阿修羅の章」
武はこの世とは違う空間で目が覚め、そばには暗黒の空間にいた怪物=オオナムチがいました。
不思議な声は自身のことを「唯一にして最高の真理」「すべての時間と空間を支配するブラフマン」と名乗る。そして武を「わが分身であるアートマン」として世界を動かす権利と力を受ける者だと説明する。ブラフマンは「契約のしるし」として怪物に武の右ひざをかませて「おまえはアートマンになる」と告げる。
武は熊本県・菊池郡近くの山中にある磐座(巨石)の上に倒れていて、武たちを追跡していた菊池に助けられる。菊池一族の家伝によると、縄文後期に大災害が発生。菊池一族と武の父方の一族は生き残った人々の一部だった。生き残った人々から後継者が出現し古代の遺産を引き継ぐ。天の斑駒が引き裂かれる時、暗黒神スサノオが出現する。
菊池は武を熊本各地の遺跡へ連れ回す。武は遺跡の壁面に記された円の模様の暗示に導かれ、大分へ。武は「ブラフマンのしもべで暗黒神のつかい」と名乗る馬頭の怪物に出会う。怪物は「おまえはブラフマンと結びつき、転輪聖王となる。やがて暗黒をつかさどる神スサノオにあう」と告げる。怪物は、そのためには体に8つの刻印を受けなければならないと語る。
武は大分・国東半島の山中にある磨崖仏で、馬頭観音の口に右足をかまれ逆さ吊りになった状態で発見されるんです。
★「餓鬼の章」
「餓鬼の章」の舞台は、前章に続き国東半島の磨崖仏周辺。
武は馬頭観音の近くにある比叡山延暦寺系のお寺「施餓鬼寺」で保護される。寺のご本尊は馬頭観音。畜生道や餓鬼道に堕ちた人間を救う仏。転輪聖王の愛馬ともいわれる。だから寺では名前のごとく年に2回、施餓鬼会(餓鬼道に堕ちた人を供養する)を行っている。
2人は空洞内で安置された棺を発見。棺の中はカラだったが「親魏」と彫られ半分になった金印を見つける。棺のフタには神代文字で「女王卑弥呼 金印をもって暗黒神につかえ…大御水にて不老不死を得…」と記されていた。1人残った美弥は空洞内をさらに調査し、泉を見つける。神代文字には泉につかると不老不死を得ると書かれていた。
菊池や竹内らが施餓鬼寺を訪れると、武の姿はなく、本堂には大穴が開きメチャクチャに崩壊していた。実は寺では餓鬼を本堂の穴の中に閉じ込め、天台の秘密呪法でしずめていた。
卑弥呼らが変貌した餓鬼たちを、寺では千数百年にわたって閉じ込めていた。
要するに、寺に閉じ込めていた餓鬼たちを「アートマン」「転輪聖王」となるべき武が解き放ったんです。
 |
| 日本神話の英雄、ヤマトタケル |
★「地獄の章」
「地獄の章」の舞台は大阪、飛鳥、奈良、京都。古代の朝廷にまつわる地になります。
大阪・羽曳野の前方後円墳「白鳥陵」の後円部が一夜にして掘り返されていた。さらに飛鳥・石舞台でも不可思議な生き物の足跡が無数に見つかった。武はアートマンの力で餓鬼たちを使って白鳥陵を掘り返し、「親魏倭王」の金印の半分を見つけていた。
武を追跡する菊池の説明によると、クマソは邪馬台国と抗争していた狗奴(くな)国で、卑弥呼から金印の半分を奪っていた。
ヤマトタケルはクマソを倒した際に金印を手にし、そのまま白鳥陵に葬られた。
菊池は武がトラックをチャーターして妙見山に向かっていることを知り、後を追う。山中で武に追いつき、一族の人間たちで包囲。武から金印の半分を奪い、自分が持つ片割れと合わせた。金印は1つになり地中から巨大な馬の神像が出現。トラックに積んだ箱から餓鬼たちが飛び出し、菊池らに襲いかかった。
武はまさに金印を使って「馬の神像」=「暗黒神」を呼び覚ましたんです。
菊池一族から逃れた武は、山中で倒れているところを竹内に発見されました。
竹内が武の体をさぐるとヘビ型のあざが6つ。諏訪、出雲、大分(邪馬台国)、飛鳥、奈良、京都で聖痕を得ていた。
竹内によると、古代人は8つのヘビの聖痕を持つ者を「八岐大蛇(やまたのおろち)」と呼び恐れた。
8つの聖痕を持つ人間が出現した時、暗黒神スサノオが天空から舞い降り、地上に破壊と死をもたらす、と。
そして6つの聖痕を身につけた武が「八岐大蛇」となるまで、聖痕は残り2つになり…。
★「人間の章」
謎の老人・竹内と再会した武は天乃叢雲剣(あまのむらくものつるぎ)を渡され、老人の案内で静岡・焼津へ向かいます。
天乃叢雲剣は、出雲でスサノオが八岐大蛇を退治した際に手にした神剣。アマテラスに献上され、ニニギノミコトとともに地上に降臨。
伊勢神宮に収められていたけど、朝廷への反逆者の征伐に向かうヤマトタケルに託されました。
ヤマトタケルは焼津へ赴いた際に敵の火攻めにあい、天叢雲剣で燃える草をなぎ払い窮地を脱出。
竹内は武を駿河湾の海辺につれていき、岩礁に隠れた祠(ほこら)に導く。祠のご神体は大きな丸い石。竹内が石をつえで叩くとパカリと開き、中には液体と人骨が入っていた。竹内によると、古代の日本では大異変が数度あって、人々は生き残るためにタイムカプセルに入って人工冬眠していた。竹内自身もカプセルで生き延びた1人で、自分は武内宿禰(たけのうちのすくね)と名乗った。
祠には特に大きなカプセルがあり、竹内はヤマトタケルの妻・弟橘媛(おとたちばなひめ)が入っていると告げる。武がカプセルを割ると、中から美女が出てきて武に「ヤマトタケルさま」と呼びかけ、古代鏡を渡す。だが弟橘は体が崩れ溶けていく。直後に雷が祠を襲い武が持つ神剣に落ちる。その衝撃で左肩に聖痕が記される。
東京の自宅では菊池一族の緒形が待ち構え、菊池が武の父を殺したと明かす。武の父は縄文期の生き残りの一族の末えいで、諏訪でタケミナカタを発見した。そばで隠れていた菊池は武の父を殺せば、アートマンの資格が自分に回ると考えてを下す。だがタケミナカタはそばにいた、当時3歳の武に聖痕を与えた。
武は8つの聖痕と三種の神器を手にし、アートマンになる資格を得るんです。
★「天の章」
「天の章」では、「暗黒神話」のストーリーの謎が明かされます。
ただ、その結末はやはり作品を読んでいただきたいと思います。この項では〝さわり〟だけ紹介します。
ブラフマンを名乗る不思議な声は武に「おまえはヤマトタケルでありアートマンである」と告げる。さらに「おまえとヤマトタケルは別々の時空間に、同時に存在する同じひとりの人間である」と明かす。不思議な声は「今こそすべての秘密をあかしスサノオにあわせよう」と武を宇宙空間に飛ばす。やがて武の目前に迫ってきたのは、馬頭の暗黒星雲だった…。
竹内によると、日本神話に登場する3貴神は天体を示している。アマテラスは太陽、ツクヨミは月。そしてスサノオも天体だと主張。
さらに3貴神を生んだイザナギは、先立って底筒之男ら3神を生んでいるが、これはオリオン座の3つ星(ベルト)を表していると説明。
ブラフマンは、馬頭星雲は生きていて2000年以上前=縄文時代には地球の近くにいたと告げる。馬頭星雲が太陽や月をおおったため、地球は天変地異に襲われ多くの人や生物が死んだ。
スサノオが高天原を暴れて荒らし、機屋(はたや)に天の斑駒を投げ込んだため、アマテラスが岩戸に隠れた。そのため地上は暗黒におおわれたという故事は、暗黒星雲による天変地異を神話で表現したもの。
さらに釈迦、ヤマトタケル、未来に出現するという弥勒菩薩がアートマンであるとも説明。
ヤマトタケルは1600年前に地球を救うために暗黒星雲を遠ざけたとも明かします。
ブラフマンは「武よ、おまえはどうするのだ⁉︎」と決断を迫るんです。そして武の決断は…、作品をご覧ください。
2.「暗黒神話」を楽しむために知っておきたい歴史・神話的な知識
 |
| ヤマトタケルが眠る白鳥陵 |
★ヤマトタケル
「暗黒神話」は日本の古代史と神話、さらに仏教と古代インド哲学とヒンズー教の要素がブレンドされた壮大な作品です。
前項では6つの章の各ポイントを説明しましたが、いたるところに耳慣れない名前や歴史的事例などがあったと思います。
ただ、この名前や事例について知っておけば「暗黒神話」をより楽しむことができるんです。
まずは主人公・武の〝もう1つの姿〟であるヤマトタケルについて説明します。
ヤマトタケルは第12代景行天皇の皇子。元の名を小碓尊(おうすのみこと)といいます。
古事記では、荒々しい性格が父の景行天皇にうとまれていたと描かれています。
でも武勇を買われ、天皇から朝廷に従わない九州南部のクマソ(熊襲)や東国を征伐せよと命じられて見事に成果をあげたんです。
西征では大和を起点として九州〜出雲と巡り、東征では大和〜焼津〜武蔵〜信濃(諏訪)〜尾張と巡ります。
そして三重で病没すると白鳥と化して飛び、河内(大阪・羽曳野)に降り立ったとされ、その地に白鳥陵が築かれました。
「暗黒神話」では、武が8つの聖痕を得る旅がストーリーとなっていますが、ルートはまさにヤマトタケルの西征&東征と同じ。
しかも体に受けた聖痕を結ぶとオリオン座、馬頭星雲=スサノオがいる星座と同じ形になるーという設定になるんです。
★ブラフマンとアートマン
ブラフマンとアートマンは、いずれも古代インド哲学やヒンズー教の概念です。
まずはブラフマン。古代インドでは、われわれが存在する宇宙の根源。宇宙を司り動かす真理と考えられていました。
神さまとしての姿や形はなく、というか、そんなものは超越して宇宙そのもの。絶対者。
ヒンズー教では宇宙の創造神ブラフマーと同じ。神々はすべてブラフマンから発生したと考えられています。
そしてブラフマンと同一のものとされているのが、アートマンです。
アートマンは人の奥底にあるもの、人の自我=意識です。スピリチュアルでいう魂ともいえるんじゃないでしょうか。
自我=意識=魂=アートマンがブラフマンと同一とされるのは、ブラフマンが宇宙=世界そのものであるから。
世界を構成するすべてがブラフマンなら、アートマンはその一部ですから。
さらにブラフマンとアートマンが一体になった状態を「梵我一如」といい、この境地に達した者を仏陀としています。
「暗黒神話」ではブラフマンの分身がアートマンで、ブラフマンの宇宙を動かす力を与えられた者と設定しています。
ブラフマンは存在するだけで、意思を決定するのはアートマン。「宇宙を動かす力」の1つが暗黒神スサノオというわけです。
また「阿修羅の章」で、武は馬頭の怪物から「ブラフマンと結びつき転輪聖王となる」と告げられています。
転輪聖王は古代インドで、法で世界を統治する理想の帝王とされています。
お釈迦さまは生まれた際に、仙人から「家にあれば転輪王に、家を出れば世を救う仏陀になる」といわれたそうです。
「暗黒神話」ではアートマンの系譜として釈迦、ヤマトタケル、さらに弥勒菩薩と設定しています。
弥勒は、釈迦の入滅から56億7000万年後の世界に出現し人々を救う菩薩さま。
ストーリーを楽しむ上で「弥勒」の名前は覚えておいてください。
 |
| 武内宿禰の肖像画 |
★武内宿禰
「暗黒神話」のストーリーで、武とともに重要なキャラが謎の老人・竹内。
そして老人は自ら、武内宿禰(たけのうちすくね)だと告白しています。
武内宿禰は古代の朝廷の重臣。景行天皇・成務天皇・仲哀天皇・応神天皇・仁徳天皇と5代にわたって仕えたとされています。
また朝廷に仕えた巨勢氏、蘇我氏、平群氏、紀氏など27氏の祖ともいわれているんです。
古事記などの年譜から計算すると、実に330年生きたことになる。だから実在したかどうか怪しい、伝説の人とされています。
「暗黒神話」では、竹内は歴史の証人であり神の言葉を伝える者として、卑弥呼を始め権力者たちに仕えていたと告白しています。
もちろん生身の人間では300年も生きたり、現代まで生きることはできない。だから冬眠カプセルに入って生き延びた、と。
一般的な常識では、人間が300年以上も生きることはできません。
最近では「武内宿禰」は古代朝廷の役職名で、初代・武内の子孫たちが役職名を継いだのではないかという人もいます。
「正統竹内神道」祭主で「正統竹内文書」の継承者としていた故・竹内睦泰氏は「第73世武内宿禰」と称していました。
最後に「暗黒神話」で活躍した竹内老人は、次項で紹介する続編「孔子暗黒伝」にも登場。
なぜ歴史の証人、神の言葉を伝える者になったのか? その理由が明かされています。
3.続編の「孔子暗黒伝」で「暗黒神話」ワールドがさらに広がる
★「暗黒神話」の前日譚
「孔子暗黒伝」は「週刊少年ジャンプ」1977年50号から1978年9号まで連載された作品。
全7話でコミックス全2巻、文庫版では全1巻に収められています。
「暗黒神話」の連載終了から約1年後に発表された続編。
これだけ重厚な作品を続けて連載していた昭和のジャンプはホント、スゴい雑誌だったんですね。
「孔子暗黒伝」は「暗黒神話」の続編であると同時に、前日譚でもあるんです。
舞台は紀元前5世紀の春秋戦国時代の中国とインド、さらに縄文時代の日本。アジアをまたにかけたストーリーが展開します。
春秋戦国時代の思想家で哲学者、孔子が古代帝国・周の遺跡で1人の男の子を発見、保護する。子どもは「赤」と名付けられ孔子に育てられる。だが暮らしていた村が襲われ、赤は謎の老人・老聃(ろうたん)に救われる。赤は老聃とともにシルクロードを西へ旅に出たが、老人は病に倒れ「ある男と会え」と遺言される。赤はインドで奴隷階層の少年アスラと出会う。2人は釈迦に導かれて一体化し「ハリ・ハラ」として日本にまで旅する。
★「ハリ・ハラ」が「アートマン」になるための旅
まずはタイトルにもなっている「孔子」。言わずと知れた儒教の祖。古代の周王朝の政治を理想とする思想家・哲学者です。
この偉人が周王朝の遺跡で子どもと出会うことからストーリーがスタート。
孔子が保護した際に、空に赤気(オーロラ)が広がっていたことで「赤」と名付けられました。
赤は裏表=人間としての影がなく、自然に動物たちが慕ってくる不思議な少年に育ちます。
西への旅に誘った老聃は老荘思想、道家の祖とされる老子ですね。孔子と同様に、世界中に思想を広めた伝説の偉人です。
少年アスラは、古代インドでは神だったけど征服民族によって魔神・魔族とされた民族の名前。少年は魔族の末えいという設定です。
赤とアスラはインドで出会い、入滅前の釈迦と会うんです。
「暗黒神話」で描かれたように、釈迦はアートマンの1人。2人のことはブラフマンからのお告げで知っていたと明かすんです。
釈迦は世界=宇宙の真理を2人に語るんですが、歴史上には並外れた人間が現れて歴史を大きく変えてきた、と。
「並外れた人間」がアートマンで、赤とアスラもそうだと明かすんです。
さらに、このままではアートマンとして不完全だとして2人を一体化=1体の人間「ハリ・ハラ」に変化させるんです。
ハリ・ハラは、古代インドの破壊神シヴァと最高神ヴィシュヌが合体した神。
釈迦は2人がハリ・ハラ=アートマンとしては不完全だとして、さらなる旅に出すんです。
やがて完全体(神)になり、ブラフマンと結びつけと命じました。
赤とアスラを結びつけた孔子と老聃は、釈迦とともに並外れた力で世界に影響を与えた偉人たち。
そういう意味ではアートマンだったといえるかもしれません。
 |
| 邪馬台国の女王・卑弥呼 |
★武内宿禰の正体
ハリ・ハラとなった2人は長い旅の末、船に乗って日本にたどり着きます。
当時の日本は縄文期で、人々の共同体が村からクニに発展していたころ。
諸星さんは、共同体のリーダーたちに日本神話で登場する神々の名前を与えて、縄文期の日本の世界観を表現しています。
くわしくは作品を読んでいただきたいのですが、おおざっぱにいうと、古代インドの神々と日本神話の神々を整合させた感じ。
そんな日本にハリ・ハラが出現し、縄文期の社会に混乱と異変をもたらすんです。
そんな異変に巻き込まれた縄文期の人たちの中にいたのが、謎の老人・竹内。「スクナビコ」という名前の少年として登場します。
スクナビコは、出雲の大国主(オオナムチ)の国作りに協力した「小彦名(スクナビコナ)」をイメージさせる名前。
スクナビコはハリ・ハラが巻き起こした異変に巻き込まれて、3世紀の日本にタイムスリップするんです。
そして当時の邪馬台国の女王・卑弥呼に仕えて…。
エンディングは「暗黒神話」の最初のシーンにつながるという見事すぎる構成になっています。
まとめ・不思議な諸星ワールドにハマろう
 |
| 荒ぶる神スサノオは日本神話の英雄でもある |
ここまで「暗黒神話」について紹介してきました。
「暗黒神話」は令和の今でも名作として高く評価されています。
古代の神話・歴史のミステリー要素が詰まっているのが特徴で、古代神話や歴史的な知識があるとメチャ楽しめる。
そのため、この記事では「暗黒神話」の詳細や壮大なストーリーをより楽しむために必要な知識として、
- 古代の日本・中国・インドの神話&歴史が交錯するストーリー
- 「暗黒神話」を楽しむために知っておきたい歴史・神話的な知識
- 続編の「孔子暗黒伝」で「暗黒神話」ワールドがさらに広がる
上記の3つの基礎知識を紹介&解説してきました。だから、
「すごく評判がいいけど、どんな内容なの?」
「読んでみたけど内容が難しすぎる。誰か解説してほしい…」
なんて方は、この記事を読んで「暗黒神話」の詳細についてよく分かり、難しい内容も面白く理解できたと思います。
ぜひ作品のページを開いて、壮大なストーリーに飛び込んでください。不思議な諸星ワールドに、絶対にハマりますよ!
当ブログでは、ほかにも面白い漫画を紹介しています。ぜひご覧ください。
「百億の昼と千億の夜・ネタバレ」宗教、科学、宇宙論…面白いけど難しい名作SFが分かる4つの基礎知識
「栞と紙魚子」クトゥルフ神話に影響を受けた名作漫画が読みたい人へオススメの3エピソード
エヴァ、トランスヒューマニズム…伝奇マンガの名作「生物都市」が秘める3つの先駆性
この記事で紹介した作品をすぐ読みたいという方には、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がお勧め。
「BOOK☆WALKER」などのマンガストアなら無料で試し読みもできますよ。
読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」
※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して本や商品を紹介しています。
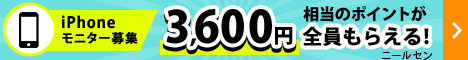







0 件のコメント:
コメントを投稿