 |
| 加曽利貝塚で復元された竪穴式住居 |
特別史跡に指定された縄文遺跡を楽しもう
海あり、山ありのプチ田舎ですが、とても住みやすくていいところです。
ただ、いい年のオッサンになって、まだ行ったことがないスポットが多いことに気づきました(苦笑)。
その1つが、「加曽利貝塚」。千葉市内にあって、国から特別史跡に指定されているくらい有名。
しかもワタシは「歴オタ」を名乗っているのに、行ったことがなかった。
正直いって「貝の化石がたくさん集まった遺跡でしょ?」って、ナメてました。
でも最近訪れてみて、マジでスゴいところだなと驚いた! 面白かった!
そしてネットなどをのぞいてみても、
「加曽利貝塚では、どんな遺物が発掘されているの?」
「加曽利貝塚で犬とか人の骨が発掘されたと聞いたけど、ホントなの?」
「加曽利貝塚では遺物の採取ってできるの?」
なんて興味津々な声がたくさんあるんです。
この記事では、歴オタのワタシが加曽利貝塚にお邪魔してメッチャ魅了された、
- 貝塚だけじゃない! 神秘的な土器や土偶がたくさん
- 犬は人間の家族の一員であることがしみじみ分かる
- 発掘体験プログラムなど縄文イベントがたくさん
上記の3つの魅力について紹介&解説します。
この記事を読めば、見つかっている遺物や発掘体験イベントなど加曽利貝塚の魅力がよく分かる。
そして、実際に加曽利貝塚に行ってみたくなりますよ。
※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
加曽利貝塚について
★世界最大級の貝塚
加曽利貝塚は千葉市若葉区桜木8丁目にある、縄文時代の遺跡。
当時の人たちが、食べた貝のカラなどを捨てたモノが地中に蓄積された貝塚です。
当時の人たちの「ゴミ捨て場」という感じ。だから貝塚は居住空間の一部。集落跡の一部でもあるんです。
縄文時代の期間は約1万2000年前から約2300年前。約1万年続きました。
加曽利貝塚には2つの貝塚があって、1つ(北貝塚)は約5000年前(縄文中期)にできた環状(サークル)型。
もう1つ(南貝塚)は約4000〜約3000年前(縄文後期)にできた馬蹄(U字)型。
いずれも約1000年かけて、北貝塚は直径約130メートル、南貝塚は長径約170メートルの貝塚が出来上がりました。
現在、2つの貝塚は連結する形になっていて「8の字」型になっています。
加曽利貝塚が世間に知られるようになったのは明治時代。1887(明治20)年に上田英吉さんにより学界に初めて紹介されました。
1963(昭和38)年ごろ、企業による土地買収で存続が危ぶまれましたが、保存を望む市民運動を受け千葉市が保存整備に着手。
1966(昭和41)年に千葉市が北貝塚周辺を買収し「千葉市立加曽利貝塚博物館」を開館。
さらに南貝塚周辺の土地も買収し、貝塚の全域(約15.1ヘクタール=東京ドーム3個分!)を整備。
「加曽利貝塚縄文遺跡公園」として市民に親しまれ、さらに現在は国宝と同格の文化財とされる特別史跡にも指定されています。
★縄文の暮らしが分かる
加曽利貝塚については、同貝塚博物館の元副館長・村田六郎太さんの著書「加曽利貝塚 日本最大級の縄文貝塚」(上の写真)が面白い!
加曽利貝塚のくわしい解説のほか、保存を目指す市民運動の経緯なども記されていて、とても参考になります。
さて貝塚ですが、日本には約2500もあって、うち4分の1は東京湾沿い(特に千葉市)にあるんだそうです(すごっ!)。
また約15ヘクタールの加曽利貝塚は、世界でも最大級なんだそう。
加曽利貝塚がスゴいのは、年代の違う2つの貝塚が存在する環状集落であること。
だから集落(住居)跡が発見されていて、縄文中期〜後期の暮らしぶりが分かる遺物もたくさん発掘されているんです。
これがメチャ面白くて魅力的! しかも無料で楽しめるんです(2025年1月時点)。
次項からは加曽利貝塚の魅力について1つずつ紹介&解説していきます。
1.貝塚だけじゃない! 神秘的な土器や土偶がたくさん
 |
| 加曽利貝塚では竪穴式住居が2つ復元されています |
★約7000年前の竪穴式住居
そもそも貝塚は、縄文時代の人たちの生活の場としてあったもの。
中央の広場を囲んで、住居がサークル状に並ぶ「環状集落」があって、その周囲に食べ物などのゴミ捨て場があった感じ。
貝などの魚介類や木の実、獣の骨などが約1000年の間に積もって出来上がったのが貝塚なんです。
当然ながら貝塚の近くには住居跡もある。加曽利貝塚でも住居跡が発見されています。
それが何と約7000年前! 縄文時代の区分では初期〜中期といったところ。そして縄文時代の住居といえば「竪穴式住居」です。
地面を掘り下げて床をつくり、その床に掘立柱を立てて梁(はり)などを組み、土や植物で屋根をふいた住居。
現在では、その用途が住居に限らず倉庫や工房、馬小屋などにも使われていた可能性が浮上。そのため「竪穴建物」とも呼ばれています。
加曽利貝塚では、発掘された住居跡を参考にして2棟の竪穴式住居が復元されています。
いずれも無料開放されていて、住居内への出入りが自由。ワタシも2棟とも中に入りましたが、ホント不思議な感じ。
床の中心に地床炉が再現されていて、天井には明かり取りも兼ねて煙が抜ける穴もあってめっちゃリアル。
モンゴルの遊牧民が使っているゲル(移動式住居)のような感じがして、実に機能的。
縄文の雰囲気を体感できて楽しめる施設になっています。
 |
| 縄目とヘビの文様が神秘的な縄文土器 |
加曽利貝塚では貝などの魚介類や動物の骨、木の実などのほかにも、さまざまなモノが見つかっています。
何といっても縄文土器。実はこちらで発掘された土器が、縄文土器の研究でヒナ型になったんだそうです(スゴっ!)。
15ヘクタールと広大な面積を誇る加曽利貝塚では、さまざまな場所をアルファベットで名前をつけて発掘してきました。
そのうちの「B地点」と「E地点」で画期的な発見があったそうです。
「B地点」では縄文後期中ごろ(約3500年前)の「加曽利B式土器」。
「E地点」では縄文中期後半ごろ(約5000年前)の「加曽利E式土器」。
さらに、いずれの地点でも土の階層によって年代ごとに形式が違う土器が出土。
これにより「この形式の土器が出たなら何千年前の遺跡だ」と区別できるようになったんだそうです。
加曽利貝塚が日本、そして世界の考古学・歴史学にもたらした功績はメチャ大きいですね!
加曽利貝塚博物館では、これまで発掘された土器がたくさん展示されています。
ワタシは縄文土器は写真で見たくらいの知識しかありませんでしたが、実際に断片から復元された土器を見て大コーフン(笑)。
縄文土器の最大の特徴である、縄状の文様のプリミティブ(原始的)な魅力に心がわきたちました。
また縄文中期(E式)の土器の装飾が華麗なこと。そして縄文後期(B式)になると装飾がシンプルで機能的に変化していること。
時の流れとともに、人間の文明がどう変化していくのか。それが実感できて、めっちゃコーフンしてしまいました。
博物館では撮影がOKなので、しっかりスマホで撮影させてもらっています。
 |
| 土偶もプリミティブで神秘的なフンイキ! |
★いつまでも眺めちゃう土偶
加曽利貝塚ではたくさんの土偶も発見され、貝塚内の博物館で展示されています。
土偶は縄文初期から作られていた、土の人形。人や動物、道具など、さまざまなモノがかたどられています。
土偶を作った目的は豊穣や出産のための祭祀や呪術などの道具というのが有力な見方。でも、本当のところは分かっていません。
人型では女性をかたどったと見られるモノが多いそう。女性が子どもを産む神秘的な生命力への信仰があったといわれています。
土偶といえば、青森県つがる市の「亀ヶ岡遺跡」で発掘された「亀ヶ岡式」の遮光器土偶。
顔にゴーグルをつけて、胸と腰がドーンと大きいヤツ。よく「宇宙人をかたどっている」といわれているヤツですね。
加曽利貝塚博物館で展示されているのは、縄文後期の「山形土偶」が多いんです。顔が山のような形をしているヤツですね。
関東地方でさかんに作られていたそうですが、これが素朴でいいんですよ。
遮光器土偶のような精密さや不可思議さはないけど、上の写真の女性とみられる土偶にある2つの胸やおなかのふくらみ。
縄文時代の人たちが、女性という存在の特徴をどうとらえて崇めていたのか。
当時の人たちの精神性というか、考え方が素朴な作りから感じられて、いつまでも眺めてしまうんですよね。
ちなみに土偶の顔って、初期のころはのっぺらぼう。時代がたつにつれて目や鼻、口がつけられていったんだって。
その理由は分かっていないそうだけど、人類が精神的・理知的に成熟していく様子が感じられてため息が出てしまう。
博物館に展示されている土偶たちの顔を見るだけでも楽しめますよ。
2.犬は人間の家族の一員であることがしみじみ分かる
 |
| 出土した人骨の複製 |
★人骨も出土した神聖な場所
加曽利貝塚ではここまで紹介してきたように、貝塚以外にも土器や土偶が出土。
さらに耳飾りなどの装飾品、釣り針などの漁労具といった多種多様なモノが見つかっています。
その中には人骨、縄文人の遺骨も発掘されているんです。
明治時代から始まった発掘で、これまで見つかっている人骨は約230体! 男女の大人や子どもの遺骨も発見されています。
地中の貝層(貝の化石がある層)を掘っていたら、人骨が出てきたそうです。
そして人骨が出てくることで、貝塚自体の意味合いや解釈が変わる可能性があるそうです。
ここまで貝塚を「縄文時代のゴミ捨て場」なんて書いてきましたが、そうとも言い切れない可能性があるんです。
上の写真は貝塚博物館内に展示されている人骨(完全体)の複製です。
人骨は20代の女性で、足を屈曲させ体を丸めるように埋葬されている姿を再現しています。
この姿って、とても「ゴミ捨て場」に放置されたとは思えません。
じっと見つめていると、故人を悼むように丁寧に安置されたように感じるんです。
だから貝塚は「ゴミ捨て場」ではなく、貝や動物、そして人の霊を慰め、感謝しつつ葬る場所。
神聖で信仰の対象となる場所だったんじゃないか? という解釈もあるんです。
ワタシも実際に加曽利貝塚の展示物を目の当たりにして、厳粛な気持ちを覚えました。
 |
| 加曽利貝塚博物館にはワンちゃんも散歩にくるよ |
★昔も今も犬は家族の一員
貝塚は単なる「ゴミ捨て場」ではなく、縄文人にとって神聖な場所だったー。
このことを感じさせる展示物が、加曽利貝塚博物館にはあるんです。
それは犬の完全体の遺骨です。
加曽利貝塚では狩猟で食糧にした動物の骨なども出土していますが、ほとんどがバラバラ。
一方、犬の骨はやはり貝層で5体ほど見つかっているそうですが、展示されている犬は完全な姿で体を丸めて安らかに眠りについている感じです。
さらに、骨折が治った跡がある骨も見つかっているんだとか。
縄文時代の人たちが、犬を大切にしてかわいがっていたことが分かる証拠ですね。
犬は古代(約4万年前〜約2万年前)に東アジアにいた「ハイイロオオカミ」が家畜化されたと考えられています。
狩りのパートナーや集落の守りを務めるなど、古代から人間にとって大切な家族の一員でありトモダチだったとされています。
だからこそ人骨が安置された貝層に、体を丸めて眠るように埋葬されたんだと思います。
以前ワタシのウチにも犬がいて、すでに虹の橋を渡ってしまいましたが、ホントにかわいくて大切な家族、子どもでした。
博物館に展示されている、体を丸めて眠る姿をみて、愛犬のお葬式のことを思い出しました。
やはり体を丸めて永遠の眠りについている愛犬の姿が、加曽利の犬とだぶったんです。
犬は最愛の家族であり、トモダチである。加曽利貝塚は、そんなことを改めて教えてくれる場所でもあるんです。
 |
| 加曽利貝塚の敷地からは市街が見下ろせる |
★なぜ貝塚は内陸部にあるのか
全国にある貝塚って、海辺ではなくちょっと陸地に入った場所にありますよね。
加曽利貝塚も、最も近い千葉港から直線距離で5キロくらい離れています。
「じゃあ、貝や魚をとりに海まで5キロ歩いていってたの?」と疑問がわいてきます。
実は縄文時代の早期から前期に「縄文海進」という現象があったそうなんです。
当時は地球が温暖化して北極や南極の氷がとけたため、海水は約120メートル上昇。陸地奥に海水が侵入していたとか。
関東平野でのピークは約6500年前〜5500年前で、まさに縄文中期。東京湾は今より海面が3メートル高かったそう。
また加曽利貝塚はちょっと小高い丘にあります。だからこそ縄文時代は海水に侵入されず、海辺に近い状況で集落ができたのかもしれません。
なぜワタシが「縄文海進」や貝塚に興味をもったかというと、当ブログで公開中の、
『邪馬台国論争』畿内、九州…「今はどの説が有力⁉︎」という方にお勧め!分かりやすくて面白い研究本4選
という記事を書いたことがきっかけなんです。
研究本を読んでいて、陸地に侵入した海水が引いて水田耕作ができたのが、九州は弥生時代(2〜3世紀)で、近畿では4〜5世紀。
したがって約3.5万人の人口だったといわれる邪馬台国の食を支えることができた土地は九州だろう、という説が面白かったんです。
だから加曽利貝塚で、千葉市街を見下ろせる広場に立ってみた。
そうしたら縄文から弥生期の集落(ムラ)やクニがどうやってできていったのか、おぼろげながらイメージできたんです。
3.発掘体験プログラムなど縄文イベントがたくさん
 |
| 北貝塚の観覧施設。貝層が見られる |
★表面採取がダメなワケ
加曽利貝塚では、敷地内の地表に出ている土器や石器、化石などを採集する「表面採取」が禁じられています。
要するに、加曽利貝塚の敷地内で「ここに遺跡がありそう」と勝手に発掘作業をすることができないんです。
なぜダメなのかというと、まだ発掘中だから。
前述した通り、加曽利貝塚は約15ヘクタールという広さですが、発掘が進んだのは全体の7〜8%だけなんだとか。
要するに、貝塚にはまだまだトンデモないものが眠っている可能性がある。だから表面採取はダメ。盗掘になります。
表面採取はダメだけど、地中に埋まっている遺物のスゴさは体感できます。
貝塚博物館では、ここまで紹介した土器や土偶などの遺物がたくさん展示されています。
さらに貝塚の貝層(断面)を見ることができる「貝塚断面観覧施設」が、北貝塚と南貝塚にそれぞれ1カ所ずつあるんです。
いずれも発掘作業で出現した貝層をそのまま保存していて、自由に見ることができるんです。
施設内は両面がアクリル板張りになっていて、左右に貝層が展開している感じ。
約1000年かけて小さな貝が積もった貝層を見ていると、1000年にわたる生活の営みが実感できる。
不思議な気持ちと感動に襲われるんです。
 |
| 竪穴式住居内の地床炉 |
加曽利貝塚では表面採取はできませんが、縄文時代を体感できるイベントが実施されているんです。
基本的にイベントの開催日は毎月第2・第4日曜日と祝日。
場所は加曽利貝塚公園内の広場や、貝塚博物館と併設されている休憩施設「かそりえ」(めっちゃきれいです)など。
イベントも体験型のプログラムが盛りだくさん。
復元された竪穴式住居の中の炉で火を焚いたり、棒と板を使った火起こし体験とか。
さらには貝層の土を使った擬似発掘体験もできて、実際に貝の化石や土器の破片などを探すこともできるんです。
ほかにも石器や貝アクセサリー作り体験もあったり、土器や土偶のレプリカを作る体験もある。
さらには貝塚公園内をボランティアのガイドさん付きで探検できたり。
しかもイベントには無料で参加できるので、たくさんの人たちが参加しています。
体験プログラムの開催内容については、加曽利貝塚博物館のホームページで紹介されています。
体験プログラムの内容などの詳細を知りたい方は、ぜひホームページにアクセスしてみてください。
 |
| 公園入り口には案内マップがあるよ |
★竪穴式住居を眺めながらウォーキング
加曽利貝塚の魅力は、約15ヘクタールの広大な遺跡全体を楽しめること。実際に訪問して堪能できました。
加曽利貝塚は縄文遺跡公園として整備されていて、散歩やウォーキングにうってつけの場所。
小高い丘の上に芝が広がる敷地内で、散策コースを楽しむことができるんです。
ワタシはバイク(ホンダ・グロム)で訪問しました。
入口の駐輪場にバイクを止めて止めて公園を望むと、左に北貝塚、右に南貝塚という感じ。
2つの貝塚の間に通っている散策コースを歩いていくと、貝塚博物館へ。
博物館で展示物を楽しんだ後は、博物館から見て右手にある竪穴式住居へ散策コースを歩いて向かいます。
散策コースの周囲はさえぎるものはなく、とても広々。歩くにつれて大きく見えてくる竪穴式住居の威容は、まさに圧巻ですよ。
北・南の貝塚には、いずれも実際の貝層を見ることができる「貝塚断面観覧施設」もある。
さらに北貝塚には竪穴式住居跡を保存した観覧施設もある。
テクテクと歩いて施設を巡るだけで、めっちゃ運動になるんです(笑)。
散策コースの周辺は木々も多くて、春〜秋は緑も楽しめます。ただ注意点が1つ。マムシに注意してください(怖っ…)。
公園は自然が豊かな分、いろんな生物が住んでいます。散策コースには注意を喚起する看板も立っています。
「遺物を探してみようかな」と思って林の中に入ったら、いた…、 なんてことがあるかもしれませんよ。
まとめ・2027年度には新貝塚博物館が開館する
 |
| 縄文後期の鉢。曲線が素晴らしすぎる! |
ここまで千葉・加曽利貝塚について紹介してきました。
そして、歴オタのワタシが加曽利貝塚を訪問してメッチャ魅了されてしまった、
- 貝塚だけじゃない! 神秘的な土器や土偶がたくさん
- 犬は人間の家族の一員であることがしみじみ分かる
- 発掘体験プログラムなど縄文イベントがたくさん
上記の3つの魅力について解説してきました。
加曽利貝塚は国から特別史跡に指定されている、ワタシの地元・千葉の宝です。
そして最近訪れてみて「貝のゴミ捨て場」などじゃなく、縄文時代や当時の人たちの息吹を感じることができるスゴいところ。
そう感じ、この記事をまとめた次第です。だから、
「加曽利貝塚では、どんな遺物が発掘されているの?」
「加曽利貝塚で犬とか人の骨が発掘されたと聞いたけど、ホントなの?」
「加曽利貝塚では遺物の採取ってできるの?」
なんて興味のある方は、この記事を読んで、遺物や発掘体験イベントなど加曽利貝塚の魅力がよく分かったと思います。
現在、加曽利貝塚博物館は縄文遺跡公園内にあって無料で観覧することができます。
一方で博物館が特別史跡内にあるのはふさわしくないとして、違う場所に新博物館を2027年度までに開館する計画があります。
今の博物館は解体撤去される方針で、新博物館は有料化される可能性があるそうです。
解体作業が始まると、魅力あふれる展示物がしばらく見れなくなる可能性があります。
興味がある方は、早めに訪問することをオススメします。今なら無料ですよ!
当ブログでは、ほかにも歴史に関する面白い本などを紹介しています。ぜひご覧ください。
『邪馬台国論争』畿内、九州…「今はどの説が有力⁉︎」という方にお勧め!分かりやすくて面白い研究本4選
坂本龍馬は薩摩藩士?フリーメーソン?暗殺の黒幕は?幕末の英雄の新事実が面白い「龍馬本」3作品
中高生におススメ!苦手な日本史が好きになる歴史小説4選と活用法
この記事で紹介した村田六郎太さんの「加曽利貝塚 日本最大級の縄文貝塚」は、「Amazon」などで購入が可能です。
加曽利貝塚博物館の元副館長さんによる解説は分かりやすく、貝塚保存の市民運動の経緯なども記されていて参考になりますよ。
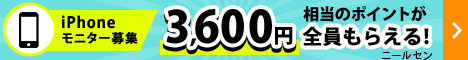






0 件のコメント:
コメントを投稿