 |
| 奈良・纏向遺跡は邪馬台国の有力な比定地とされているが… |
幻の女王国に関する各説の最新情報や研究成果が分かる
日本人なら誰もが興味があるといっていい「邪馬台国」。
約1800年前の日本に存在し、女王「卑弥呼」が治めていたとされる幻の国。日本史最大の謎にして、最高のロマンが漂っています。
その比定地を巡り、江戸時代から続く論争は令和の時代でも継続中。
歴オタじゃない人でも「邪馬台国って、どこにあったんだろう?」という興味はあると思います。
そして最近になって興味をもった人、ワタシのように急に邪馬台国熱がぶり返した方たちなどから、
「邪馬台国論争って、今はどの説が有力なの⁉︎」
「邪馬台国や論争について分かりやすくて面白い、お勧めの本を教えて!」
そんな声がたくさんあがっているんです。
この記事では、そんな方たちにお勧めの「邪馬台国論争」や比定地の有力説が分かる研究本を紹介、
- 「ここまでわかった!邪馬台国 『魏志』倭人伝全文を読む!」
- 「データサイエンスが解く邪馬台国 北部九州説はゆるがない」
- 「邪馬台国の謎を解く IT(情報技術)のV字アプローチを用いて」
- 「Q&Aでよくわかる!! 阿波倭邪馬台国論入門」
上記の4作品について紹介&解説します。
この記事を読めば、4作品が邪馬台国や論争について分かりやすくて面白いこと、比定地の有力な説の研究成果や最新情報もよく分かります。
そして4作品のページを開いて、幻の邪馬台国を追い求めたくなりますよ!
※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して本や商品を紹介しています。
邪馬台国と比定地の有力説について
 |
| 女王・卑弥呼はどこに眠ってるのか? |
★3世紀の日本に存在した女王国
誰もが知っているとは思いますが、改めて「邪馬台国」についてざっと説明します。
邪馬台国は3世紀ごろの日本(倭)に存在したとされる国。当時の中国の歴史書「三国志」の「魏志倭人伝」(正式には魏志東夷伝)に記されています。
魏志倭人伝によると、当時の倭は大小の国々による戦乱(倭国大乱)がたえない状態でした。
国々の話し合いで女王を共立したことで争いが終焉。その女王の名を「卑弥呼」と伝えています。
邪馬台国は約30の国の連合体。「鬼道」(呪術)を使う卑弥呼が祭祀を、補佐役として弟が政治面を担う形で治めていたそうです。
ただ南にあったとされる「狗奴国」と交戦状態で、卑弥呼は優位に立つため当時は3つの国が争っていた中国の「魏」の後ろ盾を得ようと画策。
魏に朝貢し、皇帝から「親魏倭王」の封号を獲得。魏の使節から卑弥呼に「親魏倭王」の印綬などがもたらされたとしています。
邪馬台国や卑弥呼に関して、実は日本の正史には記載がないんです。
ただ「日本書紀」が魏志を引用する形で卑弥呼と「神功皇后」が同一だとしています。
邪馬台国は古くから、中国から書物が輸入され「魏志倭人伝」を読んだ知識人などに知られていました。
そして「邪馬台国」の名は、江戸時代の学者・新井白石が「やまたいこく」としたことが広まったもの。
魏志倭人伝(写本)では「邪馬壹(壱)国」もしくは「邪馬臺(台)国」と伝わっています。
★比定地を巡る論争
邪馬台国があった場所については、日本の正史では記載がないため、特定するには昔も今も魏志倭人伝の記述に頼るしかない状態です。
倭人伝に記されている、倭国へ赴いた魏の使節が報告した道程や土地の様子などが参考にされてきました。
これに国内各地にある遺跡の規模などを比較して候補地が主張され、いまだ論争が続いています。
そして現時点で有力な比定地とされているのが、畿内大和説と北九州説の2つ。
ほかに出雲説、阿波徳島説、沖縄説、さらにはエジプト説などもあります。
ただ奈良県桜井市にある「纏向(まきむく)遺跡」(2世紀末〜4世紀前半)が、2009年の調査で都市レベルの大規模遺跡であることが判明。
遺跡域内にある箸墓(はしはか)古墳の築造時期が、卑弥呼の没年とされる西暦247〜248年に近いことから畿内大和説が有力とされています。
そして、この記事で紹介する4作品は、各説について説明が分かりやすくて面白いことからチョイスしています。
畿内大和説=「ここまでわかった!邪馬台国 『魏志』倭人伝全文を読む!」
北部九州説=「データサイエンスが解く邪馬台国 北部九州説はゆるがない」
北部九州説=「邪馬台国の謎を解く IT(情報技術)のV字アプローチを用いて」
阿波徳島説=「Q&Aでよくわかる!! 阿波倭邪馬台国論入門」
ざっとこんな感じ。次項からは作品ごとに紹介&解説していきます。
1.「ここまでわかった!邪馬台国 『魏志』倭人伝全文を読む!」
★畿内大和説を分かりやすく解説
この記事を書くにあたって、畿内大和説を分かりやすく一般向けに解説している手頃(リーズナブル)な本はないか?と探しました。
でも、ないんです(苦笑)。あるにはあっても論文的で難しい。そしてお高い(笑)。
聞くところによると、理由は畿内大和説の本って売れないからだそうです。
邪馬台国って、地形的に中国・朝鮮に近い九州にあるんじゃない? なんてイメージが強いですからね。
また大和政権発祥地=邪馬台国というイメージも、なにか当たり前すぎてつまらない…、なんて感じもします。
そんなワケで畿内大和説本を探すのに苦労したんですが、「分かりやすいじゃん!」と見つけたのが、この本。
「ここまでわかった!邪馬台国 『魏志』倭人伝全文を読む!」は2011年6月に刊行。
歴史ファンに人気の雑誌「歴史読本」編集部による解説本なので、めっちゃ分かりやすいんです。
比定地の各説や、邪馬台国の風俗や卑弥呼の人物像などについて、歴史学者や考古学者らが分かりやすく説明しているんです。
この作品が発売されたのは、ちょうど奈良県桜井市の纏向遺跡で大規模な建物群遺跡が発見された直後。
畿内大和説の勢いに加速がついた時期なんです。
畿内大和説を主張している学者さんや研究者は、主に京大や大阪大など関西の有力大学の人たち。地元の人たちですね。
そしてこの作品で畿内大和説を解説しているのは、歴史学者の西本昌弘さん。
西本さんは関西大学教授で専門は古代史。畿内大和説のポイントをしっかりと教えてくれています。
※上記の写真は刊行当時の書影ですが、現在はAmazonの「kindle unlimited」なら無料で読むことができます。
★大和の最古の遺跡と古墳
もともと「邪馬台国」は、古来から「大和国(やまとこく)」の音訳として知られていたそうです。
「邪馬台」=「大和」という感じで、畿内大和説の大きなアピールポイントでした。
特に奈良県桜井市にある纏向遺跡と箸墓古墳は、築造年代が邪馬台国と同じ3世紀ごろということで比定地の有力候補とされていました。
そして2009年に築造年代が3世紀前半で、方位と軸線がそろった大型建物群が発見。
都市レベルの遺跡だったことが分かり、「邪馬台国の痕跡じゃないか⁉︎」と畿内大和説派のボルテージが急上昇。
西本さんも「卑弥呼の居館もしくは祭祀場につながる遺跡が確認された意義は大きい」と強調しています。
そして西本さんは文献史学と考古学の観点から畿内大和説のポイントを説明しています。
まずは文献史学。畿内大和説の強みの1つは、魏志倭人伝に記された道程(距離・方向)にハマること。
倭人伝の道程通りに進むと、邪馬台国は九州のはるか南にあることになる。そして方位の面でも倭人伝には誤りがある。
当時の中国の人たちの〝日本の地形観〟などを参考に方位を修正すると、邪馬台国は畿内方面に存在した公算が大きいとしています。
次に考古学面。畿内大和の遺跡からは数多くの「三角縁神獣鏡」が発見され、鏡には魏の年号が刻まれたモノも多い。
魏志倭人伝では、卑弥呼が朝貢したお返しとして、魏から「親魏倭王」の印綬のほかに約100枚の鏡が贈られたとしています。
これが畿内大和説のもう1つのアピールポイントなんです。
一方で九州説派などからは、肝心の中国大陸からは「三角縁神獣鏡」が発掘されていないという指摘がありました。
西本さんによると、「三角縁」に近い図象文様などの特徴が一致する鏡が中国華北で発見されていると主張しています。
また箸墓古墳に埋葬されている人物は、日本書紀で三輪山に住む大物主神の妻になったと伝えられている女性。
倭迹迹日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと)。第7代孝霊天皇の皇女とされています。
国立歴史民俗博物館の研究グループが炭素14年代法での年代測定で、箸墓古墳の築造年代が240〜260年と発表。
この築造年代は、卑弥呼の没年(247〜248年)に近いとしています。
また纏向遺跡が、実在した最初の天皇である第10代崇神天皇の王宮であるとする議論がさかんになっている。
そして崇神政権と卑弥呼の王権が何らかの形でつながる可能性があると主張しています。
 |
| 箸墓古墳に卑弥呼は眠っているのか? |
★優位とされる畿内大和説の疑問点
西本さんは上記のポイントから畿内大和説が優位にあり、邪馬台国の比定地論争は終結に向かっていると結んでいます。
ただ畿内大和説の根拠を読んでいると、少なくない疑問点が浮かんできます。
まずは畿内大和地域で、大きな戦乱の痕跡が見つかっていないこと。
魏志倭人伝では、卑弥呼が女王に共立される以前に「倭国大乱」の時期が続いたとしています。
多くの国々が入り乱れて戦っていただけに、剣や鏃(ヤジリ)などの武器といった戦乱の痕跡が多少なりとも残っているはず。
でも畿内大和地域では、当時の戦乱の痕跡が発見されていないそうです。
そして畿内大和地域では纏向遺跡以前の、ムラやクニといった共同体レベルの遺跡がとても少ないということ。
要するに、3世紀の畿内大和地域に突如として都市レベルのクニが出現したイメージがあるんです。
さらに畿内大和説派の主張が、古事記や日本書紀に記されている「神武東征」神話を無視している印象があること。
神武東征は初代神武天皇が九州・日向から東へ進み、奈良盆地を制して天皇に即位する神話です。
この神話と畿内大和地域の状況を考えると、大和政権の祖たちが九州から奈良盆地に移動し、纏向に王権を打ち立てた感じがするんです。
そして、なぜ畿内大和説派の研究者が「神武東征」を無視するのか?
その理由は戦前の日本を支配していた「皇国史観」を嫌悪する、戦後からのアカデミズムが原因なのかと思います。
でも神話とされた「トロイ」の遺跡がシュリーマンに発見された事例もあるように、神話には事実を反映したモノがあると思うんです。
だから日本神話を無視する姿勢は、正直いって疑問に感じます。
2.「データサイエンスが解く邪馬台国 北部九州説はゆるがない」
★九州説の優位性をデータで示す
邪馬台国北九州説は、日本人にとっては最もポピュラーな説といえます。
魏志倭人伝で記されている邪馬台国までの道程で、壱岐・対馬・末盧(松浦?)・伊都(糸島?)と九州に身近な地名が登場。
さらに北九州には3世紀頃の遺跡や遺物、戦乱の痕跡がたくさんあり、中国大陸(魏)由来の遺物も発掘されているからです。
そして「データサイエンスが解く邪馬台国 北部九州説はゆるがない」は2021年10月に発売されました。
纏向遺跡での大型建物群跡の発掘から10年ほどが経過した時期に、安本美典さんによって発表されました。
安本さんは京大大学院出身の古代史研究家。心理学者でもあります。
古代史研究では、文献の特徴を数値化して統計学的手法で文献の分析や比較をする「数理文献学」の使い手です。
また邪馬台国北九州説の強力な論者の1人。北九州の女王国が東(奈良盆地)に移動したとする「東遷説」の論者でもあります。
この作品では纏向遺跡での〝大発見〟から10年が経過し、この遺跡から邪馬台国としての決定的な証拠(遺物)が出ていないこと。
長く邪馬台国研究にたずさわっている近畿の研究者たちから「邪馬台国は九州にあった」との見解を発表するケースが増えていること。
安本さんはそれらの事実を指摘しつつ、北九州と畿内の遺跡などの研究成果を数値化して比較。
改めて、邪馬台国北九州説の優位性を主張しているんです。
★発掘された遺物数の比較
安本さんは作品中で、北九州と畿内の遺跡などから発掘された魏由来の鏡や戦乱の痕跡とみられる鉄の鏃(やじり)の数に着目。
両地域などから発掘された遺物が数値化された邪馬台国研究者たちの研究成果を引用して、比較しています。
まずは鏡。魏志倭人伝には魏に朝貢した卑弥呼が「銅鏡100枚をもらった」と記されていることを前提としています。
北九州と畿内をはじめ、全国の遺跡から発見された魏由来とみられる鏡の数を各都府県ごとに示したグラフを掲載。
福岡、佐賀などの北九州での鏡の数は、畿内の約10〜20倍と圧倒していることを示してます。
そして武器である鉄の鏃。安本さんは魏志倭人伝で「倭人は鉄の鏃を用いる」と記されていることを指摘しています。
前述した通り、卑弥呼が女王に共立される以前は「倭国大乱」の状態。
邪馬台国があった場所の周辺は戦争状態だっただけに、大量の鏃が残っている可能性があります。
安本さんはやはり、発掘された鏃の数を示した各都府県ごとのグラフで比較。
鏡と同様に福岡県が奈良県を圧倒し、実に約100倍の差があると指摘しています。
この2つの数値を前提として、確率計算法(ベイズの公式)で両地域に邪馬台国があった確率を計算。
その結果、福岡県を「1000」とすると奈良県は「1」だと主張しています。
さらに鏡や鏃に絹、勾玉などの遺物を加えて確率を計算すると、福岡県にあった確率は99・8%。奈良県は0%としています。
前述した「三角縁神獣鏡」についても、中国本土で出土した例は1件もないことやコピー鏡の可能性が強いことなどを強調しています。
 |
| 佐賀・吉野ヶ里遺跡は弥生時代の大規模遺跡群だ |
★畿内大和説の学派の伝統と同調圧力
考古学の分野では、ある社会的な位置にある人が強く主張すると、多くの研究者がそちらになびく風潮がある。ある特定の空気ができあがってしまう。同調圧力、属人主義の傾向が強すぎる。
さらに同調圧力は畿内大和説派による発表を報じるマスコミにも働いているとも指摘。
学会の重鎮や専門家が主張しているんだから事実なんだろうと、内容を疑うことなくそのまま報じていると指摘しています。
京大では鏡の研究に関して伝統があるが、出土品についてくわしく記録して目録を作っているだけにすぎない。その目録から自分が持っている「仮説」を裏付ける「事実」だけを抽出している。
安本さんが発掘成果やその研究成果をデータ化して比較する手法は、注目する価値があると思います。
3.「邪馬台国の謎を解く IT(情報技術)のV字アプローチを用いて」
★システムエンジニアリングの手法
「邪馬台国の謎を解く IT(情報技術)のV字アプローチを用いて」の著者は大野治さん。
元日立製作所の執行役員常務で電力システム社CIO。バリバリのシステムエンジニア(SE)。
日立グループの情報システムを刷新し、モノとインターネットつなぐ「loT」の基礎を築いたといわれている人です。
そんなエキスパートが「邪馬台国」について、帰納法を使って比定地を導き出しているんです。
帰納法は多くの事実や事例から共通点をまとめて、その共通点から分かる根拠をもとに結論を導く方法。
要するに邪馬台国に関するこれまでの研究成果から共通点をまとめて、その共通点から比定地を導き出しています。
前項の安本さんは畿内大和や九州を始め、各都府県で発掘された遺物数をデータ化して比較し「九州説」の優位を主張しています。
一方、大野さんは文献・遺物などの研究結果やデータを整理。さらに地理学や当時の人口動態、運搬能力などもチェック。
それらから共通点をまとめ「九州説が優位」という仮説に到達。その仮説に関わる各事象を1つずつ丁寧に検証する手法をとっています。
この検証の仕方がメチャ説得力があって面白いんです。
★説得力がある検証
この作品での大野さんの検証内容は、めっちゃ説得力があるんです。
一番感心したのが、邪馬台国の比定地の検証。3世紀の地理的な条件から「どこが邪馬台国にマッチするのか」を説明しているんです。
作品では邪馬台国の総戸数は7万戸超とされていて、人口は約3・5万人との推計を紹介しています。
大野さんは、これだけの人たちの生活を支えることができる土地はどこが最もふさわしいのか?
当時の食の基盤である水田稲作をキーとして、各比定地を比較して調べています。
6000年前(縄文時代)の日本の国土は「縄文海進」といわれる状況で、ほとんどが海の中。
邪馬台国が存在したとされる弥生時代(3世紀)に入って、北九州地域では水田稲作が可能な土地が増えてきた状態だったそう。
一方で畿内地域は、その大部分が巨大な湖だったそうです。そして水が引いて稲作が可能になったのは4〜5世紀と推測。
邪馬台国の〝国民〟3・5万人のための食料生産ができる地は「北九州」とする仮説を導いているんです。
また、3世紀ごろの国内の交通(土地)事情についても検証。当時の主な交通手段は船と歩きでした。
そして朝鮮半島に渡る航路としては潮流を利用するため、魏に朝貢するための船は北九州か丹後、越前から出発していたと推測。
ちなみに国内の航路は日本海沿岸に沿ったコースで、陸岸に目標を掲げながらの航海だったそうです。
一方で瀬戸内海の航路ができたのは6世紀頃としていて、その意味からも魏に朝貢するための船が出ていたのは北九州だと仮説しています。
大野さんは魏志倭人伝などの文献や遺物についても、これまでの研究成果などで比較。
当時の地理事情や食糧生産の状態、交通事情なども比較して検証し、邪馬台国は「福岡平野から筑紫平野の周辺」と推測しています。
 |
| 古代中国から伝わった銅鏡の像 |
★古代史の謎に迫る検証も
大野さんは「邪馬台国」以外にも、古代史のさまざまな謎に迫る検証を実施。これもメチャ面白いんです。
例えば日本人の起源。日本人はどこからやってきたのか?
大野さんはDNA分析など生物学の面から検証。日本人を含めた各人種のDNAの特徴を比較し、日本人の誕生の経緯を推測しています。
さらに、歴史的な事実ではないとされている神功皇后の「三韓征伐」や、宋書など中国国史に登場する「倭の五王」。
さらに6世紀ごろに起こったとされる「磐井の乱」なども検証。これらと「邪馬台国」との関わりについて言及しています。
大野さんの検証は多岐にわたっていて、従来の研究者たちを圧倒している感があります。
例えば、これまでの畿内大和説派や北九州説派は、文献や鏡などの出土物や遺跡だけの分析に終始していた感じ。
だから議論は平行線をたどっていたと思います。
でも今は、ここまで説明してきたように地理学や人口動態、生物学などさまざまなアプローチ方法があります。
大野さんは、そのアプローチ法を使わない手はないと、さまざまな切り口から邪馬台国に迫っています。
素人から見ても、邪馬台国研究者たちは大野さんの切り口を無視してはいけないと思うんです。
そして大野さんの検証内容はめっちゃ面白いので、ぜひ作品を読むことをオススメします。
4.「Q&Aでよくわかる!! 阿波倭邪馬台国論入門」
★都市伝説YouTubeでも話題に
歴オタの方なら、邪馬台国「阿波徳島説」は最近よく耳にしていると思います。
YouTubeの都市伝説チャンネルや歴史チャンネルなどでも、特集動画が増えていて大人気です。
阿波徳島説は、1976(昭和51)年発刊の「邪馬壱国は阿波だったー魏志倭人伝と古事記の一致ー」でお披露目された説だそう。
でも、徳島では昔から「邪馬台国は阿波にあったんじゃ」と語り注がれていたんだとか。
そして阿波徳島説の主な主張は、
- 邪馬台国は大和政権の前進として阿波の山の上で成立した。
- 古事記や日本書紀に出てくる皇祖神・天照大神は卑弥呼のこと。
- 古事記などの神話とその舞台は、すべて阿波を舞台にした神話。
ざっと、こんな感じです。
そして「Q&Aでよくわかる!! 阿波倭邪馬台国論入門」は、2019年に菅井英明さんが刊行。
菅井さんは著述家・音楽家で徳島・藍住故事研究会の会長でもある方。
作品ではQ&Aの方式で、阿波徳島説に関するさまざまな疑問に答えています。
阿波徳島説に関する作品の中では、すごく分かりやすくて頭にも入りやすい感じ。
読み進めていくと「なるほどなあ、邪馬台国はホントに徳島にあったのかも…」なんて思っちゃうほど説得力があるんです。
★日本神話は全て徳島で起こったこと
この作品で説明されている内容は、めっちゃ衝撃的。
だって、邪馬台国=大和政権は徳島の山上で誕生して、日本神話はすべて徳島周辺で起きたことっていうんですから。
例えば、弟の素戔嗚尊(スサノオノミコト)の狼藉に怒り、天照大神が岩屋に隠れたため世界が闇に包まれたという「天岩戸」。
亡くなった伊弉冉尊(イザナミノミコト)を慕って、伊弉諾尊(イザナギノミコト)が訪ねた「黄泉平坂(よもつひらさか)」。
さらに高天原を追放されたスサノオによる八岐大蛇(やまたのおろち)退治。
有名すぎる日本神話はすべて徳島周辺で起こったことで、その痕跡である遺跡や遺物、地名がすべて徳島周辺にある!
さらに島根・出雲地方が舞台で、大国主神(オオクニヌシノミコト)が主役の出雲神話もすべて徳島が舞台だと!
だから「国譲り神話」も、徳島の山上にあった高天原の天孫族が、その近くにあった出雲を制したと主張しているんです。
魏志倭人伝に記されている邪馬台国への道程に関しても、記述通りにいくと北九州と畿内大和はハマらない。
でも、阿波ならば方向・距離など全てがハマる、と。
また山上に国(高天原)を置いた理由については、紀元前後に発生した大地震と津波の影響だとしています。
日本は「地震国」といわれるだけに、古代から地震の被害を受け続けていた。
そして地震と津波の影響を避けるため、山上に国を置いたと説明しています。
 |
| 徳島の祖谷渓谷 |
★なぜ阿波徳島説はこれまで広まらなかったの?
菅井さんによると、阿波にあった邪馬台国は四国、瀬戸内の島々、さらに北九州、壱岐、対馬と支配地を拡大。
そして阿波から開拓者たちが各地に派遣される中、神武天皇が畿内大和地方でも政権を樹立。
阿波と大和を拠点としつつ、飛鳥時代に皇族が一斉に畿内(奈良)へ移動したと主張しています。
作品の中で説明されている阿波説の内容に驚くと同時に、疑問も出てきます。
皇室の故郷=聖地を往時のまま残しておきたかったのではないか。皇室ゆかりの地と知られたら、遺跡を荒らし破壊する者も出てくる。明治のころから政府はひそかに発掘したものを中央に運んでいる。阿波と中央(皇室)は関係ないように見せかける理由があるのではないか。
菅井さんは、それでも阿波と皇室のつながりを示す証拠として「麁服(あらたえ)」があると主張しています。
「麁服」は天皇の代替わりの際に行われる儀式「大嘗祭(だいじょうさい)」で、新天皇が身につける服のこと。
はるか昔から現在に至るまで、阿波に住む忌部氏が皇室からの注文を受けてつくっているモノです。
徳島をはじめ四国には神話や古代史にまつわる地名や遺跡がたくさんあり、「麁服」など皇室と深いつながりを示す事例もある。
邪馬台国の比定地候補として、改めて注目したいところです。
まとめ・4作品を読んで謎の女王国を追いかけろ
 |
| 福岡・志賀島で発見された「漢委奴国王」の金印のレリーフ |
ここまで「邪馬台国論争」や比定地の有力説が分かる研究本について紹介してきました。
そして畿内大和説、北九州説、阿波徳島説のことが分かる、
- 「ここまでわかった!邪馬台国 『魏志』倭人伝全文を読む!」
- 「データサイエンスが解く邪馬台国 北部九州説はゆるがない」
- 「邪馬台国の謎を解く IT(情報技術)のV字アプローチを用いて」
- 「Q&Aでよくわかる!! 阿波倭邪馬台国論入門」
上記の4作品を紹介&解説してきました。
この記事を読んで、4作品がいずれも邪馬台国や論争について分かりやすくて面白いこと。
そして比定地の有力説の研究成果や最新情報も分かったと思います。だから、
「邪馬台国って、どこにあったんだろう?」という興味がある人。
最近になって興味をもった人や、ワタシのように急に「邪馬台国」熱がぶり返した方で、
「邪馬台国論争って、今はどの説が有力なの⁉︎」
「邪馬台国や論争について分かりやすくて面白い、お勧めの本を教えて!」
なんて方にはぴったりの作品なんです。
この記事を読んで邪馬台国のことをもっと知りたいという方は、ぜひ4作品を読んでみてください。
謎の女王国を追いかけてみたくなりますよ!
当ブログでは、ほかにも歴史が大好きになる作品を紹介しています。ぜひご覧ください。
「宗像教授世界篇」謎の遺跡ギョベクリ・テペに迫る異能の民俗学者が掲げる注目の3つの仮説
坂本龍馬は薩摩藩士?フリーメーソン?暗殺の黒幕は?幕末の英雄の新事実が面白い「龍馬本」3作品
八王子、群馬、沖縄…ディープな日本史・郷土史が勉強できて最恐の「ご当地怪談本」厳選3作品
中高生におススメ!苦手な日本史が好きになる歴史小説4選と活用法
この記事で紹介した4作品をすぐ読みたいという方は、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。
「ebookjapan」「BOOK☆WALKER」などのブックストアなら無料で試し読みができますよ!
読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」
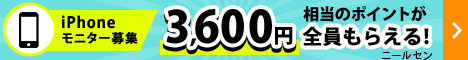
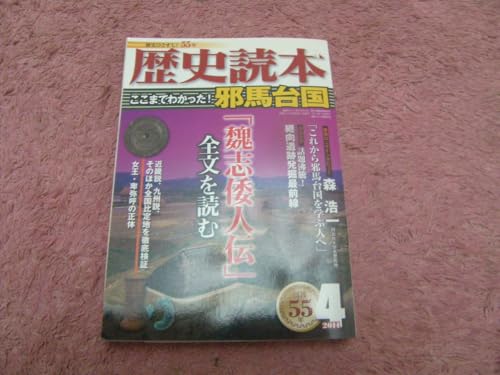








0 件のコメント:
コメントを投稿