 |
| 日本列島が沈没する衝撃的なストーリーは不滅の人気を誇る |
原作である昭和の名作SF小説を超えるコンセプトがエグすぎる
漫画のSFパニック作品で、天変地異に遭遇する「災害モノ」は人気のジャンルです。
「もし、住んでいるところが災害に襲われたらどうなるの⁉︎」なんて、非現実的な世界観に没入することができたり。
「天災は忘れたころにやってくる」と天変地異への備えとして読んだり。だから、
「災害やサバイバル系のストーリー漫画を読みたい」という人が結構多いんです。
そんな方たちにオススメの漫画として人気や評価が高いのが、一色登希彦さんの作画による作品「日本沈没」です。
SF作家・小松左京さんの昭和の名作小説を原作とした作品。この原作をベースにした斬新な地震発生理論や災害発生時の描写。
さらには感動的な人間ドラマとしても、高く評価されているんです。それだけに、
「地震が発生した描写がかなりエグいって聞いてるけど、実際はどうなの?」
「地震のメカニズムなど、原作とは違う設定のストーリーが描かれているって聞いたけど、どんな感じなの?」
「サバイバルのヒューマンストーリーとしては面白いの?」
そんな声がたくさんあるんです。
この記事では、漫画版「日本沈没」が持っている特徴と魅力について、
- 現代の科学的知見による大地震が発生した場合の描写がエグすぎる
- 原作を超える地震発生メカニズムの内容が斬新でスゴすぎる
- 登場人物など災害に直面する「日本人」の人間ドラマがリアルすぎる
上記の3つの魅力について紹介&解説します。
この記事を読めば漫画版「日本沈没」の特徴的なストーリー、大地震が発生した際の描写や地震メカニズムの斬新さが分かります。
さらにはリアルなサバイバル人間ドラマとしての魅力も分かって、作品のページを開いてみたくなりますよ。
※この記事ではアフィリエイトプログラムを使って商品を紹介しています。
「日本沈没」ってどんな作品なの⁉︎
この記事で紹介する漫画版の原作「日本沈没」は、1973(昭和48)年に小松左京さんが発表したSFパニック作品です。
舞台は197×年の日本列島。伊豆・天城山の噴火や小笠原諸島の小島が沈没するなどの大規模災害が発生した。深海調査など現地を調べた地球物理学者・田所雄介博士は、日本列島が沈没する予兆だと確信する。田所博士の進言を受けて日本政府は「D計画」を発足。全日本人を救うための海外避難計画を推進する。田所博士とともに「D計画」を進める主人公・小野寺俊夫ら登場人物たちが、沈みゆく母国を舞台に人間ドラマを繰り広げる。
コミカライズもされて、1973年から1974年まで「週刊少年チャンピオン」でさいとうたかをさんが連載しています。
そして2006(平成18)年から2008年まで「ビッグコミックスピリッツ」で一色登希彦さんが連載。コミックスは全15巻が発売中。
ドラマや映画版、漫画版はいずれも小松さんの原作をベースにする一方で、ストーリーや設定に独自のアレンジが加わっています。
その中で一色さんの漫画版は、現代の科学的な知見に基づいて、今の日本で大災害が発生したらどうなるのか?
地震メカニズムについての斬新な理論や、大災害に直面した登場人物ら日本人のリアルな人間ドラマがメチャ素晴らしいんです。
最近(2025年7月)では、漫画家・たつき諒さんの作品「私がみた未来」が大注目されました。
作品で注目を集めた「大災難」の予言は外れましたが、この作品によって防災への意識が高まっています。
それだけに新知見を盛り込んだ一色さんの漫画版はぜひ読んでほしい作品です。
次項からは一色さんによる漫画版が持つ魅力を、1つずつ紹介&解説していきます。
1,現代の科学的知見による大地震が発生した場合の描写がエグすぎる
★新宿の雑居ビルでの異変
漫画版「日本沈没」で描かれる災害時の描写は、とにかくエグい!
第1話から始まる「序章/地下の竜巻編」から、作品を読む人はストーリーにわしづかみされてしまいます。
舞台は11月の東京・新宿。深海潜水艇のパイロットの仕事をこなして上陸した小野寺は、同僚の結城慎司と酒を飲みにいきます。
小野寺と結城は雑居ビルにある居酒屋「雑種天国」へ。入り口近くのビルのすき間で調べごとをしている田所博士に気づく。店内は大繁盛で、非番だった東京消防庁のハイパーレスキュー隊員、阿部玲子が仲間たちと飲み比べをしていた。玲子たちと小野寺&結城が相席になり飲んでいると、田所博士が店内に入ってきて「このビルは危険だ」と告げる。さらに蒸し暑い店内を見渡し「熱力学的見地で語るならば、熱いということは色々なことが起きているということだ」と指摘。
ビルの周囲の土からたくさんのセミの幼虫が出てきて孵化を始めたり。店内ではテーブルのグラス内のお酒が傾いていたり。
小野寺は自分がいるテーブル付近の危険を察知し、玲子や結城らに「テーブルから離れろ!」。小野寺の言葉に、結城は「デラ(小野寺)さんの言うことを聞いてくれ」と相席者たちをテーブルから離れさせた。
★雑居ビルだけが地中に沈んでいく
テーブル周辺での異変を回避した小野寺たちですが、さらに異常な事態は加速していきます。
玲子と田所博士に「2歩下がれ!」と小野寺が命じた直後に柱が落ちてきたり。
脱出しようとした客たちが「出口が閉じていく!」。雑居ビルは地中に沈み始めていた。異変は雑居ビルだけのため通行人は気づかない。玲子が「助けて! 119番に連絡して!」と叫んでも素通りしていく。結城ら数人が先に店外へ出て、中の客たちを引っ張り上げる救出作業に入った。
その描写がマジでエグい…。大半の客が脱出し、店内に店主と小野寺、田所博士、玲子が残った時点で出口が完全に沈んでしまい…。
そんな状態でも小野寺は冷静で、途中で揺れの「戻し」があり脱出口が開くのを察知して1人ずつ脱出させていくんです。
その間にハラハラドキドキの人間ドラマが展開されて、危地にいる人の心理描写がめっちゃリアルに描かれています。
詳しくは作品を読んでほしいのですが、ワタシ的に刺さったのは通行人たちの態度、姿勢。
もちろん救出に手を貸す人もいるけど、多くの人たちがビルから救出される姿とビルが沈んでいく様子を携帯で撮影している。
現代の災害時では象徴的な描写です。実際の災害時でも動画が公開されていて、見るたびに何とも言えない気持ちになる。
被災の当事者にならない限り、他人事という感じなんですよね。
隣接するビルが何の影響も受けない一方で、雑居ビルはネジ曲がりながら地中に飲み込まれ、跡形もなくなります。
居合わせた人たちが、他人事のように一部始終を携帯で撮影している前で…。
でも、事態は他人事どころじゃなくなってくるんです。
 |
| 京都の象徴・金閣寺が沈んでいく… |
★日本人のふるさと・京都が消える
新宿の異常事態から1カ月がたった12月。伊豆でマグニチュード6.5の大地震が発生します。
これを皮切りに、日本列島全体で大災害がボッ発していくんです。
伊豆・天城山、さらに三原山で大規模噴火が発生。そして三原山の噴火とともに地震津波が襲いかかる。この描写がトテツもないんです。
小野寺と玲子は2人で初日の出を見にきた江ノ島の海辺で噴火&地震に遭遇する。危険を察知した玲子は海辺の人たちに避難を呼びかけるが、海の向こうの現象(異変)に魅入られるように誰も動かない。大波は人々を飲み込み、約1キロ先の長谷の大仏にまで到達するほど。海辺の街は無数の車や瓦礫、遺体に覆われてしまった。この「相模湾地震大津波」の犠牲者は21万人にまで及んだ。
作品で描かれた大津波シーンは、東日本大震災で発生した大津波の脅威がフラッシュバックするほどリアルでした。
京都の朝の空にオーロラが発生。突じょ強烈な揺れが襲い、京都タワーがネジ曲がりながら倒壊。マグニチュード8の地震は京都駅を崩壊させ、新幹線は横転。崩壊したビルから落ちてくる窓ガラスが路上の人たちに降り注ぐ。人気観光スポットの金閣寺はゴボゴボと泡立つ周囲の池の中に沈んでいく。
前述したように、大津波がくることに気づかずキョトンとした表情で津波に飲み込まれていく人たち。そんな無防備な人たちが都市型災害に遭遇する。
大きな揺れで動けずにおびえ、横転する新幹線に巻き込まれる人たち。降り注ぐガラスが体中に突き刺さった人たち。
大災害が大都市で発生した場合に起こりうる地獄絵図が描かれているんです。
そして作品中で最も悲惨なシーンといえるのが、第44話から始まる「記憶喪失の国、記憶喪失の首都編」。
1923(大正12)年に発生した関東大震災以来となる、首都直下型地震が発生した様子が描かれています。
大正時代とは比べモノにならないくらい、都市の機構が発達し人々が集まった首都周辺で大災害が発生したらどうなるのか?
作品によると、21世紀初頭に日本政府は「死者数1万人」と想定していたそうですが、この想定がいかに甘すぎるか…。
この理由は、ぜひ作品で確認してください…。
2.原作を超える地震発生メカニズムの内容が斬新でスゴすぎる
★全日本人を国外に脱出させる「D計画」
原作や漫画版などを含めた「日本沈没」では、各地でボッ発する異変を受けて政府が地震や災害に関する有識者たちを招集します。
尾形茂弘首相の信頼を得た田所博士ら学者たちが、小野寺らが操縦する深海潜水艇で日本海溝など各地を調査。
深海などで日本の国土に壊滅的な危機が迫っているという報告を受けて、政府が極秘にプロジェクトチームを結成。
このチームが推進するのが「D計画」です。
「D計画」は2段階に分かれていて、「Dー1」は日本の国土で何が起こっているのか?
そして最悪の場合、国土で何が起こるのかを調べて確定させることが目的です。
そして「D−2」は最悪の場合に対応する計画。全ての日本人と日本の資産を国外に脱出させることが目的。
そのため具体的な脱出方法や、避難民の受け入れ先となる各国との調整を進める役割をになっています。
メンバーは地球物理学者・田所博士、海洋地質学者・幸長助教授、情報科学者・中田、そして深海潜水艇パイロットの小野寺など。
政府側からは尾形首相をトップに、総理府総務長官や内閣官房長官、防衛庁(当時)長官が極秘に参加。
内閣調査室の山崎が政府と田所らメンバーとの橋渡しを務めているチームです。
ちなみに原作やテレビ版などでは「D」の意味は明かされていませんが、この漫画版では「Diaspora(ディアスポラ)」として紹介されています。
「ディアスポラ」は「散らされた」という意味で、かつて国を追われたユダヤの人々を示す言葉です。
そして、この「D計画」が脱出計画を進める上でよりどころとしているのが「プレートテクトニクス理論」です。
★「プレートテクトニクス理論」
「プレートテクトニクス理論」は1960年代に注目を集めた地球科学の理論です。
地球の表面は何枚かの岩盤(プレート)で構成されていて、このプレートがマントル対流などで移動しているという理論。
いわゆる「大陸移動説」と「マントル対流説」がベースとなっています。
そして各プレートの境界は接していて、プレートがもう一方のプレートの下に沈み込む。
やがて下のプレートに巻き込まれた上のプレートが限界に達して、「ズルッ」と跳ね上がって元に戻る。これが地震の原因だとしています。
日本列島は「ユーラシアプレート」「北米プレート」「太平洋プレート」「フィリピン海プレート」の4プレートに囲まれている。
各プレートで沈み込みと跳ね上がりがあるから、日本は「地震大国」と呼ばれている、というわけです。
この理論を根本的なよりどころ(理由)として推進したのが「D計画」であり、全面的に紹介したのが「日本沈没」だったんです。
1973(昭和48)年の映画版で、東大教授で物理学者の竹内均さんが「プレートテクトニクス理論」を説明するシーンがありました。
竹内さんが「ズルッ」というたびに、説明映像の中のプレートが跳ね上がる。このシーンが生々しくて、メチャ怖かった…。
ただ当時から、学界から「プレートテクトニクス理論では、日本列島は沈まない」と指摘されていました。
原作者の小松さんも、学者さんたちとの対談でこの事実を認めています。
でも小松さんの日本が沈没するアイデアなどは、学者さんから「修士論文に相当する」と高い評価を受けているんです。
そして漫画版「日本沈没」では、従来の「プレートテクトニクス理論」などでは説明しきれない事象があると指摘。
各理論は「大いなる錯覚」として、斬新な理論を展開しているんです。
 |
| 地球上の大陸の地下はどうなっているのか? |
★「マントルコーン理論」
「プレートテクトニクス理論」では説明しきれない事象を、説明するための理論。
1990年代以降に「プレートテクトニクス」を補完する新理論として登場したのが、「プルーム(煙)テクトニクス」です。
地面の下には岩石でできたマントルが存在して、このマントルが粘り気のある濃い液体のようにゆっくりと流動している。
これが「マントル対流」といわれていますが、「プルーム」理論では地下でマントルの上下の流動があるとしています。
1つは「ホットプルーム」(上昇流)。深部で熱くなったマントルが上昇してくるモノ。
この熱で地表付近のマントルやプレートが溶解して、火山や地震が発生する。
もう1つが「コールドマントル」(下降流)。冷たいマントルが地表付近から深部へ下降していくモノ。
下降することでプレートを引きずり込む力が働くため、群発地震や大規模地震が発生するとされています。
原初の地球にできた陸地は自転などの作用でほころびができて、やがて五大陸やさまざまな島々として裂けた。裂けた陸地の下はマントルプルームのように地球の深部につながっていて、円錐(コーン)のようになっている。各陸地のコーンは干渉しあうことで細かくなり、地球の地殻に大きな影響=変動をもたらす。
メチャ斬新で思わず「そうかも…」とナットクしちゃいそうな理論。これって作画した一色さんの創作だそうです。
でも「推論、帰結ス。⑦」で田所博士がこの理論を力説するシーンは、めっちゃリアリティーがあって恐ろしいんです…。
3.登場人物など災害に直面する「日本人」の人間ドラマがリアルすぎる
★阪神大震災の被災者
「日本沈没」はSFパニック作品ですが、大災害に遭遇する登場人物たちのサバイバル、人間ドラマが展開される作品でもあります。
まずは主人公の小野寺俊夫とヒロインの阿部玲子。2人は幼少期に関西に住んでいて、阪神大震災に遭遇しているんです。
少年時代の小野寺は引っ込み思案で、両親の夫婦仲がよくない環境に育ちました。
やがて父親とアメリカに移ることになった直後、大震災が発生。両親を亡くした一方で、小野寺は1人生き残りました。
以後、移住する予定だったアメリカへ渡り、世界海洋財団の庇護を受けつつ潜水艇のパイロットに。
天性の危険察知能力を生かして世界有数のパイロットとなり、帰国しました。
一方で孤独感と厭世の気質が強く「こんな世界どうとでもなればいい」。心の中でそんな思いを抱えていました。
そして玲子も大震災で家族を失い、自身も自宅の残骸の下敷きになった経験があります。
家族を救えなかった悲しみと悔しさから、レスキュー隊員となって救助活動に突き進むけど、危険をかえりみないこともしばしば。
そんな2人が新宿の雑居ビルで出会い、地中に沈んでいくビルで救助活動に奮闘するんです。
「人の世話を焼いた後、自分の命を守らないヤツにヒーロー気取りされちゃ、残された方は我慢ならない」「おまえともこんな出来事とも2度と関わりたくない。おれは海の底の方がいい」
そんな2人は、さらに起こり続ける大災害の地で交錯していきます。
★尾形首相の覚悟
ある日、「今から大地震が起こるので、今すぐここから逃げてください」といわれたら、みなさんはどうするでしょうか?
怖いと思いつつも「まさか…」「そんなこと信じられるか⁉︎」と半信半疑になって、その場に居続けるんじゃないでしょうか。
第61話「核保有ヲ論ズ③」と第62話から始まる「冥府、火の国編」では、尾形首相が命をかけて避難を呼びかけます。
田所博士らの調査と情報科学者・中田の分析で日本沈没は確実になり、大災害が発生する場所と正確な日時まで予測が可能になりました。
一方で予測通りに災害が発生するのか、検証する必要がある。
だから予測された京都、東京での大震災時は、「D計画」は国民に知らせず事態を見守りました。
大地震は予測通りに発生。多くの犠牲者を出したことに尾形首相は「国民を見殺しにした」という罪悪感にさいなまれていました。
さらに「D計画」は熊本で災害が発生すると予測し、国外脱出計画「D−2」を進めるため日本が沈没する事実を国民に発表することを決定。
発表の真実性を高めて避難を呼びかけるために、尾形首相が単身で熊本に乗り込むんです。
「あと5時間で阿蘇山がカルデラ爆発します!」「その予言が当たった場合、1年たたず日本は沈没します」「噴火した場合、熊本はただではすまない。この尾形の死ぬ姿を目にすることで日本沈没の事実を受け入れていただく」
当然ながら、首相の呼びかけに熊本の人たちや国民は「何言ってんだ⁉︎」と困惑。
「逃げなきゃ!」という人の一方で、多くの人たちが「総理がおかしくなった…、そうであってくれ︎」とその場に居続ける。
さらに政敵であり首相の足を引っ張りたい政権党の大柳幹事長が、「日本沈没は妄言だ」とテレビ番組で呼びかける。
だが5時間後、無情にも予測通り阿蘇山が大噴火。熊本は地獄と化します…。
首相は「みんな逃げて!」と叫びつつ、降り注ぐ噴石に「俺に当たってくれ!」「熊本とともに死なせてくれ!」。
噴石の雨に襲われる自分の姿がテレビ中継されることで、日本沈没の事実と国外脱出の必要性を訴える。
国のトップの責任と覚悟が問われる人間ドラマとして、このエピソードは心に刺さるんです。
 |
| 熊本城に阿蘇山の噴石が直撃する… |
★全日本人が難民になる
熊本の阿蘇山大噴火以降も災害が発生。日本列島は被災地だらけになっていきます。
被災地の治安は最悪で、発生した野盗と自警団が血を流し合う。一方、人々には諦めの感情がうずまき、無気力感に支配されていくんです。
一方で「D−2」計画も進み、日本政府は避難民の受け入れに関して各国との交渉・調整に奮闘します。
でも各国との交渉の場である国連で、日本政府は重大な事態に直面します。
「日本人を1人残らず脱出させ、世界各国で受け入れるのは現実的に困難」
全日本人は難民になるわけですが、現実世界でも難民は世界的な問題です。
何万、いや何十万もの「日本難民」を受け入れて、その国の社会はどうなってしまうのか⁉︎ というワケです。
受け入れ直後に難民は保有する財産を提出すること。財産は受け入れ先が所有する。難民が使う言葉は、受け入れ先が決定。難民の姓名の呼び方も受け入れ先が決める。難民の居住場所や社会的権利などは、受け入れ先が決める。
日本人としての尊厳を奪われる重大事に、日本政府と日本人はどう決断を下すのか⁉︎
この続きはぜひ作品をご覧ください。漫画版「日本沈没」の見どころの1つでもあります。
まとめ・日本沈没後の日本人を描く原作の「第二部」にも注目
 |
| 「第二部」では災害が地球規模で発生する |
ここまで漫画版「日本沈没」について紹介してきました。
そして、この作品が持つ魅力として、
- 現代の科学的知見による大地震が発生した場合の描写がエグすぎる
- 原作を超える地震発生メカニズムの内容が斬新でスゴすぎる
- 登場人物など災害に直面する「日本人」の人間ドラマがリアルすぎる
上記の3つの魅力について紹介&解説してきました。
人気ジャンルで数多くあるSFパニック作品の中でも、漫画版「日本沈没」は評価が高い作品です。
この記事を読んで、作品の特徴的なストーリー、大地震が発生した際の描写や地震メカニズムの斬新さが分かったと思います。
リアルなサバイバル人間ドラマとしての魅力にあふれていることも分かったと思います。だから、
「地震が発生した描写がかなりエグいって聞いてるけど、実際はどうなの?」
「地震のメカニズムなど、原作とは違う設定のストーリーが描かれているって聞いたけど、どんな感じなの?」
「サバイバルのヒューマンストーリーとしては面白いの?」
そんな疑問がある方こそリアルに刺さるので、ぜひ読んでいただきたいと思います。
そして最後に。小松さん原作の「日本沈没」には、「第二部」があります。
谷甲州さんとの共著で、日本沈没後に各国で生きる日本人はもちろん、地球全体に発生した異変に直面する人類の姿が描かれています。
実は漫画版の最終話は「第一部 完」という文字でしめられていて、「第二部」を予感させるエンディングとなっているんです。
漫画版の続きがあるとすれば、「第二部」の内容に加えて作画の一色さんの構想が加わる可能性がありそうです。
「一色さんの構想」のヒントは漫画版のストーリー最終盤に盛り込まれているので、その意味でも作品のページを開いてみてください。
当ブログではほかにも面白いSF漫画を紹介しています。ぜひご覧ください。
「百億の昼と千億の夜・ネタバレ」宗教、科学、宇宙論…面白いけど難しい名作SFが分かる4つの基礎知識
「バビル2世 ザ・リターナー」昭和の人気超能力漫画の〝続編〟秀逸すぎるストーリー&設定3つの魅力
怪物、ゾンビ、悪魔の黙示録「人類の危機」に遭遇するスリル感がヤバイ「パニックマンガ」5作品
この記事で紹介した作品を「すぐ読みたい」という方は、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。
「BOOK☆WALKER」などのブックストアなら無料で試し読みができますよ。
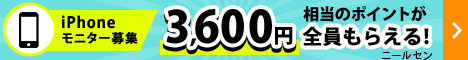









0 件のコメント:
コメントを投稿