 |
| テントの前には最高の景色が広がる |
外遊びの楽しいイメージが活字から広がる
森の中で味わうさわやかな空気。浜辺に座って耳にする潮騒の心地よさ。
山や海など自然の中に飛び込んで楽しむアウトドア。メチャ楽しくてリフレッシュには最高の趣味、レクリエーションです。
人気マンガ「ゆるキャン△」のヒットでキャンプブームが続く中、家族や友だち、恋人と外に飛び出して楽しんでいる人が多いと思います。
一方で「キャンプって、楽しいの?」という人が少なくありません。
「アウトドアをやってみたいけど、けっこう大変なんじゃない⁉︎」とためらう人も…。
二の足を踏む理由(後述)はたくさんあるでしょう。私も最初は「ホントに面白いの⁉︎」と疑ってました。
でも、アウトドアがテーマの小説を読んだことで考え方が一変。
「アウトドアって、キャンプって、面白いかも…」
エンジンがかかって、キャンプやカヌーの川下り、釣りなどの小説にドップリ。
「アウトドアやってみてぇ~」という気持ちが高まり、社会人になって自由にできるオカネができ、家族もできて「さあ行くぞ!」。
みごとにハマりました(笑)。
理由は、めっちゃ面白い外遊びの描写がアタマの中に楽しそうなイメージを作ってくれたから。
この記事では「やってみたいけど大変そう」とためらう人がハマってテントを張りたくなっちゃう、面白いアウトドア小説をチョイス。
- 「わしらは怪しい探検隊」(著者・椎名誠)
- 「のんびり行こうぜ」(著者・野田知佑)
- 「二つの心臓の大きな川」(著者・アーネスト・ヘミングウェイ)
以上の3作品について紹介&解説します。
この記事を読めば、3作品で描かれているアウトドアライフの魅力が分かってめっちゃハマります。
さらに、もっと作品を読みたくなってドップリ。「キャンプって面白そう!」とテントを張りたくなりますよ。
「キャンプが苦手」な原因は解決できる
 |
| 自然の中で飲むお酒は最高ですよ |
アウトドアをやってみたいけど二の足を踏んじゃう原因。さまざまあります。その理由をあげると、
- 「昼間は暑いし、ハダが焼けそうでイヤ」
- 「夜になると冷えるんじゃないの?」
- 「外でゴハンがうまく作れるか自信がない」
- 「外でオシャレにゴハンを食べる意味が分からない。家で食べればいいじゃん!」
といったところ。さらには、
- 「トイレって、あるの? あっても汚そう…」
- 「だって、虫がいるじゃん…」「ヘビもいるじゃん…(ワタシです)」
おっしゃることは、ごもっとも。正論。自分も初めはそう思ってました。
でも、今は気候にマッチするアウトドアウエアがたくさん。タープやテントには虫除けのスクリーン(網戸ですね)が標準装備してます。
外メシ用の調理ギアもズラリ。火起こしや炊飯が簡単にできる便利ギアがたくさんあって、ネットにはコツを伝授する情報もあふれてます。
本の活字はマンガなどの映像以上に想像力をかき立てる。内容やディテールがくわしく描かれるのでイメージがわいてくる。
アタマの中がアウトドアのイメージでいっぱいになると、面白かったシーンを「自分で再現してみたい」と思うようになる。
さらに「早くやってみたい」。そんな強い気持ちが充満して「絶対やるんだ!」なんて信念みたいなモノが生まれ、実現。そしてハマる(笑)。
そんな効果が生まれます。ここからは3作品について、1つずつ紹介&解説します。
1.「わしらは怪しい探検隊」
著者は冒険&SF小説が人気の作家・椎名誠さん。
1980年に「北宋社」から単行本、1982年に角川文庫版が刊行。
「怪しい探検隊」の隊長である椎名さんと仲間たちが、日本の離島やキャンプ地を駆けめぐるドタバタ冒険私小説。
初期の隊名は「東日本何でもケトばす会(東ケト会)」。年を重ねていくにつれて、堕落したイマドキを憂う「いやはや隊」。
現在は釣りメインで時おりテント泊する「雑魚釣り隊」として活動中。
シリーズは電子書籍版でも発売中。第1作の「わしらは怪しい探検隊」は令和でも読み継がれているアウトドア小説のバイブルです。
★主な登場人物とあらすじ
主人公は椎名隊長。さらに学生時代の友人でイラストレーター・沢野ひとしさん(上の表紙)、弁護士の木村晋介さんら古参の幹部隊員。
椎名さんの勤務先(当時)の同僚で文芸評論家の目黒考二さん、「陰気な小安(稔一さん)」などなど。
「東ケト会」の隊員が、離島やキャンプ地に遠征し野営、焚き火宴会をやりまくる。
1960年代の国内が舞台。琵琶湖(滋賀)、式根島(東京)、神島(三重)、粟島(新潟)などの遠征の模様が描かれています。
ただ、そのキャンプシーンはオシャレさのみじんもない。
宴会のための食料、酒類を大量に買い込む。そのため運び役が必要で、友人や職場の若手を「ドレイ」として招集。大荷物にもかかわらず、鉄道など交通機関で移動するのが基本姿勢。目的は焚き火しての宴会。そのため人が来ない浜辺などを「キャンプ地とする」。キャンプ地周辺にトイレがなければ、草むらなどに穴を掘って簡易トイレに。撤収時は穴を埋めて帰る。
調理はどでかい鉄板や鍋を使用。食材をひたすら煮込み、焼いて一気に食い尽くす。酔っぱらってワケが分からなくなり、鍋のカレーの中に蚊取り線香が入っていたり。キャンプ地の天候や地形の確認はテキトー。なので危険な目に遭遇する。大雨で増水しテントが流されそうになったり、カミナリにおびえたり。蚊の襲撃を受けて一睡もできない事態に陥ったり。
 |
| 焚き火でつくるキャンプ飯は格別にウマい! |
★理屈じゃない!本能に刺さる面白さ
「この人たち、わざわざ離島まで行って何やってんの?」
石を集めてつくった焚き火台に、浜辺の流木や枯れ木を叩き割って火を起こす。その上に鍋と鉄板を直置き。肉や魚、野菜を焼き、食い続ける。酔っぱらって歌いながら焚き火の周りをグルグル回る。興が乗ると、ドレイ隊員の「火吹きの長谷川」が着火用ガソリンを口に含み、焚き火に吹き付ける。燃え上がる炎に大喝采。
でも、この原始的なものがキャンプ、アウトドアの根本でダイゴ味。
日々の暮らしとは違う、宵闇の中でのゴハン。焚き火から上がるオレンジの炎。パチパチと心地よく爆ぜる音。
理屈じゃなく本能に刺さる。やってるだけで楽しい。これがキャンプにハマる理由です。
シリーズはたくさんあって、キャンプギアの提供を受けたり舞台が海外になったり。キャンプシーンが洗練されていく感があります。
なので、アウトドアの根本的な楽しさを伝える意味では第1作が最高傑作。
「アウトドアに興味がある」という人は、ぜひ読んでください。背中を押してくれますよ。
2.「のんびり行こうぜ」
カヌーイストで作家、野田知佑さんの代表作の1つ。
野田さんは2022年3月27日に永眠されました。ご冥福をお祈りします。
作品は1986年に単行本が小学館から、1990年に新潮文庫版が発刊されています。
野田さんはカヌーで川を下りながら旅する「リバーカヤックツーリング」の先駆者として有名。
国内の有名河川や小さな川をはじめ、カナダのユーコン川なども旅していました。
「のんびり行こうぜ」では、千葉の亀山湖をはじめ、関東を流れる利根川、千曲川(長野、新潟)をカヌーでツーリング。
さらに余市川(北海道)、球磨川(熊本)なども漂い流れていきます。
川の両岸の先に見える日本の姿や現状を美しく、時には辛口で伝えているんです。
★アタマの中に川旅がイメージできる描写力
カヌーにはテント、ストーブ(コンロ)、ヤカン、服などキャンプ道具を厳選して搭載。両端にブレード(漕ぎ面)があるダブルブレードパドルをあやつる。緩やかな流れではゆったりと漕ぎつつ周囲の景色をながめ、急流では的確にパドリング。日が暮れたら開けた岸に漕ぎ寄せてテントを設営し、ご宿泊。
おなかがすいたら川岸へ漕ぎ寄せ、インスタントラーメンをパパッと作ってズズーッ。魚がいそうな流れなら、舟から釣り竿を出して糸を垂れる。川のそばに露天風呂があれば、漕ぎ寄せてドブン。時にはカヌー犬・ガクを旅の相棒に。ガクは野田さんのそばに座りながら、川の流れとすぎゆく景色を見つめている。
 |
| 流れに乗って川を旅する。最高なシチュエーションだ |
★だれもがやってみたいことを実行する魅力
だれもが一度はやってみたいこと。ちょっと憧れていることを野田さんはやっちゃう。
だから読んでいて「いいなあ」「やってみたいなあ」とワクワクしてくる。
これが野田さんの作品の最大の魅力です。
自分もカヌーにはずっと憧れつつ、オカネも度胸もなく実行できないまま。
でも一度だけ、素晴らしい体験をしました。
夏の北海道への家族旅行。ニセコ西部に流れる尻別川のカヌーツアーに参加したんです。
舟はデッキが広いカナディアンカヌー。
奥さんと息子、それに愛犬(自己紹介ページに登場してます)が乗り込み、緩やかな川を5キロほど下るツアーでした。
カヌーからみる川と周囲の景色。岸からながめるのと違って、ものすごく視線が低くて、だだっ広い。
緩やかに流れる川の中央を進みながら、パドリングを楽しみ、流れる景色の美しさを味わう。
なぜか愛犬は舟首に仁王立ち。舟の進む先を黙って見つめている。
「うちのワンコがカヌー犬になった!」と家族で喜び、カヌーが大好きになりました。
野田さんが見ていた風景・景色って、こんな感じだったのか。少しだけ分かった気がしました。
「カヌー旅をやってみたい」。そう思っている方にとっては必読の名作です。
3.二つの心臓の大きな川
米国の文豪、アーネスト・ヘミングウェイの名短編。
1925年に発刊された短編集「われらの時代」に収録。新潮文庫「われらの時代 男だけの世界」で読むことができます。
ヘミングウェイは第1次世界大戦下で従来の価値観が崩れた社会と人々を描く、米国の「失われた世代」の代表的な作家。
戦争の虚しさを描いた「日はまた昇る」は素晴らしい代表作です。
「武器よさらば」「誰がために鐘は鳴る」「老人と海」などの長編小説も有名ですが、実は生粋のアウトドアマンなんです。
★幼い頃から手ほどきを受けたアウトドアマスター
ヘミングウェイは幼いころ、父親にキャンプや釣りの手ほどきを受けアウトドアをマスター。
大人になってからも米国の原野や川を野営して回っていました。その体験を元にした作品をたくさん発表しています。
「二つの心臓の大きな川」はヘミングウェイが10代のころの釣行経験をもとにした短編。
主人公はニック・アダムズ。ヘミングウェイ自身が投影されています。
食料、毛布などを詰め込んだザックにテントと釣り竿を両端に吊り下げて、歩きながら移動。野営しながら釣行を楽しむ。
列車から駅のない原野で途中下車、汗だくで歩いて川にたどり着き、テントを設営。石を集めて火を起こし、夕食。缶詰のスパゲティ、ポークビーンズを、ラードを落としたフライパンで炒める。舌をやけどしてキャンプ気分を壊さないよう冷まして味わう。
その描写が、その場にいるような感覚にさせてくれる。
 |
| ヘミングウェイは生粋のアウトドアマンだった |
★キャンプシーンのリアルさがたまらない
ヘミングウェイの文体は、めっちゃ簡潔&ていねい。
キャンプシーンでのちょっとした仕草の描写が分かりやすいんです。例えば、野営地の朝のシーン。
朝露に濡れた草地で動かず体を乾かしているバッタを捕まえる。釣りエサとしてビンに詰める。
缶詰のそば粉を水で溶いてフライパンで焼く。一方で玉ねぎを薄切りにしてパンにはさみ、かぶりつく。
川でのフィッシング。マスとの格闘シーンは圧巻です。
エサのバッタを針に刺し、狙ったポイントに落とすため、道糸は重めのものを使う。マスがヒットし、ググッと長い引きがくる。マスが走るたびに竿がしなり、ブルッとふるえる。
木にクギを斧でたたいて刺し、ザックを引っかける。即席の簡易収納棚。テントの中に止まっている蚊を見つけ、マッチをすって、その火で蚊をジュッと焼く。
そして、読んでいるうちにキャンプと釣りのやり方が分かる。
「ヘミングウェイって、こんな風にキャンプしてたんだ」
「米国のアウトドアって、こうやって楽しむんだ」と納得。
「自分もやってみたいなあ」と、憧れるようになりました。
ヘミングウェイの表現方法は、若い頃の新聞記者時代に身に着けたもの。
客観的に描写する手法は「ゆで卵のようにガチガチ」と評価され、「ハードボイルド」の語源になりました。
ハードボイルドに描かれるアウトドアシーン。最高です。
まとめ・だれもが持つ〝外遊びの欲求〟をくすぐってくれる
 |
| 小さな子どもでも楽しめるアウトドア |
ここまで3作品の魅力について紹介&解説してきました。
- 「わしらは怪しい探検隊」(著者・椎名誠)
- 「のんびり行こうぜ」(著者・野田知佑)
- 「二つの心臓の大きな川」(著者・アーネスト・ヘミングウェイ)
3作品に共通しているのは原始的、本能的な〝屋外での活動への欲求〟をくすぐる魅力があること。
人には潜在的に外遊びしたい欲求がある。怖い敵がいるかもしれないけど、外に出たい。
だれもが心の中でそう思っているんです。だから、
「キャンプって、楽しいの?」
「アウトドアをやってみたいけど、けっこう大変なんじゃない⁉︎」
とためらう人には、背中を押してくれるピッタリな作品なんです。
作品を読めば、絶対に「アウトドア、面白そうだね」「キャンプやってみようかな」とワクワクしてきますよ。
当ブログでは、キャンプやアウトドアについてほかにも紹介しています。よろしかったら、のぞいてみてくださいね。
ゆるキャン△で初心者でも完全マスター!キャンプの実践方法・火起こし編
※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して本や商品を紹介しています。
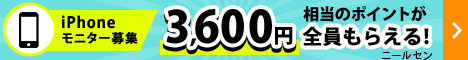








0 件のコメント:
コメントを投稿