 |
| SF小説は好きになると底なしの魅力にハマります |
マンガ版を合わせて読めばストーリーの世界観が2倍楽しめる
未来の世界や未知の宇宙など、幻想的・超現実的な世界観が楽しめる、SF小説。
スペーストラベルやエイリアン。タイムループ、ディストピア世界 etc。ストーリーの舞台がメチャ幅広い。
日々の生活からかけ離れた不思議な世界が展開して、現実逃避もできちゃう(笑)。だから、
「おもしろそうな作品があれば、読んでみたい」という人がたくさんいます。
でもSF小説には高い壁があったりする。サイエンスフィクションゆえの「科学的な用語」や少々長い説明要素。
「SF小説って、難しいですよね…」
「科学的な説明が多くて、とっつきにくい」
「難しい用語がたくさんあってイメージができない」
そんな悩みから読むのをためらう方もたくさんいるようです。
でも、そんな悩みでちゅうちょして〝知らない世界〟と出会えないのはもったいなさすぎる!
この記事では「難しくて」「とっつきにくい」SF小説がメチャ好きになってハマる名作をたくさんの作品からチョイス。
- 「星を継ぐもの」(著者、ジェイムズ・P・ホーガン)
- 「火星の人」(著者、アンディ・ウィアー)
- 「横浜駅SF」(著者、柞刈湯葉)
上記の3作品について紹介・解説します。
いずれもSFファンから高評価を得ている上に、初心者でも楽しめる。分かりやすくて前のめりになるほど好きになっちゃう名作ばかり。
この記事を読めばナットク&マンゾク。作品のページを開きたくなりますよ。
3作品をチョイスした理由
SF小説はテーマや舞台が幅広くて、いろんな世界や現象が展開するストーリーを楽しむことができます。
ただ前述したように、科学的な用語や説明がたくさん出てくる。
そのため「難しい」「とっつきにくい」というイメージが強くて、読むのをためらっちゃう。
でも、この記事で紹介する3作品には4つの魅力、セールスポイントがあります。
- ストーリー冒頭で説明要素すら不要に感じる謎やテーマが飛び出して心に突き刺さる。
- 謎やテーマがおもしろすぎて、自分から説明要素を読みたくなる。
- サバイバル・冒険要素やヒューマンストーリーも展開して感情移入してしまう。
- いずれもマンガ化・映画化されていて、合わせて読むと作品の世界観が完全に理解できる。
以上の4ポイントが素晴らしくて読みやすい。SF作品が好きになって、もっとほかの作品が読みたくなるからです。
ここからは1作品ずつ魅力を紹介・解説していきます。
1.「星を継ぐもの」
日本でも1980年に翻訳版が出版され、多くのSFファンをトリコにしました。
1981年には優秀なSF作品に贈られる第12回「星雲賞」海外長編賞を獲得。2015年時点で45万部の大ヒット作。
さらに続編「ガニメデの優しい巨人」「巨人たちの星」と合わせて「巨人三部作」といわれています。
ストーリーの冒頭で読者にトンデモない事実・現象を突きつける。話の進行とともにその謎が解明されていくハードSF。
いきなりトンデモない事実と謎がガーンとアタマに衝撃を食らわせる。その後はもう作品のトリコになってるんです(笑)。
国連宇宙軍が開発中の月面の洞窟で、奇妙なモノが発見された。赤い宇宙服に身を包んだ人間のような遺体だった。チャーリーと名付けられた遺体を放射性炭素年代測定したところ、5万年前に死亡という結果だった。所持品から現在の技術では造れない原子力パワーパックが発見され、放射性物質の半減期でも5万年前のモノとされた。
国連宇宙軍は生物学者のダンチェッカー、主人公で原子物理学者のハントを月面に招きます。
ダンチェッカーは透過撮影装置でスキャンした映像で推察。残った内臓、骨格などから地球出身の人間と断言する。だが5万年前の地球には宇宙服が作れるような高度な文明や痕跡もない。チャーリーが見つかった場所の近くでも構造物の廃墟を発見。携行食と思われるモノも見つかる。携行食の材料となった魚のような生物の構造を調べたところ、地球の生物とは全く違うことが判明する。一方で月から遠く離れた木星の衛星ガニメデで、調査隊が人類のものではない大型宇宙船の残骸を発見する。船内では大柄な体格で乗組員と思われる遺体と、数百万年前の地球の生物を発見。ガニメアンと名付けられた乗組員の体の構造を調べると、月面の魚のような生物と極めて似ていることが判明。
ハントら科学者たちは困惑しつつも、人類の発生や太陽系の本来の形などに関する〝真実〟に近づいていくんです。
 |
| 木星の衛星では大柄な体格の乗組員の遺体が… |
★5万年前に〝地球〟と月で戦争⁉︎
月に5万年前に死んだ宇宙服姿の人間、地球人が横たわっている⁉︎ しかも装備は現代科学で造れない高度なモノ⁉︎
イキナリ飛び出したトンデモない謎、事実。読者のアタマにガツーンと響く衝撃。私もしっかりとやられました(笑)。
そしてガニメデでは、大柄な体格の異星人と数百万年前に地球上で生息していた生物たちの遺骸(いがい)が…。
チャーリーの所持品には手帳もあった。これも透過撮影装置でスキャン。言語学者らと協力して解読する。手帳には月面で展開された戦争の様子が描かれていた。チャーリーは月面に配属された軍人。激しい戦闘に参加していた。一方で、月から見える〝地球〟でも戦闘が行われ、月面から放たれた兵器が都市を壊滅させる凄惨な状況も記されていた。
5万年前の地球では、氷河期をアフリカ南端で生き延びたホモ・サピエンス(現生人類)が各地へ歩いて移動を始めた時期。
「グレートジャーニー」中のご先祖さまに、地球から月へ行く技術なんかありません…。
★古代文明論の先駆け
アタマが混乱してしまう事実の数々。ハントらは困惑しつつも事実のピースをつないで推察を重ね、真実に迫っていく。
その答えが「星を継ぐもの」や続編「ガニメデの優しい巨人」で明かされます。ここから先は作品をお読みください。
ここでは作品を楽しむためのヒントになりそうな「トンデモ説」を少し紹介します。
【月宇宙船説】本来の月は地球の衛星ではなく、よそからやって来て地球の引力に捕まった。人工的で異星人の船という説。
【第5惑星説】火星と木星の間には小惑星帯がある。小惑星群はかつて存在した太陽系5番目の惑星の残骸。
【異星人来訪説】はるか古代の地球に異星人が来訪。原始人類の進化をうながし、知識や文明をさずけた。
いずれも都市伝説やトンデモ説として有名。ただ、小惑星群は木星の強大な重力で破壊された微惑星という説が有力です。
でも、これらの説は「星を継ぐもの」以下3部作で展開される要素。実は「トンデモ説」の先駆け的な作品なんです。
「星を継ぐもの」を含めた「巨人3部作」は、日本でマンガ化され大人気になりました。
描き手はSF・伝奇マンガの第一人者、星野之宣さん。「ビッグコミック」で2011年5号から2012年16号まで連載。
「星を継ぐもの」のタイトルで3部作のストーリーが展開され、コミックスは全4巻が発売されています。
原作のトンデモない謎&ストーリーと、星野さんのクールなタッチがめちゃマッチ。2013年星雲賞コミック部門を受賞。
私の「星を継ぐもの」との出会いは星野さんのマンガ版でした。衝撃的な謎にガツンとやられてハマりました。
でも雑誌が発売されるのは1週間ごと。「早く続きを知りたい」と心がはやって原作を購入。まさにトリコになりました。
原作を読み進め、雑誌でストーリーを確認するカッコウ。3部作とマンガ版を読み終えた後は、作品の世界観にドップリ。
原作とマンガ版を合わせて読めば、作品の世界観が完全に分かって深〜く楽しめるんです。
2.「火星の人」
さらに2014年に大手から再出版され、ウィアーさんにとって商業デビュー作となりました。
日本でも翻訳版が2014年に発売され、大人気。2015年の第46回星雲賞の海外長編部門を受賞しています。
人類が探求や開発を目指している火星が舞台。現実に先駆けた作品で、ドキドキワクワクするストーリーが展開します。
★あらすじ
ワトニーは火星の有人探査計画「アレス3」に植物学のクルーとして参加。5人のクルーたちと火星に降り立つ。ミッション6日目、クルーは大砂嵐に襲われた。生命の危険がある状況で任務の放棄を決定。火星からの退避も決まる。通信用パラボラアンテナが直撃したワトニーが吹き飛ばされる。彼が死んだと思ったクルーはロケットで火星を脱出した。ワトニーは体にアンテナの軸が刺さったが生きていた。居住区へ戻り治療をしたが、自分が1人取り残されたことに気づく。未知の惑星で1人。頼る仲間はいない。それでもワトニーは、残された物資をやりくりして生き延びようと奮闘する。
日本のJAXA(宇宙航空研究開発機構)も火星の衛星フォボスとダイモスを目指す探査機を2024年に打ち上げる計画を推進中。
現実でも進んでいるプロジェクトにともなうリスク。そして、その克服が「火星の人」のテーマになっているんです。
空気の薄い大気と水はなく赤い大地の惑星に1人。食料は事前に輸送され、31日を予定していたミッション分だけ。仲間のクルーたちは火星から離れ戻ってこない。地球から次のミッション「アレス4」のクルーが来るのは4年後。
植物学者とメカニック・エンジニアとしての知識とスキルをフル回転させて、冷静に着々とサバイバルする。
ワトニーはハブ(居住基地)に残された食料や水など備蓄品をチェック。電源や水再生器など生命維持機器の無事も確認。栄養のある備蓄食料が6名のクルー1人あたり50日分あること。ワトニー1人なら300日分あることを確認。さらに行動に必要なカロリーを摂取するため、ジャガイモを栽培することを決意する。
ハブ内や移動用のローバーを栽培ハウスとして使用。水分のない火星の土を運び入れ、実験用の地球の土をふりかける。クルーが残したものと自分が出して乾燥保存していた大便も土にふりかける。さらに火星から上昇して離脱するためのロケットの燃料などを化学反応させて水をつくり〝イモ畑〟にまく。
さらに宇宙空間に捨てる予定だった乾燥大便を肥料に使用(ニオイがスゴい!)。土にふりかけて水も巻いてなじませる。
特製の土ではバクテリアが精力的に活動しジャガイモも収穫。ワトニーはディナーで舌鼓をうつんです(途中であきるけど)。
 |
| 赤い大地に取り残されてもあきらめない! |
★一人称で科学的要素を分かりやすく説明
ここまで説明してきたワトニーのサバイバル計画と実践の模様は、彼の問わず語り、一人称で描かれています。
ミッションでのログ(行動日誌)に書き込む形でストーリーが進行します。
栽培に必要な土や水の量の計算方法も説明するんですが、ワトニーが自分を鼓舞するため軽妙に語っているので分かりやすい。
栽培するためのバクテリアの必要性など、教科書で読んだらスルーしそうな内容がスルスル頭に入ってくるんです。
一方で、地球上のNASAなどの登場人物たちや状況は三人称で描写されています。
「孤独な火星」と「悲しみの地球」のメリハリが効いて、ストーリーが読みやすいんです。
★映画のリアル感タップリな映像が相乗効果に
ワトニーの「生き延びるんだ」という闘志と行動はムダではありませんでした。
ローバーが移動していたり、上昇用宇宙船から燃料器具が外されていることをNASAが発見。
ワトニーが生きていることに気づき、人類初の火星からの救出ミッションが始まるんです。
この続きはぜひ作品をご覧になってほしいんですが、映像もメチャおもしろい!
作品は「オデッセイ」というタイトルで2015年に米ハリウッドが映画化。
リドリー・スコット監督がメガホンを取り、名優のマット・デイモンさんがワトニー役を演じて大ヒット。
火星でのワトニーの孤独にくじけない奮闘ぶり。赤い大地からの救出劇はリアルさとド迫力が最高です。
原作で脳内にインプットされたストーリーのイメージを映画で再確認。原作と映像のギャップも楽しめる。
「火星の人」は原作と映画の相乗効果が楽しめる作品なんです。
3.「横浜駅SF」
「横浜駅SF」は2015年、小説投稿サイト「カクヨム」などで連載されました。
2016年に第1回カクヨムWeb小説コンテストのSF部門で大賞を受賞。作品が書籍化され、柞刈さんのデビュー作となりました。
作品の舞台は近未来の日本。長く続いた〝冬戦争〟で荒れ果てた本州を「横浜駅」が増殖して覆い尽くしているー。
ディストピアの支配者が「横浜駅」という設定。実際の横浜駅でずっと改修工事が続いていることから着想したそうです。
特徴は、オリジナリティーが強い独特な世界観が素晴らしくておもしろいこと!
ストーリーで登場する機械などの名前が、JR関係のモノから命名されているのも親近感と不気味なリアリティーを与えてくれます。
★あらすじ
主人公は三島ヒロト。横浜駅の〝エキソト〟で生まれ育った青年。
世界各国を巻き込んだ冬戦争から200年後の日本。本州は増殖した横浜駅によって覆われていた。四国も横浜駅の侵入を許し増殖が始まっていた。一方でJR北日本が統治する北海道、JR福岡の九州が横浜駅の侵食に抵抗していた。ヒロトは横浜駅のエキソト、三浦半島の岬にある村「九十九段下」で暮らす青年。横浜駅からの人類の解放を目指す「キセル同盟」の東山から、ヒロトは横浜駅に5日間だけ入れる「18きっぷ」をもらう。東山は横浜駅の中で孤立する「キセル同盟」のリーダーの救出をヒロトに託し、絶命。ヒロトは横浜駅に入ることを決意。かつてエキナカのラボで研究をしていたという「教授」にいとまごいする。教授はヒロトに「42番出口へいけ」と告げる。教授の「42番出口に全ての答えがある」との言葉を胸に、ヒロトは横浜駅の入口につながるエスカレーターを駆け上がる。
★人工知能が人間を統治する世界
横浜駅を増殖させるきっかけをつくったのは、冬戦争時代に生まれ人間を統治したJR(Japan Ruler)が開発した人工知能「統合知性体」。
日本中の鉄道駅(ノード)に人工知能を攻撃から守るため分散設置しネットワークを形成。戦闘で破壊されたノードは人が修復していました。
テストで導入された横浜駅が暴走的に増殖。統合知性体を凌駕(りょうが)して本州の99%を覆いつくしてしまう。人間は基本的に横浜駅のエキナカで生活。6歳になると管理用チップ「Suika」を脳に埋め込まれる。ただ埋め込むにはデポジット(保証金)が必要。払えないとエキソトに追放。「九十九段下」は追放者たちの村の1つ。
そんな人類の解放を目的にするのがキセル同盟。横浜駅の侵食に対抗するのが、JRから分割民営化された北日本と福岡なんです。
 |
| 横浜駅が日本列島を覆い尽くしていく |
★身近なJRとグッズがSF化した不気味さ
JRは通勤・通学などで利用する社会には必須のインフラ。毎日利用するので身近な存在です。
そして全国を走る鉄道網は、まさにネットワーク。作品では各駅に分散した人工知能が人間を統治していた。不気味な世界です。
JR東日本の「Suica」はICカード乗車券ですが、電子マネーでの決済もできる。スマホでもアプリをインストールして使える。
「横浜駅SF」の「Suika」はチップを脳内に移植。電子マネーで決済ができる一方で、個人データも記録されている。
これってリアルに実現可能なこと。個人データを入れたマイクロチップを体に埋め込んでいる人、もういますから…。
チップがないと拘束される。駅の設備や人に危害を与えても捕まる。拘束された場所に近い出口から廃棄される。「横浜駅長野口」といった出口があちこちにある。山の中や村がないところもある。捨てられる場所によっては飢え死にする可能性がある。エキナカの人たちも格差社会に苦しんでいる。金のない人にチップを埋め込み、保証金の肩代わりに働かせる悪質業者もいる。
そして「教授」から告げられた「42番出口」を目指し、危険な「青春18きっぷ」の旅をするんです。
ヒロトはJR北日本の工作用アンドロイドやキセル同盟のリーダー・二条ケイハのアシストを受けて、エキナカの世界で奮闘。
自動改札や職員の追跡を振り切って「42番出口」に到着。「全ての答えがある」場所である〝人物〟と再会し、重大決断を迫られます。
ハラハラドキドキのストーリーは、ぜひ原作に合わせてマンガ版もお読みになることをオススメします。
マンガ版は2016年12月から2018年10月まで「ヤングエースUP」で連載。新川権兵衛さんの作画で、コミックスは全3巻。
コミカライズにあたって分かりやすくするため設定や用語の一部で変更がありますが、原作の世界観をしっかりと継承。
不気味なディストピア世界での冒険ストーリーのイメージがバッチリできて、メチャ楽しめる作品です。
まとめ・読み終わればSFが好きになっている
ここまでオススメのSF小説3作品について紹介・解説してきました。
- 「星を継ぐもの」(著者、ジェイムズ・P・ホーガン)
- 「火星の人」(著者、アンディ・ウィアー)
- 「横浜駅SF」(著者、柞刈湯葉)
上記の3作品はいずれも、分かりやすくて読めば夢中になっちゃう名作ばかり。
- ストーリー冒頭で説明要素すら不要に感じる謎やテーマが飛び出して心に突き刺さる。
- 謎やテーマがおもしろすぎて、自分から説明要素を読みたくなる。
- サバイバル・冒険要素やヒューマンストーリーも展開して感情移入してしまう。
- いずれもマンガ化・映画化されていて、合わせて読むと作品の世界観が完全に理解できる。
以上の4つの特徴が魅力的なことがオススメする理由です。この記事を踏まえて作品を読めば、
「SF小説って、難しいですよね…」
「科学的な説明が多くて、とっつきにくい」
「難しい用語がたくさんあってイメージができない」
なんて読むのをためらっている人は、たちまちSF小説が大好きになっちゃう。他の名作にもチャレンジしたくなりますよ。
当ブログでは他にもおもしろい「SFマンガ」について紹介しています。ぜひ、ご覧ください。
谷風長道、コブラ、星野鉄郎…星の海をさすらう気分が楽しめる「宇宙の旅マンガ」名作3選
「大ダーク」シリアスなのに笑えるSFマンガが読みたい人にピッタリな3つの魅力
エヴァ、トランスヒューマニズム…伝奇マンガの名作「生物都市」が秘める3つの先駆性
「百億の昼と千億の夜」神学、宇宙論…難解なSFマンガを楽しみたい人にお勧め名作4つの魅力
この記事で紹介した3作品を「すぐ読みたい」という方はスマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。
「BOOK☆WALKER」などのブックストアなら無料で試し読みもできますよ。
読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」
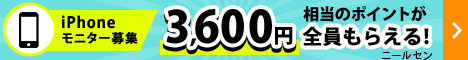

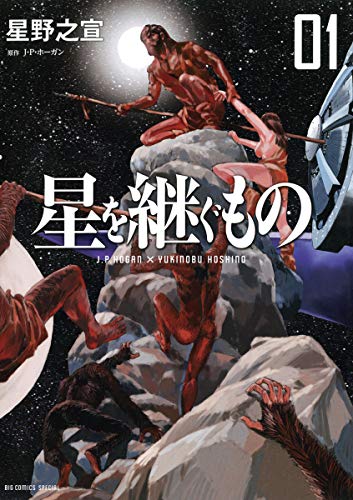

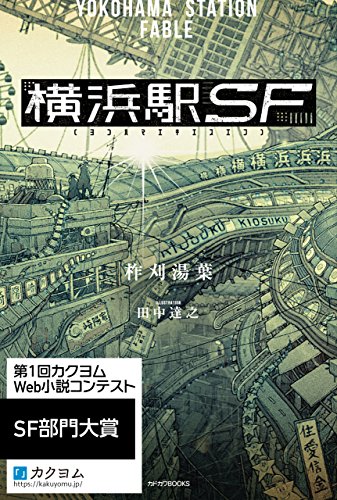
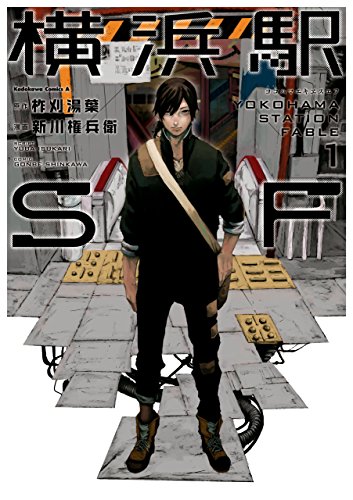





0 件のコメント:
コメントを投稿