 |
| 落語の高座はワンダーランドです |
「落語のことを知らなくても面白いの?」という方に読んでほしい
毎度バカバカしい、お笑いを一席〜♪
軽快で、心地いい口調で落語家さんが語る落語。日本が誇る伝統文化で素晴らしいエンターテイメントです。
滑稽噺(こっけいばなし)や人情噺。芝居噺や怪談噺 etc。古典落語は江戸庶民の生き生きとした姿や暮らしを教えてくれて、大笑いさせてくれます。
落語家さん自身も魅力たっぷり。新弟子時代の修行ぶりや、芸の道を極めようと奮闘する生きざま。まさに極上のヒューマンストーリー。
だから漫画でも人気のジャンル。お噺の演目がストーリーのベースになったり、落語家さんが主人公として活躍しています。
そんな「落語漫画」で大人気なのが「週刊少年ジャンプ」で連載中の「あかね噺」。
作品を読んだ人たちから「面白い!」「めちゃハマった!」なんて声がたくさん。本職の落語家さんたちからも評価が高い作品です。
ただ、まだ読んでいない方たちからは、
「落語のことを知らなくても、面白いのかな⁉︎」
「落語漫画って演目自体がストーリーになるのが多いけど、この作品はどんな感じなの?」
なんて声もたくさん上がっています。でも、心配はご無用!
「あかね噺」は本職の落語家さんの間でも高評価。読めば落語のことが分かってストーリーもメチャ面白いからです。
この記事では「あかね噺」が面白くて、大人気になっている秘密&魅力を考察。
- 落語家さんがバッチリ監修、落語の基本が分かりやすくて世界観がリアル。
- 落語の話芸で大切な憑依芸と気働きの描写が素晴らしい。
- あかねが噺を学ぶ姿が演目の内容や背景を分かりやすく教えてくれる。
- ジャンプの王道「バトル」要素がはじける「可楽杯」が熱すぎる。
この記事を読めばナットク&マンゾク。「あかね噺」が持っている魅力が分かって、作品のページを開きたくなりますよ。
「あかね噺」って、どんな作品なの?
「週刊少年ジャンプ」で2022年11号から連載中。コミックスは計14巻が発売中(2024年11月23日時点)。
作品は、落語家を目指す主人公の奮闘する姿が共感を呼んで大人気。
2022年8月に発表された「次にくるマンガ大賞2022」のコミックス部門で第3位にランクイン。
★主な登場人物とあらすじ
主人公は桜咲朱音(おうさき・あかね)。落語家を目指す17歳の女子高生。落語家の父の背中を見て育ったヒロインです。
父の徹は高座で「阿良川志ん太」を名乗る「二つ目」でした。気負いすぎの面があるけど演技力がバツグン。
志ん太は阿良川流の真打ち昇進試験のため稽古に励む。支えてくれる妻・真幸、あかねのために昇進したかった。昇進試験では古典の「芝浜」を披露。持ち味の演技力を発揮して会場をわかせた。だが結果発表で、一門トップで審査委員長の阿良川一生に受験者全員が破門されてしまう。父は転職したが、あかねは納得できない。自分が落語家になって父の無念を晴らし、父の落語を認めさせようと誓った。
1.落語家がバッチリ監修、落語の基本が分かりやすくて世界観がリアル
 |
| 落語家の生きざまは王道路線にピッタリ |
★読むだけで落語の知識が入ってくる
「あかね噺」は林家木久扇さん一門の林家けい木さんが、作品の監修を務めています。
けい木さんは「二つ目」(後述)で新鋭の落語家さん。ストーリーに登場する演目や落語界についてアドバイスされています。
また落語界でも注目度が高くて、笑福亭鉄瓶さん、三遊亭王楽さん、月亭八光さんら若手噺家さんの愛読者が多い。
それぞれYouTubeで「あかね噺読んでみた」といったレビュー動画を投稿。「面白い!」とお墨付きを与えているほど。
作品では落語の演目や落語界の基本的な知識がたくさん登場。とても分かりやすくて読んでいるうちに自然とアタマの中に入っている感じ。
ストーリーの舞台となる寄席や落語喫茶の雰囲気や空気感も、見事に再現されている。
だから落語をよく知らない人でも、ストーリーにハマって楽しめるんです。
★落語界の厳しい階級制度
あかねは父の師匠で、人情噺では落語界随一といわれる阿良川志ぐまに弟子入り。小学生のころ、父の無念を晴らしたいと志ぐまに直談判。それから6年間、師匠の自宅やカラオケ店でマンツーマン指導を受けていた。そして17歳のある日、「高校を卒業したら」という条件付きで弟子入りを認めてもらえた。
あかねにとって、最初に挑む壁が落語界に存在する階級制度です。
作品がベースにしている落語芸術協会では4階級(東京)が定められています。
【前座見習い】落語家として落語協会には登録されず、許可がなければ高座に上がれない。師匠のお使いや兄弟子たちのカバン持ちをしたり。
着物のたたみ方やお茶の出し方、鳴り物や演目の稽古。前座になるための修行を重ね、師匠に認められれば前座に昇進できる。
【前座】寄席などで最初に高座へ上がる。着流しの着物しか着れない。寄席では噺以外にも雑用などの仕事を毎日こなす。これが4年ほど続く。
【二つ目】落語家として登録され、寄席で二番目に高座へ上がる。高座以外は寄席に来なくていい。雑用はなく着物も紋付、羽織と袴がつけられる。
ただ高座数が減るので、自分で「落語喫茶」などの仕事を探す。二つ目を約10年続けると真打ち昇進試験を受けられる。
【真打ち】寄席で最後に高座へ上がる資格がある。弟子を取って後進を育てることができる。
プロ野球で例えると、見習い&前座は育成枠。二つ目は2軍。真打ちは1軍といった感じ。
師匠ともなると、スター選手やメジャーリーガーというところ。
あかねは「見習い」からスタート。着流し姿で雑用をこなし、許可がもらえたら高座に「あかね」の名で上がります。
見習い&前座さんは寄席に毎日通勤。休みは月の「31日」だけ。高座料はもらえないけどお小遣いがいただける。
師匠&兄弟子と寄席の雑用、噺の稽古がほぼ毎日。でも兄弟子や仲間と友情を育み、努力を重ねて一歩一歩階段を上がっていくんです。
★師弟制度だけに理不尽な仕打ちも
 |
| 落語家さんが高座に上がるのが待ち遠しい |
落語の世界は独特な、師弟の世界です。労働基準法などの法律に守ってもらえない。手厳しい折檻(せっかん)やクビもある。
志ん太は真打ち昇進試験に挑む。緊張と重圧から噺のマクラ(導入部)で早口になったりパニック寸前に陥る。客席からあかねのクシャミが聞こえ平常心を取り戻す。持ち前の演技力で「芝浜」を見事に語り切り大歓声を浴びる。だが審査発表で阿良川流トップの一生が「一門の面汚し共が、みっともねえ芸を見せた」。出場者全員を破門にした。
なぜ破門に⁉︎ 一生は理由を語っていないけど「志ん太の噺は芝浜とはいわない」。それだけつぶやきます。
理由を説明せず破門とはヒドイ話。でも落語界で実際にあった話なんです。
★立川談志さんの「5人破門」騒動
破天荒ぶりが伝説になっている故・立川談志さん。昭和〜平成の落語界で幅広い芸を披露した実力者でした。
落語協会から脱会して「落語立川流」を創設した気骨の人でもあります。その談志さんが2002年に大騒動を起こしました。
「二つ目への昇進意欲が感じられない」という理由で前座5人のお弟子さんたちを破門にしたんです。
作品での一生の破門騒動は、談志さんの「5人破門」がモデルのようです。
ただ談志さんは2003年に破門5人の復帰試験を実施。突き放して奮起をうながす、弟子思いの人情家でした。
一方、一生の真意は? ストーリーの進行とともに明かされるのか、ナゾ要素として注目ポイントです。
そして一生の破門騒動は、あかねが落語家を目指すきっかけ。ストーリーの発端となっている設定が心憎いかぎりです。
2.落語の話芸で大切な憑依芸と気働きの描写が素晴らしい
落語家さんの特徴といえば、高座で噛んだりすることなく、よどみなくしゃべり続ける話芸。
スラスラとテンポよく、流れるような語り口。ホント、スゴいです!
さらに登場人物になりきる演技力と表現力。これが加わることで、客席で聴いている人たちは登場人物が落語家さんに重なるように見えてくる。
登場人物が憑依したみたいな感じ。まさに憑依芸です。
今のお笑い界で、〝異常な人たち〟を演じる友近さんやゆりあんレトリィバァさんらが「憑依芸人」と呼ばれ大人気です。
この「憑依芸」、日本の芸能文化の伝統といえるんです。
例えば、歌舞伎と能・狂言。いずれも役者らがストーリーの登場人物を演じます。
その姿は、幽玄で幻想的。まるで登場人物が憑依したような雰囲気が漂う。
あかねが落語を好きになった理由は、父が演じる噺が大好きだったから。一人で喋ってるだけなのに、聞いてたら色んな人や景色が見える。魔法みたいに。
そして一人一人を演じ切るために、落語家は自分の表情や声色、指など体を使った仕草で登場人物たちを表現する。
父・志ん太は登場人物が憑依したかのような表現力・演技力がバツグンに上手。
父が高座や自宅で稽古する姿をみて、あかねも表現力を学び、演技力を身につけたんです。
★父譲りの憑依芸で道を開く
17歳になったあかねが正式に弟子入りをお願いした際、志ぐま師匠が〝試験〟を科します。「落語喫茶」での助っ人です。
連絡を受けた志ぐまは「あかね、お前行ってこい」「一度プロ(落語家)の世界を見てこい」と高座に上がることを指示。「(上がって)それでも落語家になりたいんだったら考えてやらん事もない」あかねは「爆笑とって鼻明かしてやりますから、楽しみに待っててくださいよ」
あかねは初めて高座に上がり、大勢の客の視線にたじろぐ。でも「出し切れ、積み重ねてきたもの、私の中にあるものを」。演じたのは「まんじゅうこわい」。語り口、表情、仕草を駆使して登場人物を表現。憑依したような演技に客席は大爆笑。落語喫茶のおかみさんは、あかねの演技に驚くと同時に「懐かしさ」を感じる。そして志ん太の娘だと気づく。
仲間たちが男が寝てる間にまんじゅうを並べて怖がらせようとする。実は、男はまんじゅうが大好きで「怖い」と連呼しつつパクパク。
あかねの噺は、長屋の男たちがワイワイやっている姿が浮かび上がるほどの出来。客席は大ウケで大爆笑。
おかみさんは師匠に「すごかった」とメールを送る。あかねは父譲りの憑依芸でプロテストに合格するんです。
★話芸を支える「気働き」
 |
| あかねは「気働き」を学ぶため居酒屋へ |
兄弟子は「まいける」「こぐま」「亨二」「ぐりこ」。二つ目の4人。あかねの世話役は亨二が買って出ました。
あかねは兄弟子の営業などに同行。あいさつの仕方、着替えや着物のたたみ方、お茶の出し方など雑用を教わります。
「落語には無関係だと思うだろう? 落語家は目の前のお客さんを喜ばせる商売だ」「目の前の人、一人喜ばせられないヤツには務まらない」「相手が喜ぶ事を考え、先へ先へと気を回して動く。落語家はコレを〝気働き〟という」
古典の「子ほめ」で得意の演技力を披露。お客は噺をほめてくれたけど、ウケと反応はイマイチ。
兄弟子は常連として通っている居酒屋さんで1週間働いてみろ、と命じるんです。
★お客を喜ばすための極意
第七席「気働き」。あかねは接客についてネットで調べ、大きな声で「いらっしゃいませ!」。オススメの肴をグイグイ説明します。
「私、同じ事やっちゃってない?」「自分の覚えた事をただやるばっかで、目の前の人の事を考えてない」店長は気働きについて「落語家から学んだ」とあかねに語りかける。見にいった寄席で、志ぐま師匠が笑いも涙もこっちが欲しいタイミングにどんぴしゃで入れてくる。店長は料理を出すタイミングを工夫したり、お客さんに合わせて接客を変えたりといろいろ試してみた。
亨二兄さんに同行した老人ホームの慰問会で、あかねは見違えるような噺ぶりを披露。お年寄りたちを喜ばせます。
得意の演技力だけを全開で披露しても自分勝手なだけ。お客は置いてけぼり。だからお客への「気働き」が大切なんですね。
あかねが気働きを駆使してお年寄りたちに披露した高座。語り、テンポ、間合い、客席の空気を読む力が加わり、話芸はバージョンアップ。
メチャ見事で感動します。ぜひ作品でご覧ください。
3.あかねが噺を学ぶ姿が演目の内容や背景を分かりやすく教えてくれる
「あかね噺」では登場人物たちによって、たくさんの名作・古典落語が演じられています。
【芝浜】腕はいいが貧乏暮らしの魚屋が浜辺で大金を拾う。働かなくなった亭主の目を覚まさせるために女房が機転をきかす。
【子ほめ】八五郎にタダ酒をねだられたご隠居さん。「ごちそうになるならお世辞の一つも言えるようになれ」と教えるが…。
【転失気】体調が悪い和尚さんが医者に「てんしき」はあるか聞かれる。意味が分からず小僧に借りてこいと命じるが…。
【三方一両損】財布を拾った佐官が持ち主の大工に返しにいったが、江戸っ子気質で突き返される。奉行所で大岡越前が名裁きを見せる。
他にも有名な古典噺を登場する落語家さんたちが名演。
熱演する描写は臨場感と迫力があって引き込まれる。演目の内容や面白さもアタマの中に入ってくる。これが作品の魅力の1つでもあります。
あかねも持ち前の話芸&憑依芸と身につけた気働きを使って高座に上がり、芸を披露。実力をつけていきます。
成長いちじるしい弟子に、志ぐま師匠が再び課題を与えます。
★名古典だけどプロもあまり演じない「寿限無」
学校の進路相談で、あかねは落語家になるという進路志望書を提出。先生に自分の高座を見てもらい納得してもらえました。
そして先生から学生たちの〝落語の甲子園〟「可楽杯」への出場を勧められます。
大会の審査委員長は因縁の相手、阿良川一生。あかねは出場を決意します。
兄弟子のぐりこには「アマの大会に出るのは、入門を許した師匠への不義理になる」とたしなめられる。「可楽杯」の優勝者への特典は一生との「歓談」。あかねは優勝して一生に「なんでおっ父を破門にしたのか」と聞くつもり。志ぐまは「出たらいいんじゃないか」。師匠は言い出したらきかない弟子の性分を「止めてもムダ」と尊重した。
「寿限無」は誰もが一度は耳にしたことがある古典中の古典噺。
「寿限無、寿限無、五劫のすり切れ、海砂利水魚の水行末、雲来末、風来末〜」
子どもの名前を呼んでいるうちに、名前が長すぎて相手がいなくなっていた…。
そんなオチと、決まり文句の超長い名前を繰り返すことが面白い演目。
でも「寿限無」、高座で笑いを取るのはスゴく難しい噺だそうです。
寄席ではお客の多くが落語ファン。当然「寿限無」も知っている。さらに大会では出場者もお客も〝落研〟の人ばかり。
みんなが知っているからこそ、笑いを取るのが難しい。落語家さんでも高座で演じるのは避けるほどの噺なんです。
★「寿限無」を課題にした真意は?
 |
| 寿限無には子を思う親心があふれている |
志ぐま師匠はなぜ、あかねに「寿限無」だけで「可楽杯」で勝てと課題を出したのか? 真意はなんなのか?
兄弟子ぐりこは、その上の兄弟子のこぐまに相談しようとあかねに提案します。
こぐまは元東大生。落研出身の理論派。噺の背景にある時代・社会状況や文化・風俗を深掘りして調べまくる人。
こぐまは公園のベンチで「寿限無」をあかねに演じさせる。あかねは切れのある言い立てで「寿限無」を話し切るが、こぐまは「君の言い立ては音だね。言葉に成っていない」。さらに「君は噺に興味がないの? 深く知りたいと思わないの?」と問いかける。
あかねは兄弟子の助言を受けて、江戸時代の社会状況や風俗の勉強をスタート。学校で先生に江戸時代に関する本を紹介してもらい、読みふける。そして、あかねは「寿限無」のキモに気づく。
でも、あかねが気づいた「キモ」は「言い立て」の速さじゃない。呼び切るのに苦労するほど長い名前をつけた「親心」でした。
江戸時代の平均寿命は30〜40歳前後。子どもが亡くなる率も高かった。そのため名前には長寿への思いを込めていた。
あかねは筋がいい分、役の心情に寄り添う意識が抜け落ちている。役の理解度が浅くても、それなりにこなせてしまう。でも人の心は動かせない。登場人物がなにを考えているか、その人になり切って考える。役の了見を学んでほしかった。
「少年ジャンプ」といえば、ヒット要因の三原則「友情・努力・勝利」をベースとした作品をたくさん発表してきました。
バトルもの、スポーツもの、冒険ものなど「王道路線」と呼ばれる作品を数多くヒットさせています。
「あかね噺」も王道路線を継承した作品。バトル要素にあふれ、あかねが「友情・努力・勝利」を重ねて壁を乗り越え、成長していく。
そして、バトルの最初の舞台が「可楽杯」なんです。
★学生の大会を右ストレート一本で勝つ
「可楽杯」は書類審査→一次予選→決勝と進む落語の学生選手権大会。
書類審査をパスしたあかねが臨んだ一次予選には、30人が出場。
優勝候補は2年連続で大会を連覇している練磨家からし。演技力で高い評価を受けている声優の高良木ひかる。
そうそうたるメンバーの中で、あかねは「寿限無」を披露。まずは切れとテンポがバツグンの言い立てを披露して一次予選を突破します。
優勝候補の2人も勝ち抜き、決勝に進出。あかねを含めた三つどもえの戦い。
3人はそれぞれの実力を認めながら意識しあって、バチバチと火花を散らします。
そして8人による決勝。からしは「転失気」を現代風にアレンジした改作落語。ひかるは演技力を全開した「芝浜」を披露。
2人は、それぞれ持ち味を発揮。会場の客席を大熱狂させます。
★圧倒的なアウェーに立ち向かう
からしとひかるの熱演で、客席はホットな状態。そして「優勝は2人のどちらか」。そんな空気に支配されている。
「もう、おなかいっぱいだな」なんて雰囲気も漂う中、あかねが演じるのは大会2度目の「寿限無」。
他の出場者が取っておきのネタで決勝に挑むことができる。一方で、あかねはボクシングでいうと右ストレート一本で戦わなきゃいけない。
まさに圧倒的なアウェー&不利な状況。あかねはどう立ち向かうのか?
続きは作品で楽しんでいただきたいですが、あかねの噺ぶりはホント、圧巻。
からしとひかるの噺でわき上がった疲れ気味な観客へ、居酒屋でマスターした気働きを駆使してアプローチ。
語る「寿限無」は江戸時代の関係書を読んで、理解度を深めている。
さらに大会までに学んだ経験を生かし、持ち前の憑依芸を披露するあかねの姿はステキで感動しますよ。
まとめ・ストーリー自体が魅力たっぷりの人情噺です
 |
| 寄席の前に来るだけでワクワクしてきます |
ここまで「あかね噺」が面白くて、大人気になっている秘密&魅力を考察。
- 落語家さんがバッチリ監修、落語の基本が分かりやすくて世界観がリアル。
- 落語の面白さである話芸&憑依芸と気働きの描写が素晴らしい。
- あかねが噺を学ぶ姿が演目の内容や背景を分かりやすく教えてくれる。
- ジャンプの王道「バトル」要素がはじける「可楽杯」が熱すぎる。
「あかね噺」は本職の落語家さんの間でも高評価。読めば落語のことが分かってストーリーもメチャ面白くて魅力に溢れています。だから、
「落語漫画って演目自体がストーリーになるのが多いけど、この作品はどんな感じなの?」
なんて人は、ぜひ作品のページを開いてみてください。ストーリーにハマって続きを読みたくなりますよ。
作品のストーリー自体がステキな人情噺。ワタシはいい年のオッサンですが目頭をぬぐっています。
日本が誇る文化である落語がテーマの「あかね噺」。多くの方に読んでいただきたいと思います。
当ブログでは、ほかにもおもしろい漫画を紹介しています。ぜひご覧ください。
「んなアホな!」シュールでナンセンスすぎるギャグを楽しみたい人にお勧めする3つの魅力
「嗚呼!!花の応援団」男くさくて下品だけどホロリと泣ける「伝説のギャグ名作」3つの異彩
「がきデカ」少年警察官こまわり君が大ブームを巻き起こした変態ギャグと〝その後〟を楽しもう
「あかね噺」をすぐに読みたいという方は、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。
「BOOK☆WALKER」などのマンガストアなら無料で試し読みもできますよ。
読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」
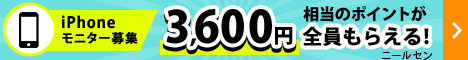


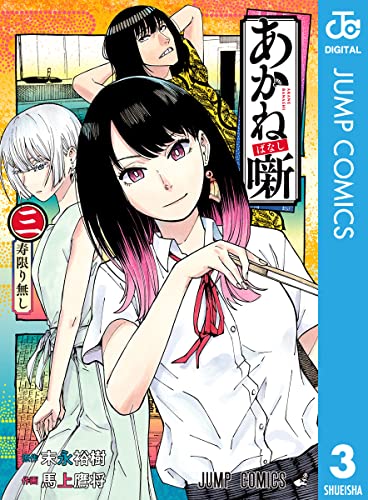
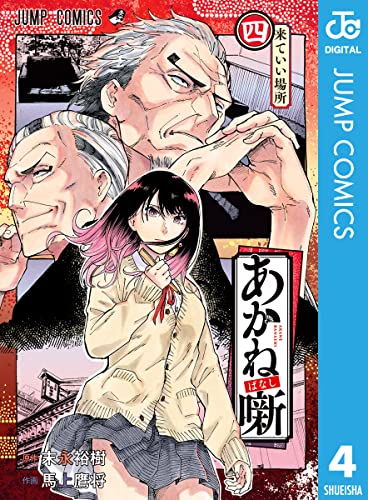





0 件のコメント:
コメントを投稿