「寄生獣」「ヒストリエ」に負けない魅力あふれる作品たち
代表作「寄生獣」。「月刊アフタヌーン」で連載中の「ヒストリエ」。
これまで世に送り出した作品は、独特の世界観と岩明さん自身の人生哲学などが反映され、ファンから高い人気と支持を獲得しています。
岩明さんは、押しも押されもせぬ大作家。それだけに、
「ほかの作品も読んでみたい!オススメはなんですか?」
「岩明さんの作品で一番好きなものはなんですか?」
なんて声がものすごく多いんです。
この記事では「寄生獣」「ヒストリエ」以外の、岩明さんの数多くの作品からオススメをチョイス。
- 「七夕の国」(掲載誌ビッグコミックスピリッツ)
- 「骨の音」(デビュー作などを集めた短編集)
- 「風子のいる店」(掲載誌コミックモーニング)
以上の3作品について紹介、解説します。
お読みになれば3作品の魅力とおもしろさがナットク。岩明さんの作風と特徴がわかって
作品のページを開きたくなります。
読めばうなってしまうほど深くて、感動させてくれる〝岩明ワールド〟にハマりますよ。
岩明均さんと3作品をチョイスした理由について
 |
| 岩明作品のメッセージ性は読者をトリコにする |
★岩明均さんについて
本名は岩城均(いわきひとし)さん。東京都出身。
学生時代には大学教授だったお父さんの著書のさし絵を描かれていたそうです。
マンガ家の上村一夫さんのアシスタントを務め、1985年のちばてつや賞に応募した「ゴミの海」が入選。
「ゴミの海」が「モーニングオープン増刊」に掲載されプロデビューしました。
代表作はなんといっても「寄生獣」。
謎の寄生生物と共生することになった高校生・泉新一の壮絶な闘いを描くストーリー。
続編「寄生獣 リバーシ」など続編やアンソロジー作品も多数。アニメ化、実写映画化もされ大人気になりました。
そして現在「月刊アフタヌーン」で連載中の「ヒストリエ」。
古代ギリシアの征服王・アレクサンドロス大王の書記官や軍指揮官を務めた実在の人物、エウメネスの波乱の生涯を描いています。
第14回文化庁メディア芸術祭マンガ部門の大賞、第16回手塚治虫文化賞のマンガ大賞を受賞しています。
★3作品を選んだ理由
「寄生獣」は、謎の生物にパラサイトされた人の頭がパッカリ分かれて刀状の武器になるなど衝撃的なシーンが特徴。
人を攻撃する際の無機質な表情はメチャ不気味。
犠牲者の顔も無表情。自分が襲われ命を落とすことに気がついていないことがわかる描写力。
ものスゴいリアリティーと説得力。グロい表現なのに読むとトリコになっちゃう。
岩明さんの作風は、独創的なアイデアがたっぷり。ストーリー構成がバツグンで哲学的なメッセージ性も感じます。
これに淡々とした絵がマッチして、メチャおもしろい。
- 「七夕の国」(掲載誌ビッグコミックスピリッツ)
- 「骨の音」(デビュー作などを集めた短編集)
- 「風子のいる店」(掲載誌コミックモーニング)
上記の3作品は「七夕の国」が「寄生獣」後。「骨の音」「風子のいる店」が「寄生獣」の前に発表されたもの。
いずれも岩明さんの作風や特徴が早い段階であふれまくり、さらに発展&凝縮されている。
「寄生獣」や「ヒストリエ」と同じくらいおもしろくて、岩明ワールドの魅力がよくわかる。
これが3作品をチョイスした理由です。ここからは1作品ごとに紹介、解説していきます。
1.「七夕の国」
コミックスは全4巻。上下2巻の「完全版」も発売されています。
岩明さんの代表作となった「寄生獣」の後に連載。超能力、ミステリー、超文明論がおりまぜられた伝奇ホラー作品です。
★あらすじ
主人公は大学4年生の南丸洋二。のんきな性格。「新技能開拓研究会」というサークルの部長。
南丸はある日、民俗学の丸神正美教授に呼び出され丸神教室を訪れる。丸神は東北地方の丸川町へ調査に出て行方不明。南丸は教室の講師らと交流するうちに丸神にも似た能力があると知る。南丸は丸神と同じ東北地方の豪族の血筋であり、現地には大きな穴のあいたヨロイなどがあることも知る。丸川町では殺人事件が発生。窓にはまるい大穴があき、遺体は頭が大きなスプーンのようなものでえぐられていた。丸川町は「丸神の里」と呼ばれた地。南丸は自分の力に関係があるのかを知るため教室のメンバーと現地へ向かう。
★異形のモノが放つ強烈な力
ストーリーは戦国時代の「丸神の里」からスタート。この里は最上、島寺という豪族の領地にはさまれた地でした。
丸神山は里の人たちが先祖の時代から守る聖地。島寺通康は反対した里出身の家臣・南丸忠頼を殺して脅し、築城を命じる。里長(さとおさ)の丸神正頼は拒絶。進撃する島寺軍3000人に正頼は自身を含めた精鋭10人で挑む。正頼らは強烈な光を発する不思議な力で島寺軍300人を一瞬で撃破。正頼は力で通康の顔半分を消し去る。
精鋭たちのヒタイや手の甲には、まるい宝石のようなものがポッコリ。
異様な姿、大軍を一瞬で倒す力。丸神の子孫の南丸も、力の使い方を覚えるとヒタイに血マメのようなものができてくる…。
★超能力+超文明論+人間観=大傑作
 |
| 「丸神の里」には守り続ける力と秘密があった |
文明をもたらしたモノは地球外から飛来し〝神〟となる。神は円すい状で頂上が開けた山に降りてくる。
「七夕の国」は超文明論が反映されていて、丸神山はピッタリの形状。
丸神山は「丸神の里」の人たちが先祖の時代から現代まで、「七夕祭り」として深夜に秘義を行ってきた聖地です。
先祖の時代から現代まで、里人の中から力が使える「手が届く」人が現れる。
さらに「窓の外を見る」。〝神〟の存在と意志を感じる力です。2つの力を持つ人が里長(殿様)となる。
里長は力を使うにつれて、前述した異様な姿に変わっていく。
そんなミステリアスな秘密を「丸神の里」は守り続けている。力をもたらしたモノへの恐怖を心に抱きながら。
でももたらしたモノは、数百年前に訪れた後はまったく丸神山に降りてこない。
〝神〟はどうしたのか。もう里にはやってこないのか。
そんなモヤモヤした気持ちを抱いたまま、今後も秘密と伝統を守り続ける意味があるのか。
そんな現代の里人の苦悩も描かれています。
あらすじで紹介した殺人事件。丸神山周辺を開発しようとした建築業者が死亡した事件です。
力を使うことは一族の生存のため必要だった戦国時代ならまだしも、現代で使えば殺人。社会的に制裁される行為。
現代のルールにマッチしない秘密を守り続ける意味があるのか。
超能力、超文明論に岩明さんの社会・人間観やメッセージがおりまぜられた、全28話のストーリー構成は秀逸。
「手が届く」「窓の外を見る」力の正体はなんなのか?
力を使うと姿が変わっていくのはなぜなのか。力をもたらしたモノは、ナニモノなのか?
里と力の秘密が明かされる一方で、南丸や里人たちが現代を生きるためどう選択するのか。
続きはぜひ「七夕の国」をお読みください。
2.「骨の音」
- 「ゴミの海」(1985年モーニングオープン増刊に掲載)
- 「未完」(1988年モーニングTHE OPENのA号に掲載)
- 「夢が殺す」(1988年モーニングTHE OPENのC号に掲載)
- 「指輪の日」(1989年モーニングTHE OPENのE号に掲載)
- 「和田山」(1989年モーニングTHE OPENのD号に掲載)
- 「骨の音」(1990年に描き下ろし)
以上6作品を収蔵。代表作「寄生獣」の連載スタート前後の作品がそろっています。
読み切り作品だけに岩明さんのストーリー構成力、ホラー要素、人間観、メッセージ性が凝縮されていておもしろいんです。
★「夢が殺す」
街では深夜に女性が襲われる通り魔殺人が繰り返されていた。大学生の原田はノイローゼ気味だった。原田は心配する彼女のマユミに相談。夢で自分が女性を殺害し、朝のニュースを見ると自分が手を下した女性だった、と。夢が繰り返され、原田は犯人が他人だと気づく。マユミは犯人が送信能力をもつ超能力者、原田は受信能力があると推測。マユミは深夜の街を歩いて探索、犯人に遭遇。その光景を夢でみている原田に「見える⁉︎あたしよ!」と訴える。翌朝にマユミの無惨な姿が発見され、原田は犯人を捕らえることを決意する。
「寄生獣」が大ブレークした理由がナットク。岩明ワールドが凝縮された作品です。
★「和田山」
東京の居酒屋で開かれた「大野台東高校」の同窓会。出席者たちは久しぶりに会う旧友との昔話に花を咲かせている。出席者たちは一人ずつ近況を報告。最後に上がった「和田山」の名前を聞くと会場内は恐怖と困惑の空気に包まれる。高校時代、クラスは和田山の影におびえていた。ふだんはおとなしいのに突然起き上がると襲いかかる。大きな体と強烈な腕力で押さえつけ、顔にマジックで落書きする。インクは洗っても落ちずヒドイ目にあっていた。恐怖の記憶から出席者たちは和田山を呼ばなかった。だが会場で悲鳴が上がり、顔に落書きされる被害者が出始めて…。
★人間が奥底に秘める狂気と心の闇
いずれの作品も、人間が心の奥底に秘める狂気。心の闇に支配される人の弱さがテーマ。
岩明さんの人間観がタップリ詰まっているんです。
「ゴミの海」は1985年のちばてつや賞に入選。そのままデビュー作品となりました。
サラリーマンの田村が、かつて自殺しようとした旅先で出会ったエリと再会。彼女がビルから飛び降りるミステリアスなストーリー。
タイトル作の「骨の音」は、彼氏に目の前で飛び込み自殺されたショックから家族が死んでも泣けなくなった女性の物語。
ヒロインの目には狂気があふれている。「寄生獣」でパラサイトされた人たちの無表情な顔に通じる不気味さがあるんです。
岩明ワールドが楽しめる傑作ぞろいの「骨の音」。ぜひお読みください。
3.「風子のいる店」
「コミックモーニング」で1985年23号から1988年27号まで掲載。
コミックスは全4巻。文庫版も全4巻が刊行されました。
岩明さんがちばてつや賞「ゴミの海」でデビューした1985年、読み切り作品で発表。
約1カ月のペースで作品が発表され、第7話からほぼ隔週で掲載されました。岩明さんにとって初の連載作品です。
★あらすじ
他人と話すとドモッてしまうので、高校では先生やクラスメートにバカにされている。気に病んで一時は自殺すら考える。今の状況から逃げ出したい。でも、内気な性格を直したい。風子は喫茶店「ロドス」でアルバイトを始める。「ロドス」ではいろんな出来事が起きたり、風変わりな客が訪れる。直面する風子は芯が強く、一人で解決しようと努力。「ロドス」でたくさんのことや人との関わりを経験し、風子は明るく前向きになっていく。
★登場キャラのセリフにあふれる人間観と哲学
ストーリーは、はっきりいって地味。「寄生獣」などほかの岩明さん作品とは違い、派手な展開はありません。
「ロドス」や学校で直面する風子の日常が中心。でも内気ながらがんばっている風子の姿がいじらしくて応援したくなる。
そして、登場キャラのセリフが深い。読んでいて考えさせられるんです。
風子はアルバイトを始めたころ、お会計の金額や「ありがとうございました」という言葉もあわててしまってしっかりといえない。
オドオド、キョロキョロして不安げな顔ばかり見せていました。
接客したオジサンからは「おまえは半人前だ」と怒られちゃう。
「『一人前の人間』なんて、誰が決めるんだ」「世の中が『標準』の速さで歩いてる。だから、足の弱い者はわきにどいてろって言うのか…?」
登場キャラのセリフには岩明さんの人間観や人生哲学があふれています。
マンガを読む読者は若い人が多いと思いますが、自分の人生を考え始めている世代にはスゴく響くセリフが多いんです。
★風子を見守る人たちの暖かさ
ストーリーでは風子を見守る人たちが登場しますが、みんなウツワが大きくて暖かい。
「ロゴス」のマスター、西崎信夫。元ラガーマンでごっつい人。風子が失敗しても優しくしっかり注意する人。
同僚がオドオドして失敗ばかりしていると、周囲はイライラしがち。でも、そんな姿は少しも見せない人。だから信頼できる。
風子の後に「ロゴス」のウエイトレスになった女子大生のみさ子。体が大きくてごっつい女性。
いつもニコニコして、なにごとにも動じない。小さいころはイジメられっ子だったけど、体を鍛えて心も強くなった人。
いじめや人間関係に悩む風子や友だちには、自分が乗り越えてきた経験や考え方を優しくアドバイスしてくれる。
わかりやすくて読者も「よし、がんばってみよう」と思わせてくれる説得力がある。
ストーリーは風子の日常を地味に丁寧に描写。だから現実味があって読者のハートに響く。
デビュー直後の初連載作品なのに、ストーリーの構成力とキャラ設定の完成度がすばらしい。
人が生きるためには、他人との関わりがホントに大事なんだなと改めて考えさせてくれる作品なんです。
まとめ・ドラマチックな展開と人間観&哲学が楽しめる
 |
| 3作品を読むことで岩明ワールドの魅力が広がります |
ここまで3作品について紹介、解説してきました。
- 「七夕の国」(掲載誌ビッグコミックスピリッツ)
- 「骨の音」(デビュー作などを集めた短編集)
- 「風子のいる店」(掲載誌コミックモーニング)
いずれも岩明さんの作品の特徴であるストーリーの構成力、ドラマチックな展開力、メッセージ性にあふれた作品です。
岩明ワールドのファンからは、代表作「寄生獣」などに比べて「評価が低すぎる」という声があるほど。
「寄生獣以外の作品も読んでみたい!オススメはなんですか?」
「岩明さんの作品で一番好きなものはなんですか?」
そう悩んでいる方は、ぜひ3作品を読んでみてください。絶対にマンゾク、ナットク。
岩明さんの作品の魅力にハマって、もっと岩明ワールドを楽しみたくなりますよ。
当ブログではほかにもおもしろい「ヒューマンストーリーマンガ」を紹介しています。ぜひ、ごらんください。
「ダーウィン事変」ヒューマンジーの怖すぎる「現実感」「秘密」「陰謀論」3つの魅力を考察
この記事で紹介した作品を「すぐに読みたい」という人には、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。
「BOOK☆WALKER」などのマンガストアなら、無料で試し読みができますよ。
読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」
「風子のいる店」は現時点で電子書籍化はされていません。「漫画全巻ドットコム」や「amazon」などでコミックスが購入できます。人気の漫画も全巻まとめて買える【漫画全巻ドットコム】


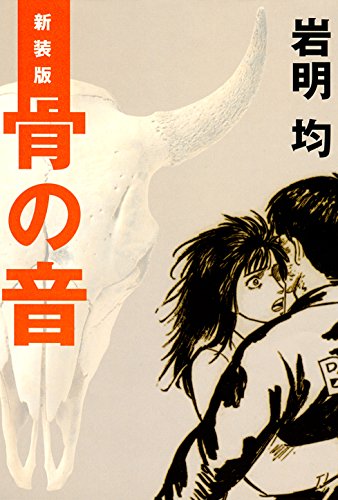

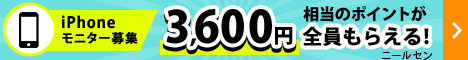





0 件のコメント:
コメントを投稿