 |
| 七帝柔道は主に寝技による死闘が展開 |
自伝的小説で「青春ストーリーが読みたい」人にもピッタリ
日本を代表する武道&格闘技といえば、柔道です。
国際的なスポーツとして海外でも競技者・愛好者がたくさん。「2020年東京五輪」で日本は計12個のメダルを獲得。
まさに、お家芸。「柔道ニッポン」として人気の武道&スポーツです。
一方で、柔道や格闘技ファンから熱い視線を浴びている「もう1つの柔道」があります。
それが「七帝柔道」です。
柔道は国際スポーツ競技として発展するため、細かいルールや規定を導入してスポーツ化。
一方の七帝柔道は古来から伝わる「柔術」そのもの。競技としては7つの旧帝大だけで行われています。
ただ試合や練習の様子は一部でしか紹介されていないため、若い柔道愛好者やファンから悩みの声がたくさん上がっています。
「七帝柔道って、どんな感じなんですか? 歴史やルールが知りたい!」
「七帝柔道の人たちがやっている練習って、厳しいの? 内容を教えてください」
「強くなりたくて七帝柔道に興味があります。試合や練習の内容がイメージできるような本って、ありますか?」
そんな悩みを解決できる本が、作家・増田俊也さんの「七帝柔道記」です。
増田さんが競技者だっただけに七帝柔道の歴史&ルールなどの基礎知識や内容、魅力がタップリ。この記事では作品の中で展開されている、
- 七帝柔道の歴史とルールを主人公の増田さんが分かりやすく説明。
- ひたすら畳の上で展開されるストイックで過酷な練習と内容。
- 息詰まるほどリアルで迫力のある対戦シーン。
- 過酷な練習の意味を問い続ける姿へのシンパシー。
上記の4つの見どころ&魅力を紹介・解説します。
作品は増田さんの体験をベースにした自伝的な小説。だから「面白い青春小説が読みたい」という方にもピッタリ。
記事を読めば七帝柔道の基礎知識が分かり、作品のページを開きたくなりますよ。
「七帝柔道記」って、どんな作品なの?
著者は小説家、ドキュメンタリー作家の増田俊也(ますだ・としなり)さん。名古屋芸大芸術学部で客員教授も務めています。
「七帝柔道記」は「月刊秘伝」で2008年1月号から2010年10月号まで連載。
2013年2月に角川書店から単行本として刊行。2017年2月には文庫本も発売されています。
女性マンガ家の一丸さんがコミカライズし、「ビッグコミックオリジナル」などで2014年から2019年まで掲載。単行本は全6巻。
2016年にはNHKーFM「青春アドベンチャー」でラジオドラマ化されています。
さらに2024年3月には「七帝柔道記 Ⅱ 立てる我が部ぞ力あり」がついに刊行されています(後述)。
★自伝的青春記・私小説&あらすじ
高校時代から柔道に打ち込んでいた増田は、地元・名古屋大柔道部の練習に参加。寝技のあまりの強さにビックリ。名大柔道部は「七帝柔道」を実践している七帝の1つ。その洗礼を浴びた。さらに部員から勧められた、七帝柔道の源流である「高専柔道」を描いた井上靖さんの「北の海」を読んで感動。
でも作品を読み進むうちに世界観にハマり、体中が震えるほどの感動が味わえるんです。
ここからは作品の4つの読みどころ&魅力について、1つずつ紹介・解説します。
1.七帝柔道の歴史とルールを主人公の増田さんが分かりやすく説明
「七帝柔道記」では、七帝柔道の歴史や実際に行われているルールが紹介されています。
高校時代の名大での体験をきっかけに増田さんが体感していく「七帝柔道」。
主人公の一人称でストーリーが進行。増田さんの視線や言葉で七帝柔道の歴史や内容が語られ、メチャ分かりやすいんです。
★高専柔道が源流
七帝柔道は北大、東北大、東大、名大、京大、大阪大、九州大。旧帝大の7大学の柔道部で行われています。
主にというか、ほぼ寝技。投げを狙う相手を引き込んで寝技で抑え込むか、絞めるか、関節を極めるか。
合戦で武士たちが生き残るために使った「柔(やわら、体術)」「柔術」がベース。まさに兵法。だから実戦的なんです。
このスタイルは戦前に行われていた「高専柔道」を継承したもの。
高専柔道は戦前の旧制高校・大学予科・旧制専門学校の大会で行われていました。
当然ながら立っての投げ技OK。見事に投げれば一本勝ち。でも立ち技を狙わず寝技に引き込むこともOK。これが「高専柔道」の特徴です。
寝技は、立ち技ほど技術的才能がなくても練習量次第でどんどん上手くなって強くなることが可能だそうです。
試合は団体戦のみで抜き(勝った選手が次戦に臨む)スタイル。しかも多人数での対抗戦でした。
出場選手を増やすため未経験者や白帯の選手が多くなる。短期間で強くなるため、うってつけなのが寝技なんです。
この高専柔道を舞台にした小説を発表しているのが作家・井上靖さん。
沼津中学時代に旧制第四高校(現在の金沢大)の高専柔道家と対戦し、同校を目指した体験を描いた「北の海」は七帝柔道家のバイブル。
作品では「練習量がすべてを決定する柔道」で「それこそが寝技」という言葉が登場しますが、まさに高専柔道&七帝柔道の本質です。
★GHQに禁じられた柔道
戦後の日本では、占領軍であるGHQに柔道や剣道などの武術が禁じられました。理由は「軍国主義的」だから。
存続の危機に陥った柔道を復活させるために奮闘したのが、柔道の父で講道館の創始者・嘉納治五郎さん。
「軍国主義」的な要素を消して、国際的な競技スポーツだよとGHQにアピールするために生み出されたのが、現在主流の講道館ルールです。
いきなり引き込む寝技はダメ、投げ技からの移行ならOK。立ち技&寝技でこう着したり場外の場合は「待て」でリスタート。
「技あり」2つで一本勝ち。有効、効果などのポイント制。五輪など国際競技のルールの源になっています。
「このままでは本物の柔道が日本から消滅してしまう」「七帝柔道がとるべき道は、スポーツ化していく講道館柔道に対し高専柔道を受け継いだ武道としての柔道ではないか」
七帝柔道ルールは講道館柔道&国際ルールとは違っていたり、禁じられたモノがたくさんあります。
- 試合は団体戦。1チーム15人で勝った選手が次戦に臨む抜き制。時間は先鋒から13人目まで6分、副将・大将戦は8分。
- 勝敗は一本勝ちだけ。有効・効果はなし。「技あり」2本で一本勝ち。1本だけでは勝てない。
- 一本勝ちは、投げ技なら相手の背中を畳につけること。抑え込みでは30秒。
- 関節技など固め技は相手が「参った」というか、相手が体か畳を手もしくは足で2回叩く(タップ)と一本勝ち。
- こう着しても「待て」はなく「場外」もなし。客席などで戦った場合は「そのまま」で止めて中央に戻り再開。
- 15人が戦い終わり引き分けの場合は、代表選手による8分の代表戦。決着がつくまで何度でも代表を選んで戦う。
七帝柔道では一本勝ちを狙う「抜き役」と引き分けを狙う「分け役」があります。
「抜き役」は1勝を狙うポイントゲッター。「分け役」は「抜き役」の攻撃をしのぎ引き分けを狙う、大事な役なんです。
守りに徹しても消極姿勢で減点はされない。一本勝ちが確実な「抜き役」と引き分けるのは「勝ち」と同じ価値がある。
「抜き役」が1勝し、残り全員が引き分ければ勝つことができる。
だから試合では引き分けが多い。試合時間も2時間以上。代表戦にもつれ込むと、午前0時を回ったことがあったそうです。
七帝柔道部では選手を集めるため未経験者もスカウト。大学から始める白帯の人が多い。
だから「分け役」として徹底的に鍛える。4年間鍛え上げられると、講道館柔道の黒帯より強くなる人が多いそうです。
でも練習がハードすぎ。辞める人がほとんど。増田さんは過酷な練習を紹介していますが、その内容がリアルすぎて…。
2.ひたすら畳の上で展開されるストイックで過酷な練習と内容
増田さんは高校時代、講道館スタイルを経験した有段者。名大の練習に参加して七帝柔道を知り、北大で門を叩きました。
増田さんが入学当時の北大は、毎年7月に行われる7大学による対抗戦「七帝戦」で2年連続最下位。
部の目標はただ1つ、優勝。でも部員は年々激減し低迷から脱出することにも苦戦していました。
立ち技ができる増田さんは有望株。2浪して体力不足の新人を生かすために、入部直後から「分け役」として鍛えられたんです。
★ひっくり返されて絞められるカメ
ただ苦しそうな息づかいとうめき声だけが聞こえる。これほど殺伐とした光景を見たのは初めて。私が経験したことがない苦行の場。
亀のように畳に四つん這いになって手足を縮め、相手の寝技を防御する姿勢。
「分け役」には最も大事で基本的な防御スタイル。でも軽くひっくり返されてグチャグチャにされる。
関節を極められ、頸動脈を絞められる。黒帯なのに歯が立たない。
寝技は攻撃法と防御法が交互にせめぎ合いながら進化しているもの。
さらに練習後は、100回×3セットか300回×1セットの腕立て伏せで閉める。トンデモない練習の日々が続くんです。
 |
| 三角絞めが極まった。腕と肘がきしむ |
★「参った」しても技を解いてもらえない
7月の七帝戦に向けて、北大柔道部の練習はさらに過酷になっていきます。
通常の練習に加え、5月のゴールデンウイークでの新歓合宿。6月の七帝合宿。さらに一日中行われる延長練習。
入部当時、1年目(新入生)は乱取りの回数を体力に合わせて決めることができたけど、次第に乱取りに参加することが多くなっていく。
さらに乱取りでは「参った」が許されていたけど、七帝が迫るうちに「参った」しても技を解いてもらえなくなる。
先輩は「動け!」「逃げろ!」。七帝戦を想定した実践練習になっていくんです。
★落とされて三途の川を見た
絞められたり極められたり。抑え込まれて動けないのに「逃げろ!」。口に腹を合わされて息ができず窒息寸前に…。
「参った」と手を叩いているのに許してもらえない。技を解いてもらえない。「息ができない! 殺してください! お願いです!」
自分の非力を呪いながら、泣きながら手を叩き続けた。口から泡を吹き、よだれをたらしながら悶絶するうち闇の中へ吸い込まれて意識を失った。落ちることがこれほど苦しいとは思わなかった。
死んだはずの祖母が川の向こうで手招きしている。これが三途の川なんだと思った。
そして先輩たちは「増田さんなら強くなれる。力が伸びる」。そう確信して鍛えていたんです。
 |
| 七帝では初めて柔道を始める白帯の人が多い |
★恐怖の伝統行事で大爆笑
強くなるため。七帝戦で優勝するため。北大柔道部員たちは目的を達成するために4年間、道場で汗や血を流します。
「ぼろぼろにされ、屈辱感に打ちひしがれ、トイレの個室に入り、鍵をかけて泣いた」「練習中、頭の中には楽しく遊んでいるであろうクラスメートたちの顔が浮かんでしかたなかった」
そんな思いとの戦いの日々を続けている。
でも、これだけ重苦しくて殺伐とした練習の描写を読み続けるのはけっこうキツイ。
増田さんはしっかり〝味変〟をストーリーに組み込んでくれています。
最終日には怖いOBたちが集結し、新入部員はあいさつしないといけない。寮歌も披露しろと命じられる。北大・恵迪寮に伝わる有名な寮歌「都ぞ弥生」などを、激しい練習後に練習させられる。先輩たちは「柔道部員になるための通過儀礼」でOBに粗相するなと説明。OBが怒った場合は「俺たちが1年目を守る」と散々脅かされる。
★バツグンに面白い青春小説
七帝戦が迫る中、初夏に行われる北大祭でのエピソードも秀逸です。
苦しい練習ばかりの柔道部も参加。なぜなら遠征費を稼がないといけないから。
柔道部は「中国四千年の味 やきそば研究会」で出店。お店を運営するため、歴代の部員が書き記したノウハウノートがある。
その内容がメチャ面白い。このエピソードの詳細も、ぜひ作品でお読みください。
増田さんら1年目を落としまくっている先輩たちも、本当は優しい人ばかり。
練習後に後輩たちの体を大きくするために、食事に連れていってあげたり。
「分け役」は「抜き役」より劣るという考えだった増田さんに、先輩の和泉唯信さんが「分け役」の大切さを説明するシーン。
七帝柔道にかける思いが、ものすごく伝わってくる名シーンです。
作品は重苦しくて厳しい練習の日々の描写が多いけど、こうしたエピソードが雰囲気を和らげてグイグイと読み進んでしまう。
「七帝柔道記」は、バツグンに面白い青春小説なんです。
3.息詰まるほどリアルで迫力のある試合のシーン
過酷な練習の成果を試す七帝柔道の試合も、臨場感あふれるタッチで描かれています。
柔道部の最大の目標である七帝戦。1チーム15人での抜き勝負だけに、メンバーの布陣での戦略的な駆け引きが面白いんです。
★勝敗を左右するメンバーの布陣
「抜き役」は必勝。「分け役」は相手の「抜き役」と引き分けることが使命。
これを前提に監督は布陣を熟考します。相手のエース「抜き役」が何番手で登場するかを読んで適切な「分け役」を配置したり。
先行逃げ切りするため先鋒から「抜き役」を並べて1勝をもぎ取り、後は「全分け」を狙ったり。
部員不足で1年目を起用せざるをえない北大だと、経験不足の新入部員を実力者の間に守るように置いたり。
両チームの監督の読み合いで布陣が決まる。この決断が勝敗を左右するんです。
★痛みと恐怖に打ち勝つ「分け役」の真骨頂
増田さんが1年目。昭和61(1986)年度の七帝戦。北大は大阪大(阪大)と対戦、約2時間にわたる死闘が展開されました。
作品中の対戦描写はキレがあって迫力満点。畳の上の選手たちの息づかいが伝わってくるほどリアル。
七帝戦での試合の内容を知りたい方なら、攻防の様子をイメージできて参考になります。
対戦シーンはぜひ作品で読んで欲しいので、ここでは大会の流れと「七帝柔道」を象徴する対戦を紹介します。
北大は先鋒から四鋒(4番目)まで引き分け。五鋒戦では5年目で北大最強の山岸裕さんが、阪大2年目の朝日英治さんと対戦。
開始早々、山岸さんが寝技で下になって攻め続け得意の腕緘(がら)みを極めた。朝日が肘の痛みに顔を歪める。肘は完全に極まっている。阪大陣営は「耐えろ!」。北大からは「折れ!」。肘は完全に背中の裏までまわっていたが、朝日は参ったをしない。
肘や腕を折られる恐怖と痛みに耐えて、北大最強の「抜き役」と引き分けたことは「分け役」の真骨頂といえます。
増田さんは六将戦(10番目)で初陣を飾りますが、抑え込まれて一本負け。北大は激戦の
末、敗退。敗者復活戦に回りました。
★敗者復活戦での死闘の末に…
七帝戦は1回戦で負けても、敗者復活戦で勝てば再び優勝争いに参加できるシステム。北大は敗者復活戦で名大と対戦しました。
オーダーの序盤に「抜き役」を並べ先行逃げ切りで臨んだ北大は、中盤まで2人差をつけてリード。でも1人差に追い上げられる。
分ける自信なんてまったくない。緊張して出番を待っていると主将の金澤さんに呼ばれた。「おまえ、俺たちのために死ねるか」「死ぬ気でいけば、絶対に分けられる」
負けたら引退となる4年目の先輩たちの思いに、見事にこたえました。
でも北大は終盤に追いつかれて代表戦にもつれ込み、代表2人目で敗退。3年連続最下位となりました。
4.過酷な練習の意味を問い続ける姿へのシンパシー
酒を注いでくれた4年目の先輩たちの目は涙で充血していたが、あまりに優しく、柔らかだった。「辞めるなよ。練習苦しいだろうが最後まで頑張れよ」。みんな同じことを繰り返し言った。
「なあ、辞めんなよ。最後までやれば絶対にいいことがある…」
★ボロボロにされても練習する意味が分からない
試合で最後にモノをいうのは体力。和泉主将の方針のもと、北大柔道部は過酷な寝技乱取りの本数を増加。
他大学との練習試合。北海道警への出稽古。ウエートトレーニングの導入。苦行僧のように極限まで肉体をいじめました。
畳に叩きつけられ、関節を極められ、絞められる。板壁に押さえつけられ、そのまま落とされる。活を入れられて息を吹き返し、また落とされる。その繰り返し…。
七帝戦まで12人いた1年目は次々と辞めていく。体はケガでボロボロ、疲労は蓄積していく。
増田さんの親友・竜澤宏昌さんは「差がありすぎて練習する意味がない」と和泉主将に食ってかかったほどでした。
★たどり着けない答え
秋がすぎて冬を迎え、北大キャンパスが深い雪に覆われても過酷な練習は継続している。
将来は柔道で飯を食っていくわけじゃないのに、なぜこんな苦しいことをやっているのか?他の学生たちはスキーやテニスを楽しみ、彼女とデートしたりしている。自分たちがやっていることに何の意味があるのか?
でも答えにはたどり着けない。悩み、苦しみ、それでも涙を流して練習を続ける姿にめちゃシンパシーを感じてしまうんです。
 |
| 北大のポプラ並木 |
★「思いをつなぐ」ことの尊さ
昭和62(1987)年。増田さんは2年目になり、柔道部にも新入生が入部。練習は過酷になり、他校との練習試合でも苦戦が続きます。
2度目の七帝戦に向けて体をいじめる増田さんにも、トラブルが発生して…。
この後のストーリーはメチャ引きずり込まれて劇的で、感動的。ぜひ作品をお読みください。
そして、増田さんら北大柔道部員たちは「七帝柔道を続ける意味の答え」にたどり着けるのか?
増田「北大は勝てるんでしょうか…。勝てる日が来るんでしょうか」和泉「来る」「進むんじゃ。後ろを振り返りながら進みんさい。繋ぐんじゃ」和泉「思いは生き物なんじゃ。思いがあるかぎり、必ず繋がっていくんじゃ」
思いをつなぐこと、共有し続けることの尊さ。人間だからこそできる、思いと歴史の継承。
和泉さんの広島弁が心に染みわたる名シーンです。
まとめ・続編「七帝柔道記Ⅱ」で北大柔道部の〝その後〟が描かれる
ここまで「七帝柔道記」の見どころ&魅力について紹介&解説してきました。
- 七帝柔道の歴史とルールを主人公の増田さんが分かりやすく説明。
- ひたすら畳の上で展開されるストイックな過酷な練習と内容。
- 息詰まるほどリアルで迫力のある対戦シーン。
- 過酷な練習の意味を問い続ける姿へのシンパシー。
上記の4つの読みどころ&魅力は、七帝柔道の歴史と基礎知識や試合・練習内容を教えてくれる。秀逸な青春小説としても楽しめるんです。だから、
「七帝柔道って、どんな感じなんですか? 歴史やルールが知りたい!」
「七帝柔道の人たちがやっている練習って、厳しいの? 内容を教えてください」
「強くなりたくて七帝柔道に興味があります。試合や練習の内容が分かりやすくてイメージできるような本って、ありますか?」
そんな悩みを一発回答で解決してくれます。
そしてぜひ読んでいただきたいのが、続編です
増田さんは2023年5月23日発売の「小説野生時代」6号から連載をスタート。
「七帝柔道記Ⅱ〜立てる我が部ぞ力あり」のタイトルで、2024年3月に単行本が発売されました!
続編が刊行される前、増田さんはツイッター(現 X )で、警察小説を完成させた後に「七帝柔道記Ⅱ」の単行本化に取りかかると投稿。
増田さんのこのツイートを読んだことが、この記事を書くきっかけ。そのために改めて作品を読み返したら涙腺が崩壊しました(苦笑)。
まだ読んだことがない人は、この記事を踏まえて作品を読めば絶対にハマります。
そして続編を楽しむ上でも「七帝柔道記」を、ぜひお読みください。
また「七帝柔道記Ⅱ」に関しても、当ブログで紹介しています。
「七帝柔道記 Ⅱ 」北大は七帝戦で勝てるの?主人公はどうなるの?感動のスポーツ小説3つの読みどころ
当ブログでは他にも「格闘技小説・マンガ」を紹介しています。ぜひご覧ください。
鬼の木村、異種格闘技…闘うシーンや心理描写がリアルすぎて秀逸な「格闘技小説」3作品
伝説の格闘技プロレス「UWF」の崩壊、解散の裏事情が分かる「暴露本」ベスト3
「プロレスマンガの最高傑作を教えて」という人に読んでほしい名作ベスト3を徹底解説
「七帝柔道記」をすぐに読みたいという方には、スマホなどにダウンロードすれば即読みできる電子書籍版がオススメ。
「BOOK☆WALKER」などのブックストアなら無料で試し読みができますよ。
読みたいコミックが48時間100円から借りられる「Renta!」
月額840円でマンガ20000冊以上読み放題「BOOK☆WALKER」
※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して本や商品を紹介しています。
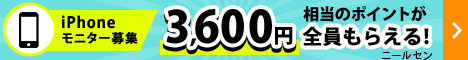

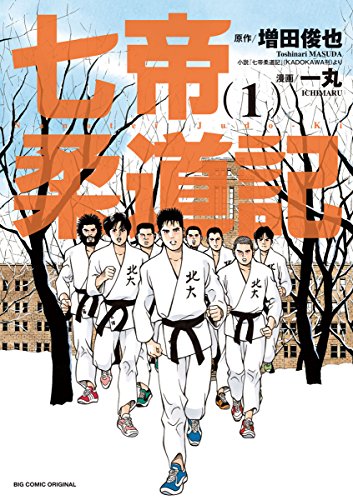

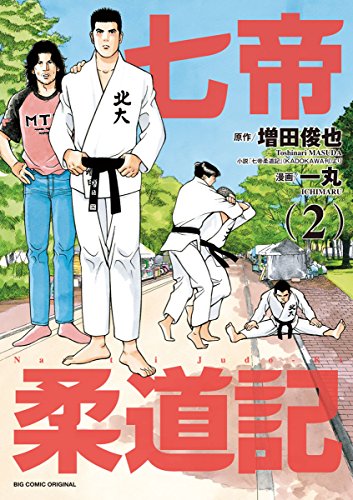
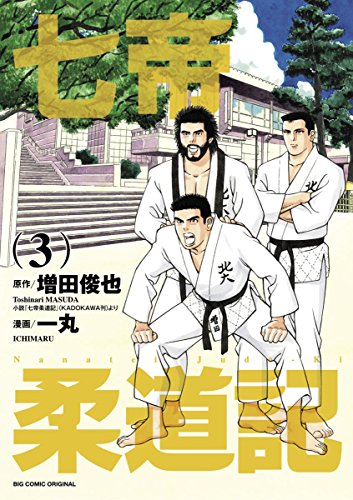
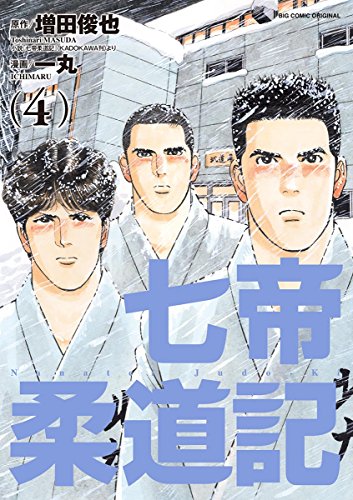
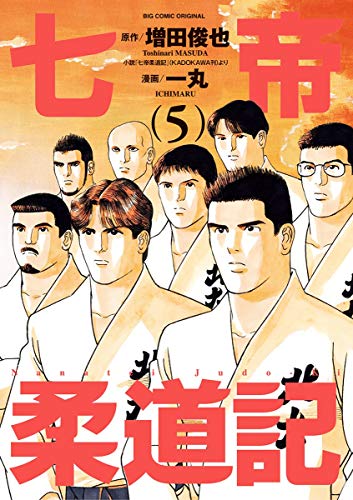
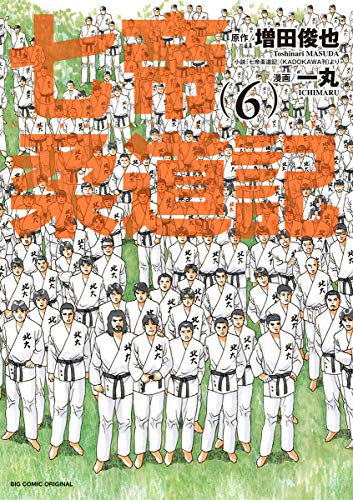





0 件のコメント:
コメントを投稿