英雄たちの活躍を読むだけで知識が頭に入ってくる
中高生や大学受験生の方たちの中で、東洋史や現代国語の熟語などが「覚えられない」「苦手…」と苦戦している人たち。
きっと、少なからずいらっしゃると思います。
そんな方におススメなのが、日本の大衆文学で、昔も今も読み継がれている大ベスト&ロングセラー小説、吉川英治さん作の「三国志」です。
古代中国の三国時代をかけ抜けた英雄たちの勇姿を、昭和の大作家・吉川さんが深い造詣を駆使し、自身の解釈でアレンジして描いた名作。
約2000年前の物語ながら壮大なスケールがファンを魅了。小説、マンガ、ドラマ、映画、ゲームにも舞台が広がる人気ぶり。
三国志がすごいのは、これだけじゃありません。
英雄たちの活躍を読み進めるだけで、日本、中国を含めた古代東洋史、さらには熟語、ことわざまで覚えることができる。
日々の勉強に努力する学生さんや受験生にとって、とてもためになる最高の参考書なんです。
ここでは、三国志が持っている、
- 読むだけで古代東洋史をマスターできる
- 四文字熟語が覚えられる
- 有名なことわざも勉強できる
3つの魅力を解説。この記事をお読みになれば、
「覚えるのが苦手…」と思っている中高生や受験生の方には、「こうやればいいんだ」と、今後の勉強方法の参考になりますよ。
三国志とは
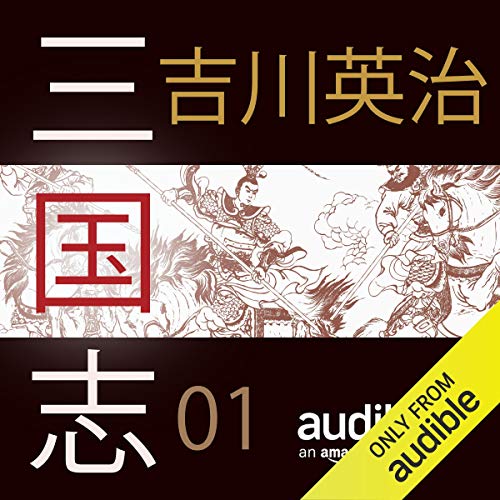
小説「三国志」は、1939(昭和14)年に「中外商業新報」(現在の日経新聞)で新聞連載小説としてスタート。
1943(昭和18)年に終了しましたが、吉川さんは戦時中も執筆、連載されました。
戦後に単行本化、文庫本化。最近では電子書籍化もされ、昔も今も愛されています。
作品の舞台は、西暦100年代後半の後漢末期から200年代初頭の三国時代の中国大陸。
魏、呉、蜀の三国による興亡の歴史がつづられています。
その原本は、西暦280年ほどに西晋で成立した、三国に関する歴史書。
三国それぞれの歴史的エピソードや風俗などを歴史家の陳寿がまとめたもの。
それを底本に、1300~1600年代まで大陸に君臨した明の時代、歴史小説として描かれた「三国志演義」が成立。
少年時代から、それらを通読していた吉川さんが、自身の知識や解釈を加えて書き上げたのが吉川版「三国志」です。
「三国志演義」と同様、吉川版の主人公は蜀漢の祖・劉備玄徳。義弟の関羽、張飛や勇将・趙雲、軍師・諸葛孔明の活躍。
ライバルの魏王・曹操、呉帝・孫権との知略、戦略を駆使した闘いは、昔も今もファンを虜にしています。
1.日本古代史と中国史を合わせた東洋史としてマスターできる
先にも書きましたが、三国時代は約2000年前、西暦100年代後半の後漢末期から200年代初頭。
魏・呉・蜀が覇権を巡って三つ巴の闘いを展開していたワケです。
この時代の日本を見てみると、なんと女王・卑弥呼で有名な邪馬台国が君臨していた「倭国」の時期なんです。
しかも、三国と邪馬台国には密接な関係があるんです。
この時代のアジアの外交は「遠交近攻」がテーマ。
遠い国と手を組み、近隣の敵国を挟み撃ちして攻撃、もしくは外交的圧迫を加える外交テクニックです。
邪馬台国は周辺の国々との抗争で優位に立つため、中国大陸と手を組む必要がある。
魏も遠方の倭国と関係を持つことで呉・蜀へ圧迫をかけたい。
そこで行われたのが邪馬台国による魏への使者派遣。
魏は卑弥呼に「親魏倭王」の金印を授け、魏帝が卑弥呼を、倭国を統治する王として認可したのです。
これは日本の古代史に出てくる「魏志倭人伝」に記述されています。
そもそも「魏志」とは魏の歴史書。魏・呉・蜀が三つ巴の闘いを演じていた時に、卑弥呼が使者を送ってきたんです。
まずは、この時代背景を覚えて三国志を読んでください。グッとおもしろさが増してきます。
日本と中国の古代史、古代東洋史が理解できるんです。
日本史や世界史を必須科目にしている中高生、受験生には、三国志を読むことは大変なアドバンテージになります。
 |
| 関羽は中国では商売、学問の神様として信仰されています |
2.みんなが知っている熟語には三国志発祥が多い
吉川さんも作品中で言及していますが、「三国志」からは誰もが知っている熟語が数多く生まれているんです。
ここでは代表的なモノを紹介します。
苦肉の計
これは「三国志」の中でも有名な戦闘、「赤壁の戦い」から生まれた熟語です。
魏に対し兵力差で圧倒的に不利な呉の大都督・周瑜は、劣勢を挽回するため一計を案じます。
陣営の重鎮で老将の黄蓋とはかり、黄蓋を裏切者に仕立てて魏陣へ送り込むことを決定。
魏軍を率いる曹操をだますため、呉兵たちの目前で黄蓋を呉への不忠者としてムチによる百叩きの刑に処します。
呉陣に侵入していた魏のスパイはこの旨を曹操に報告。信用した曹操は黄蓋を迎え入れることを決意。
体中に傷を負った黄蓋は密かに船で脱出し魏陣に投降すると約束しますが、その船には着火剤を満載し火をつけて魏の船団に突入。
船団は火だるまと化し、魏軍は総崩れ。黄蓋が自身を苦しめて相手を騙したことから「苦肉の計」と呼ばれるようになりました。
破竹の勢
魏は蜀を滅ぼしたが、その後、家臣だった司馬一族に乗っ取られ、国名を晋に改めます。
その晋は呉を討ち中華の統一を狙います。
だが呉が抵抗し苦戦。その際、晋の勇将・杜預が「わが軍は竹を割くがごとき勢いにあり、一気に攻めれば呉を滅ぼせる」と主張。
その言葉通り、呉を攻め立て滅ぼしました。
3.ことわざも有名
三顧の礼を尽くす
優秀な軍師を探し求めていた劉備は、「臥竜」と高く評価されながら在野に暮らす諸葛孔明を迎えようと決意します。
劉備は関羽、張飛を連れて孔明の庵を訪ねますが、旅に出ていたり、外出していたり。
そして三度目の訪問で孔明は在宅だったが、お昼寝中。
劉備は目が覚めるまで待ち、ようやく孔明と会談。軍師として迎えることができました。
目上の人が礼を尽くしてお願いするという意味です。
泣いて馬謖を斬る
蜀の大軍師・諸葛孔明。
彼が、その才能を愛していた馬謖が命令を守らず、魏との戦いに敗北したため、その責任を問うため泣きながら馬謖を切った故事。
組織の規律を守るためには、たとえ優秀な者でも違反をすれば厳しく処分することが必要という意味です。
まとめ・楽しめて学べる最高の参考書
私はウン十年前の大学受験の際、私立文系で英語・国語・日本史を選択して臨みました。
英語がからっきしだったので浪人しましたが、国語の方は四字熟語や故事に関しては、三国志などで目にしていたのでクリア。
歴史に関しては、マンガ家・諸星大二郎さんの代表作「妖怪ハンター」が大好き。
この作品が題材にしていた記紀神話や民俗学に興味がありました。
さらに高校時代に三国志を読んで、その時代に卑弥呼が邪馬台国を治めていたことを知ってから歴史オタクと化しました。
そして司馬遼太郎さんの歴史小説などを読みふけったことで、教科書の内容が物足りないぐらい理解することができました。
私にとって三国志は、歴史や国語の勉強を好きにしてくれたきっかけであり、最高の参考書でした。
吉川さんの文体は非常に読みやすく丁寧で、読み進めることで現代文や長文の読解力の向上にもつながります。
中高生や受験生の方たちにとっても、三国志を読むことで歴史や国語の苦手意識がなくなり、これからの勉強に役立つこと間違いなしです。
当ブログでは「三国志マンガ」についても紹介しています。
また歴史に関する小説・マンガも解説しています。よろしければ、ごらんになってください。
「三国志」を「すぐに読みたい」という方は、スマホなどにダウンロードしてすぐ読める電子書籍版がオススメです。
「BOOK☆WALKER」などの電子書籍ストアなら無料で試し読みができますよ。
※当ブログではアフィリエイトプログラムを利用して本や商品を紹介しています。
リンク
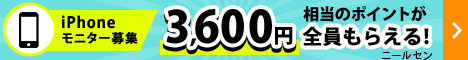






0 件のコメント:
コメントを投稿